ライブラリー

【バフェットのポートフォリオ解説】アップル、バンカメ追加売却、新規投資はドミノ・ピザとプール
ウォーレン・バフェット率いるバークシャー・ハサウェイ(BRK.B)の2024年9月末時点でのポートフォリオが、11月14日に米証券取引委員会(SEC)に提出された報告書「フォーム13F」にて明らかになりました。本記事では、バフェット氏のポートフォリオを紹介の上、今回新たに投資が明らかになったドミノ・ピザ(DPZ)とプール(POOL)について解説します。2024年12月末時点でのポートフォリオについては、以下の記事をご覧ください。バフェットポートフォリオの中身アップル株、バンカメ株を追加売却バフェット氏は集中度の高いポートフォリオを運用していることで知られ、上場ポートフォリオは上位5銘柄で約70%、上位10銘柄で約90%を占めています。上位保有銘柄アップル(AAPL) : 26.2%アメリカン・エキスプレス(AXP) : 15.4%バンク・オブ・アメリカ(BAC) : 11.9%コカコーラ(KO): 10.8%シェブロン(CVX): 6.6%オキシデンタル・ペトロリアム (OXY): 4.9%ムーディーズ(MCO): 4.4%クラフト・ハインツ(KHC): 4.3%チャブ(CB): 2.9%ダビータ(DVA): 2.2%4-6月に続いて、7-9月もアップル株の約4分の1を売却。バークシャーの2024年6月末時点のポートフォリオでは、アップル株は3割近くを占めていましたが、今回の株式売却により保有比率は26%へ低下しました。また、ポートフォリオの中で2番目に大きなポジションを占めていた、バンク・オブ・アメリカ株の保有も約4分の1削減し、アメリカン・エキスプレスに次ぐ3番目のポジションとなりました。投資縮小の理由や意図についてバフェット氏はこれまでのところ明らかにしていませんが、10月以降も継続して、バークシャーはバンカメ株の売却を行なっています。ドミノ・ピザとプール製品の卸売業者への新規投資が明らかにそのほか、注目を集めたのはドミノ・ピザ(DPZ)とプール(POOL)への新規投資です。ドミノ・ピザは世界最大の宅配ピザチェーンで、世界で約2万店舗を展開しています。同社はファストフードチェーン業界全体が減速するなか、第2四半期にプロモーションの頻度を増やさずに、売上を前年同期比7.1%成長させました。しかし、国際市場での純店舗数増加が予定より175~275店舗少なくなる可能性があるとの見通しを受け、7月18日の決算発表後に株価が13%下落していました。一方、プールは北米、ヨーロッパ、オーストラリアに約 440 の販売センターを構える、スイミングプール関連製品の世界最大の卸売業者です。コロナ禍で自宅で楽しめるプールをつくる人が増えたことから、プールの株価は一時急騰していましたが、借入コストの上昇が住宅の修理や改修需要を圧迫し、最近のパフォーマンスは年初来約8%の下落と低迷しています。9月末時点でのドミノ・ピザの保有は約5億4900万ドル、プールの保有は約1億5200万ドルに相当し、どちらもバークシャーにとっては少額の保有となります。手元資金は約50兆円に、自社株買いも見送りバークシャーは2024年7-9月期に346億ドル相当の株式を売り越したため、現金と米短期債保有額を合計した広義の手元資金は9月末時点で3252億ドル(約49兆7600億円)に達し、過去最高値を更新しました。また、自社株買いも2018年第2四半期以降、6年ぶりに見送りました。バークシャーは最低300億ドルの現金を保有することを約束していますが、適正価格で購入できる企業全体や個別株が見つからない場合には、現金を蓄積させることが多くなっています。年次総会でバフェット氏は、「非常にリスクが低く、多くの利益をもたらすと思われる場合以外はバークシャーは投資を急がない」と述べています。市場関係者の間では、バフェット氏は株価が割高だと考えているのか、不況が来ると考えているのか、大型買収のために資金を確保しているのか、それとも引退の準備をしているのか、様々な憶測がとんでいます。バフェットポートフォリオを簡単コピー?ブルーモ証券では、2024年9月末時点でのバークシャーのポートフォリオをワンタップでコピーし、投資を始めることができます。株式のみで構成されるポートフォリオのほか、米短期債を含む手元資金を反映したポートフォリオのコピーもできますし、そこから変更を加えてオリジナルのポートフォリオの作成も可能です。
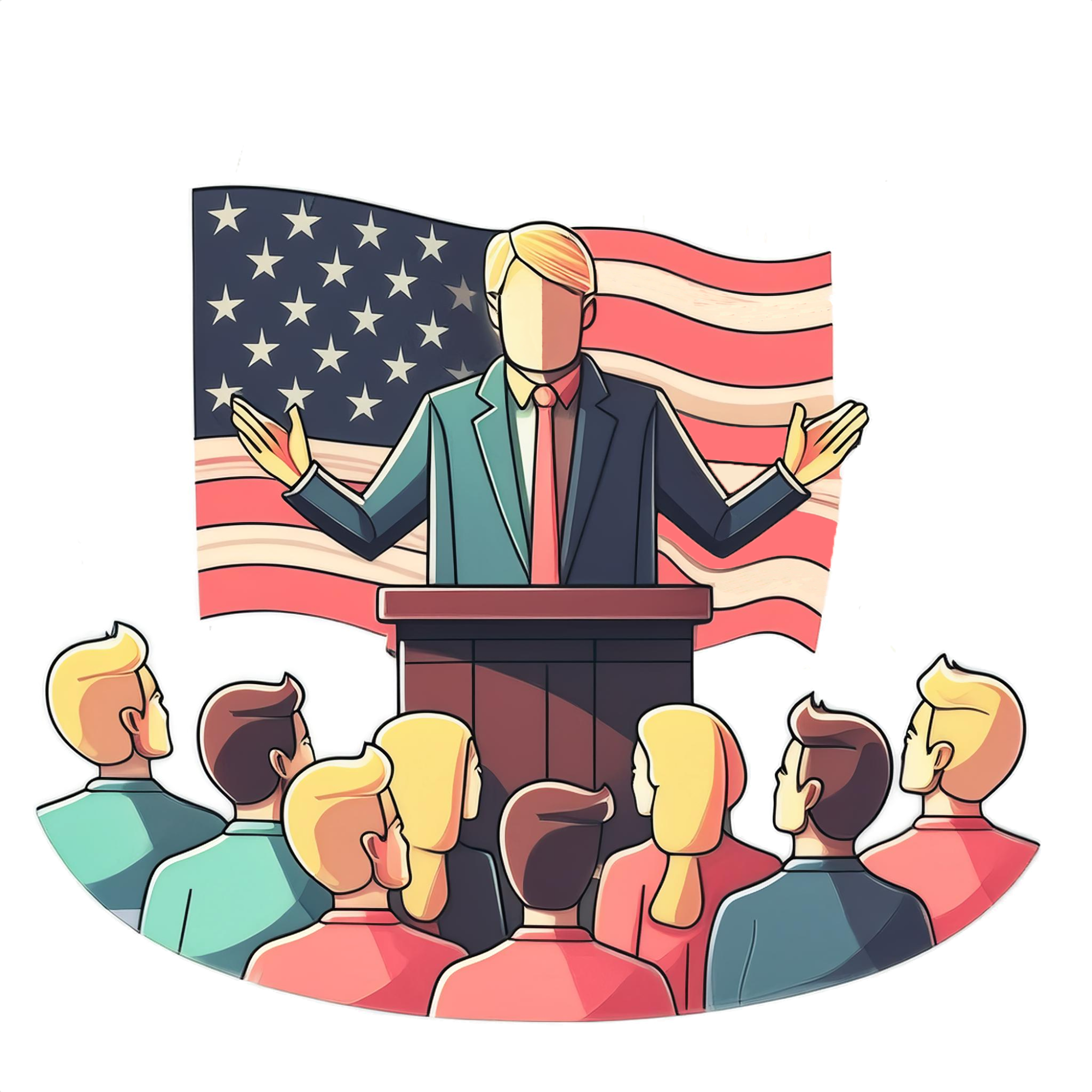
トランプ氏当選で株価急騰、大統領選後の米国株市場の見通しは?
本記事では、ドナルド・トランプ氏の大統領選勝利への米国株市場の反応を解説のうえ、米景気と株価の今後の見通しについて市場関係者の見方を紹介いたします。「トランプラリー」、「トランプトレード」やトランプ氏再選が米国株市場に与える影響については過去の記事で解説していますので、関心のある方はあわせてご覧ください。トランプトレード一色の市場トランプ氏の選挙勝利により、11月6日主要3指数はすべて過去最高値を更新しました。ダウ工業株30種平均は3.6%(約1,500ポイント)と2年ぶりの大幅上昇。S&P 500は2.5%上昇し、ナスダック総合指数は3%上昇しました。トランプ大統領が掲げる規制緩和と減税の公約に対する市場の期待感は強く、経済政策の恩恵を受けると見込まれる銀行、工業会社、中小型株の株価が上昇しました。銀行株トランプ政権は金融規制が緩和されるとの見方が強く、銀行株指数は10.7%急伸しました。 JPモルガン・チェース(JPM)の株価は12%上昇し、史上最高値を更新。ウェルズ・ファーゴ(WFC)とゴールドマン・サックス(GS)はともに13%上昇しました。国債利回りの急上昇も銀行の純利息収入が増加することから、銀行株の上昇を後押ししました。ハイテク・工業株大統領選挙でトランプ氏を支援してきた、イーロン・マスク氏のテスラ(TSLA)は15%上昇。トランプ氏がEV購入に対する補助金の削減や関税の引き上げを実施すれば、テスラは競争から守られるだろうとアナリストらは指摘しています。その他ハイテク企業もトランプ政権から大きな恩恵を受けることが期待され、エヌビディア(NVDA)とグーグルの親会社アルファベット(GOOG)はともに4%上昇しました。ただし、フェイスブックの親会社であるメタ・プラットフォームズ(META)は、マグニフィセント・セブンの中で唯一わずかに下落しました。8月末、トランプ氏はメタのザッカーバーグ最高経営責任者(CEO)に終身刑をちらつかせ、自身に不利な行為をしないよう圧力をかけていることが報道されています。また、規制緩和と保護関税の見通しが工業株の上昇を後押しし、キャタピラー(CAT)は8.7%上昇し史上最高値を更新。3M(MMM)は5.8%上昇となりました。暗号資産関連銘柄暗号資産関連規制が緩和されるとの期待から、ビットコインは約8%上昇し、仮想通貨関連銘柄も急騰しました。仮想通貨取引所コインベース・グローバル(COIN)の株価は31%上昇。マイニング企業のマラソン・デジタル(MARA)は19%、マイクロストラテジー(MSTR)は13%上昇しました。7月末に開催された「ビットコイン2024」カンファレンスにて、トランプ大統領はアメリカを地球上の仮想通貨の首都にし、「戦略的ビットコイン準備金(SBR)」の立ち上げを示唆しています。 中小型株法人税減税や中小企業に対する規制緩和が近づいているとの楽観的な見方を反映し、小型株指数ラッセル2000(IWM)は5.8%の上昇となりました。 不動産・公益株一方、多くの投資家はトランプ大統領の政策がインフレを加速させ、財政赤字を拡大させるとみており、国債供給量増加の見通しが国債価格の下落を後押ししました。住宅ローン金利に影響を与える10年国債の利回りは4.425%に上昇し、金利の影響を受けやすい不動産や公益事業株が下落しました。不動産はS&P500セクターの中で最もパフォーマンスが悪く、2.6%の下落となりした。投資家は住宅ローン金利の上昇が需要を減退させると予想しています。足元では下院が焦点に市場は、共和党が下院の主導権を奪還し、上院、下院、ホワイトハウスのすべてを掌握する「トリプルレッド」を達成できるかどうかに注目が集まります。共和党が下院でも勝利した場合、共和党が政策の決定権を握り、トランプ氏の公約実現を後押しすることになるため、トランプ氏が選挙戦中の公約を実際に実行するかどうかに焦点は移行します。一方、下院で民主党が多数派となった場合は、減税の実現が難しくなる可能性があり、スタグフレーションのリスクにつながる可能性があります。米国株の見通しは好調S&P 500の年初来上昇率は25%と株価は今年すでに大幅に上昇していますが、トランプ大統領の経済政策への期待と堅調なマクロ経済環境から多くの投資家は強気相場が年末まで続く可能性が高いと考え、S&P 500は2024年末までに6,000ポイントを超える可能性が高いと予想しています。また、一部のアナリストは法人税率が実質的に18%に引き下げられ、S&Pの株価収益率(PER)が22倍に拡大することを前提として、S&P 500の2025年末目標を7,000に引き上げています。7,000への上昇した場合、11月5日の終値から約21%の上昇となります。

【米大統領選挙直前】トランプトレード活性化、選挙結果に関わらず好調な銘柄は?
本記事では、米大統領選動向について解説のうえ、選挙結果に関わらず好調に推移する可能性がある銘柄を紹介いたします。11月5日の開票まで2週間を切り、相場要因として選挙トレードの存在感が増しています。過去の選挙結果とセクター別パフォーマンスの関係についても過去の記事で解説していますので、関心のある方はあわせてご覧ください。世論調査は接戦を示すも、トランプトレードが活性化10月中旬に実施された世論調査では、選挙結果を左右する主要な激戦州でカマラ・ハリス副大統領とドナルド・トランプ前大統領両候補の支持率が49%と接戦が続いています。しかし、世界最大の予想賭博市場である「Polymarket」では10月25日時点で、トランプ氏の支持率が61%、ハリス氏は39%とオッズがトランプ氏優勢へと大きく傾いています。10月初めの時点では、予想賭博市場でのトランプ氏とハリス氏のオッズは拮抗していましたが、過去数週間にトランプ氏の勝率が上昇するにつれて、金利上昇・ドル買いが進み、「トランプトレード」が意識されるようになりました。ヘッジファンドのポートフォリオを追跡しているJPモルガンのポジショニング調査部門によると、世界のヘッジファンドはトランプ氏が勝利した場合に良いパフォーマンスを期待できる銘柄を過去数週間に購入し、民主党政権下で良好なパフォーマンスが期待できる銘柄は急激に売られたと指摘しています。ただし、Polymarketにおけるトランプ氏勝利の確率の急上昇は、4,500万ドル(約69億円)を賭けたユーザーによる影響と見られており、当該ユーザーは金融業のバックグラウンドがあるフランス人であると特定されています。選挙リスクを軽減する取引も意識される一方、トランプ氏とハリス氏の接戦のほか、共和党ないし民主党が議会上下両院で多数派を獲得する可能性がどの程度であるのか読めないことから、一部のヘッジファンドは大統領選に向けて特定の投資ポジションを構築することはせず、ボラティリティーを抑える方法や、選挙結果にかかわらず勝てそうな取引に注力しています。UBSグローバル・ウェルス・マネジメントのカート・ライマン氏は、公益株と金融株はどちらの政権下でも好調に推移する可能性があると述べています。公益株は高配当で、経済環境にかかわらず比較的安定したパフォーマンスが期待できるディフェンシブ銘柄であり、AI関連のエネルギー需要の恩恵も受けます。一方、金融株は割安感があるとし、金融業界は最近好決算を発表したと指摘します。また、伝統的なヘッジ手段である金も今年急騰しており、多くの投資家がボラティリティへのヘッジをしていることが伺えます。
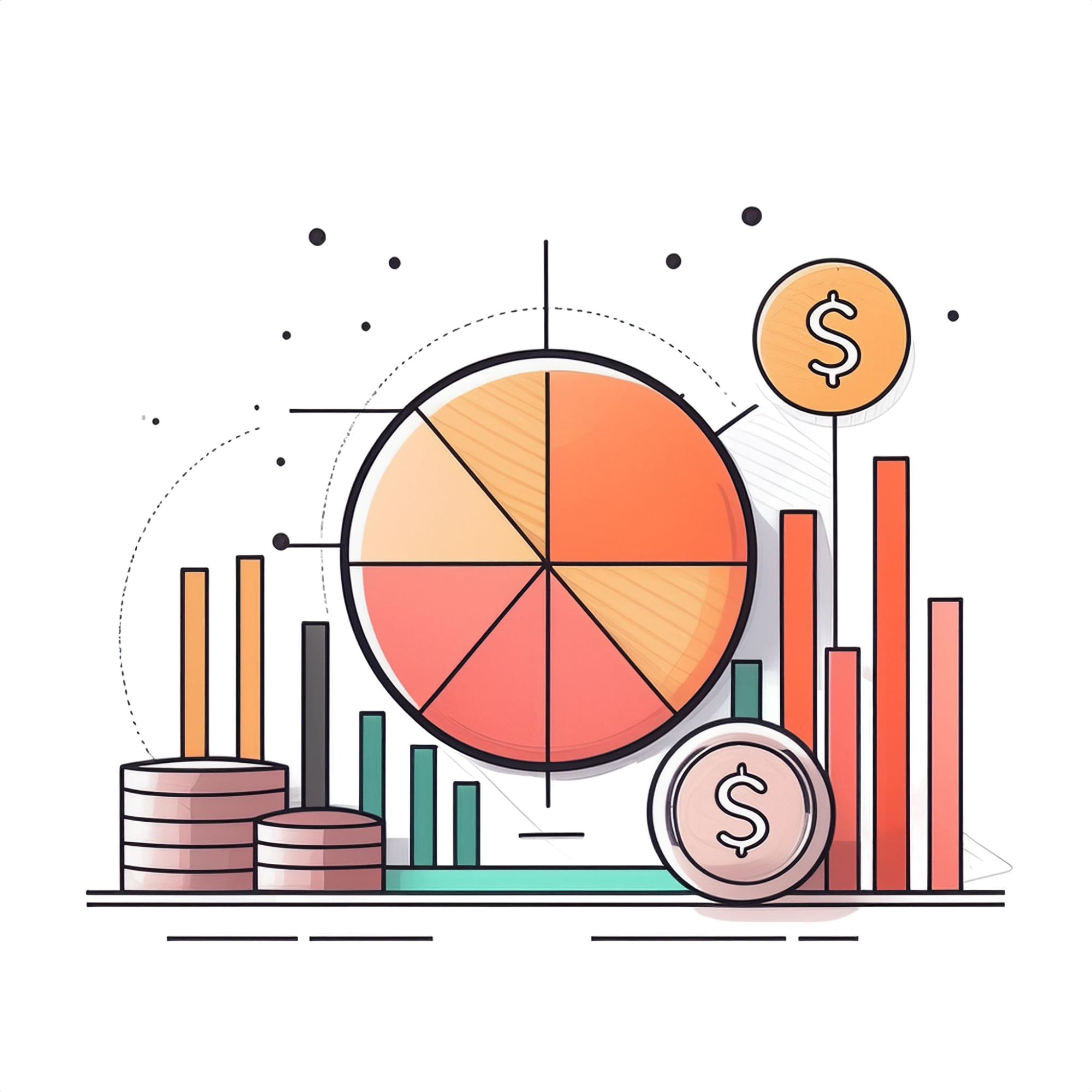
景気動向が鍵?利下げが株価に与える影響
FRB(連邦準備制度理事会)が9月のFOMC(連邦公開市場委員会)にて利下げ転換に踏み切ることが市場で広く予想されています。本記事では「利下げが米国株に与える影響」について解説します。ソフトランディングか景気後退か短期金利の引き下げにより企業や消費者の借り入れコストが下がり、理論的には利下げ後は株価が好調になるとされています。しかし、過去の主要な利下げサイクルを振り返ると市場の反応は様々であり、今後の株価動向を理解するにはFRBが金利を引き下げた背景を考察する必要があります。FRBが経済をコントロールし、ソフトランディングを実現したと市場が認識した場合、株価は堅調に推移することが期待されます。しかし、FRBが景気後退のリスクを受けて反動的に金利を引き下げていると捉えられた場合、株価は調整局面に入ることが考えられます。直近の経済指標のほとんどが米経済の底堅さを示していることから、多くのアナリストやエコノミストにとってソフトランディングは基本シナリオとなっています。7月・8月と予想を下回る雇用統計が発表されたことから景気後退懸念も再燃していますが、ゴールドマン・サックス・グループのエコノミストは、今後1年間に米国が景気後退に陥る可能性は20%と予想しています。市場の関心は「FRBがどの程度利下げを進めていくか、景気がどの程度のペースで減速するか」であり、ソフトランディングになるのかハードランディングになるのかになるのか見極めている状況にあります。大幅利下げにはリスク懸念の声も9月13日時点のFedWatchでは、9月会合で0.25ポイントの利下げを織り込んでいるほか、11月と12月会合の両方で0.5ポイントの利下げを予想しています。一部アナリストは、9月会合で0.5ポイントの利下げに踏み切った場合、米経済の健全性について懸念を生み出す可能性があると指摘します。これは1990年以降のFRBの5回の利下げサイクルのうち、0.5ポイントの利下げでサイクルを開始した2回(2001年と2007年) はいずれも景気後退が続いたためです。またFRB高官の一部は、早計な金融緩和によるインフレ上振れリスクへの懸念を示しています。企業収益や経済動向にも注目一方、2024年のFRBの利下げ幅が市場予想を下回ったとしても、必ずしも株価にとって悪いことではないとの声もあります。ヤルデニ・リサーチのストラテジストは、金利変化よりも企業利益の方が将来の株式市場のリターンを予測する上で信頼できる指標であり、経済成長が予想以上に強く、労働市場の指標もそれほど悪くなく、消費者支出も引き続き増加している環境では、利益が伸び続ける中で株価の上昇余地が広がると述べています。

米大統領選挙で株価上昇が期待されるセクターは?
本記事では、ハリス氏対トランプ氏の接戦が予想される大統領選動向について解説のうえ、過去の選挙結果とセクター別パフォーマンスの関係について紹介いたします。大統領選のアノマリー(規則性や傾向)については過去の記事で解説していますので、関心のある方はあわせてご覧ください。討論会後、支持率は再び横並びに9月10日夜に行われた、カマラ・ハリス副大統領とドナルド・トランプ前大統領による第1回大統領候補討論会を受けて、大統領選動向への注目が高まっています。討論会はハリス氏が勝利したという見方が多く、市場は討論後ハリス氏に有利な兆候を示しました。しかし、世界最大の予想賭博市場である「Polymarket」によると、現在ハリス氏の支持率は50%、トランプ氏は49%と引き続き1ポイント差の接戦となっており、選挙情勢や市場への大きな影響は生じていません。ストラテジストによると、討論会前後のオプション市場ではS&P500は±1.1%の変動しか織り込まれておらず、今回の結果は比較的低いボラティリティーが見込まれていたことと一致しています。税金や関税についての議論は限定的また、株式投資家にとって最大の関心事である税金や関税に関する方針について討論会ではあまり言及がなかったことも指摘されています。ゴールドマン・サックス・グループによると、法人税率を現在の21%から15%に引き下げるトランプ氏の税制案ではS&P500構成企業の利益が約4%押し上げられ、一方法人税率を28%に引き上げるハリス氏の案ではS&P500構成企業の利益を約8%減少させる可能性があると試算しています。関税については、トランプ氏は全ての貿易相手国に一律10%の関税と中国からの輸入には60%超える対中関税を導入する方針を打ち出しています。2回目の討論会は開催されない可能性もハリス陣営は、10月に2回目のテレビ討論会を希望していますが、トランプ氏は11日朝、FOXニュースの番組にて討論会の司会者は不公平と述べ、討論会をもう一回行う気はあまりないと示唆しています。選挙結果とセクター別パフォーマンスネッド・デービス・リサーチ(Ned Davis Research)の調査によると、1972年からの大統領任期全体のデータを見ると、民主党の大統領候補が勝利した後の最初の数ヶ月間は景気循環株が他のセクターを上回り、共和党の勝利後はディフェンシブ株が最も好調でした。景気循環株とは、景気動向によって業績が大きく変動する銘柄を指し、ディフェンシブ株とは、ヘルスケアや生活必需品といった経済全体の状況に関係なく一定の需要と安定した収益がある銘柄を指します。民主党政権下では情報技術と工業セクターが優れたパフォーマンスを誇り、ダウ工業株30種平均を83%上回りました。一方、共和党政権下ではヘルスケアセクターのパフォーマンスが良く、ダウ平均を75%上回りました。ただし、ネッド・デイビス・リサーチは、今年はハリス氏・トランプ氏の両候補とも薬価の抑制に取り組んでおり、選挙結果にかかわらずヘルスケア業界は苦戦する可能性があると指摘しています。大統領選は、考慮すべきリスクの一つアナリストらは、政治ニュースで市場は変動するものの、常に多くの変数が相互作用しており、大統領選はあくまで考慮すべき多くの事柄のうちの1つと捉えています。特に今年は、米経済の不確実性やFRB(米連邦準備理事会)の政策変更に直面し、株式市場のリスクが高まっています。相場が不安定となっても、資産運用の王道である「長期・積立・分散」の原則に従うことが資産運用を成功させるためのコツとなります。「トランプトレード」やトランプ氏再選が米国株市場に与える影響についても過去の記事で解説していますので、関心のある方はあわせてご覧ください。

それでも米国株は魅力的か?米国株投資の強みとリスク
直近の株価と為替の急変動を見て、今後の資産運用に不安を感じる方もいると思います。足下の相場変動から少し距離をおいて考えると、米国株投資には①イノベーションの中心地としての恩恵、②株主還元の徹底した経済構造、③マクロ経済の頑健性といった強みがあり、いくつかのリスクはあるものの、他のアセットクラスと比較しても引き続き長期投資のコアとしての優位性はあると考えられます。2024年はAIブーム、FRB利下げ、米国景気後退懸念、大統領選、日銀利上げと大きなイベントが続き、相場が急変動しやすい環境が続いています。新NISAで投資を始めた方で日々不安に感じている方も多いと思うので、本記事では改めて米国株投資の強みとリスクについて解説していきたいと思います。米国株投資の強みまず、米国株投資を魅力的にさせている、米国経済のファンダメンタルな(本質的な)強みを解説します。要約すると、①イノベーションの中心地として米国の代替先がないこと、②株主還元の徹底した経済構造、③内需と利下げ余地に支えられたマクロ経済の頑健性が強みと考えています。イノベーションの中心地として米国の代替先がない皆さんの日々の生活を支えている半導体・OS・クラウドインフラ・SNS・検索サービスなど、情報社会のインフラは、Alphabet, Amazon, Microsoft, Apple, Meta, NVIDIAといった米国のテクノロジー企業に独占されています。さらに次の技術革新と言われるAIや自動運転の研究開発も米国がリードしており、この領域でも米国企業が付加価値の大部分を取っていきそうな情勢です。生成AIではChatGPTのOpenAIやClaudeのAnthropicは米国企業ですし、自動運転の最先端はTeslaとAlphabetの子会社Waymoが走っています。こうしたイノベーションが生まれる土台になっているのは、世界から人材を集める米国の教育・雇用システムと、シリコンバレーを中心としたITスタートアップのエコシステムです。米国のトップ大学は世界から優秀な人材を集めつつ、移民社会がチャレンジする活力を生んでいます。私のスタンフォードMBA時代の同級生も、移民の両親が機械工をしながら教育に力を入れた結果、スタンフォード大学→CIA→業界トップのVC(かつスタンフォードMBAを働きながら取得)という成功したキャリアを移民2世として築いていました。ITスタートアップのエコシステムはここで語り尽くせないですが、上場株にも関係する話としては、スタートアップのM&Aが活発なところが大きな特徴です。Cisco, Salesforce, Adobeといった企業は老舗ですが、新興テック企業を買収することで持続的な成長に成功しています。こうした資金循環がスタートアップのチャレンジを加速しつつ、上場企業の技術進歩にも貢献していると言えます。少し前までは中国のテック企業の成長が凄まじく、世界を中国企業が席巻するのではないかと言われましたが、その後グローバルに広がる様子は見えず、イノベーションの世界は米国の一極構造が続いています。イノベーションの中心地として米国を代替できる存在が見えてこない中では、世界全体での技術進歩の果実を米国が最も大きく享受する構造が続き、米国企業の成長率への追い風は変わらないと言えます。株主還元の徹底した経済構造米国の資本市場(=機関投資家・ファンド)は企業に株主還元を強く求めるため、上場企業で非効率な経営は放置されず、経営陣の交代も頻繁に起きます。こうした経営の効率化に加え、成長投資のない内部留保や余剰アセットの保有を企業に許さないプレッシャーがかかり、利益の株主への配当還元も優先されます。成熟した米国よりも経済成長率が高い国もありますが、新興国では経済成長の果実を投資家が得る前に、政府が取っていったり(国有企業などがある場合)、消費者に配分されるケース(価格統制など行われた場合)も見られます。例えば、中国経済は過去5年間で年間平均5%弱で成長していますが、中国の代表的な株式指数の1つである上海総合指数は過去5年間で9%も下落しています。投資先企業に対する影響力が皆無の個人投資家にとって、激しい競争の中で全ての株主に対して全力で還元してくれる米国企業は、お得な投資先と言えるでしょう。内需と利下げ余地に支えられたマクロ経済の頑健性グローバルで稼げるテクノロジー企業の成長を背景に、米国の内需も活発です。こうした内需が非テクノロジー企業の業績向上にも貢献し、経済全体が強い状態が続いています。経済が強すぎるが故に、米国は高いインフレを引き起こし、2022年頃から大規模な金融引き締めが進んで現在に至ります。足下では金融引き締めが効果を出して、インフレ鎮静化傾向が見えてきたのですが、同時に製造業中心に企業業績にも翳りが見えています。これが景気後退懸念として、2024年の米国株式市場を不安定化させている大きな要因です。しかし、現状FRBはまだまだ金利引き下げの余地を残しており、経済を刺激できる状態です。インフレ鎮静化と景気拡大の継続を両立する「ソフトランディング」を実現することをFRBとして目指していますが、仮に一時的な景気後退に入ったとしても、利下げで景気回復を進められる見通しは高いと言えます。こうしたマクロ経済の頑健性が、金融危機やコロナショックのタイミングと異なり「出口の見えない不透明性」を排除しているのも強みです。米国株投資のリスク為替変動の影響は一旦考慮せず(直近では日本株相場も円高の時に下がる傾向にあり、米国株投資だけの話でもないため)、米国株相場の観点から米国株に投資することのリスクを解説します。短期的なリスク:高まりすぎた期待値との調整短期的な市場変動は、企業業績や米国経済全体の成長といったファンダメンタルズ(本質)では決まらず、株式市場の需給で決まります。これを大きく左右するのが、アクティブに運用している機関投資家やヘッジファンドです。米国株式市場の短期的な変動は大手投資家のセンチメント(今後の市場動向に対する見立て・温度感)が大きな要因となり、その方向性次第で短期的な株価下落のリスクがあります。2023年後半からの米国株市場は、Magnificent7と言われる大型テクノロジー企業7社に資金を入れておけば上がっていく相場環境で、短期的・裁量的な売買を繰り返すヘッジファンドも「Magnificent7のロング(長期保有)」戦略を取っていました。こうした資金集中が2024年の大型テクノロジー株の上昇を支えていた面もあるので、この高まりすぎた期待値が修正され、ヘッジファンドの資金が離れると短期的には株価が下落するリスクがあると言えます。しかし、こうした株価下落は短期動向なので、企業業績が健全に伸びていれば一定の株価上昇は見込めるものとして、心配しすぎることはないと言えます。中期的なリスク:米国経済の景気後退局面中期的なリスクとしては、米国経済が金融引き締め後のソフトランディングに失敗し、景気後退局面入りすることです。以前に記事でもまとめていますが、景気後退入りした場合、平均10ヶ月間程度は株価の上がりにくい状態が継続することになります。FRBが利下げをするのは確定路線なので、焦点となるのはFRBの利下げスピードです。インフレを沈静化しつつも、縮小しつつある米国景気の底上げに間に合うかどうかが今後の大きなポイントになります。利下げは2025年にかけて行われると予想されるので、市場予測ベースでは2025年中までに45%程度の確率で景気後退入りするリスクがあると見積もれば良いでしょう。長期的なリスク:テクノロジーでの敗北長期投資目線で最も注目すべきなのは、米国株投資の強みの源泉であるイノベーションの中心地としての地位が今後も安泰かという点です。今後、他の国や地域が世界の技術進歩をリードするようなトレンドが生まれれば、その地域により重点的に資産を配分した方が有利となります。長期的なリスクなので、はっきりと顕在化したタイミングを言えるわけではありませんが、以下のようなポイントに注目しておくと良いでしょう。まず、日常生活の前提となっているテクノロジーやサービスに占める米国企業の割合が減っていかないかという点です。例えば、クラウドサービスやモバイルOSに米国企業以外の大手テクノロジー企業が占める割合が増えてきたら、それは危険な兆候といえます。次に、大きな技術革新のタイミングで米国以外のテクノロジー企業が台頭してこないかという点です。過去の米国経済の急成長は、GAFAをはじめとした現在の大型テクノロジー企業の台頭で説明されるため、次世代のこうした企業が米国から出続けなければ、長期的な成長に翳りが出ると考えられます。運用先として他のオプションはあるのか株式指数の間での比較過去10年、過去5年での各国指数の推移を下記で計算しました。過去10年では、NASDAQ>S&P500・ブラジル株式・インド株式>日経平均>ヨーロッパ株式>中国株式過去5年では、インド株式>NASDAQ>S&P500>日経平均>ヨーロッパ株式>ブラジル株式>中国株式という結果になりました。株式で見ると米国株・インド株への投資リターンが最も高かったことになります。IXIC:NASDAQ、SPX:S&P500、NIKKEI:日経225、SX5E:ユーロ株式指数、DAX:ドイツ株式指数、HSI:香港ハンセン指数、NIFTY:インド株式指数、IBOV:ブラジル株式指数10年推移(2015/3/10-2024/9/9)5年推移(2019/12/31-2024/9/9)アセットクラス横断の比較また、他のアセットクラスとして、債券や不動産のような商品で固定利回りを得ると考え、安定利回りとして年率+3%くらいをベースレートとしておくと、5年間で+16%、10年間で+34%くらいの成長率になります。S&P500の成長率は過去5年で+69%、過去10年で+167%なので、株式は価格変動があり短期ではロスが出ることもありつつ、長期の運用では固定利回り商品に比べて大きな差がつくことになります。全く違う観点で金に投資すると考えてゴールドETFの値動きを見ると(計測期間は先ほどの株式指数比較と同じ)、過去5年間で+62%、過去10年間で+107%と、この期間でのリターンはS&P500には及ばないものの、実はかなり良かったことになります。結論:長期投資のコアは米国株優位で揺るがず過去リターンの結果からは、一部の新興国や金は有力なオプションにもなりつつ、米国株のリターンの高さが際立っていました。このことから、短期的な安定性を求める(=近いタイミングでの取り崩し・出金を考えている)場合以外は、米国株がリターンの観点からは有利だったと言えます。今後の見通しについては、長期的な成長性や経済構造は強いので、それが崩れるかどうかだけを見ておけば(特にイノベーションの中心地としてのポジション)、米国株を長期投資のコアとして据えることに、十分な優位性があると考えられます。
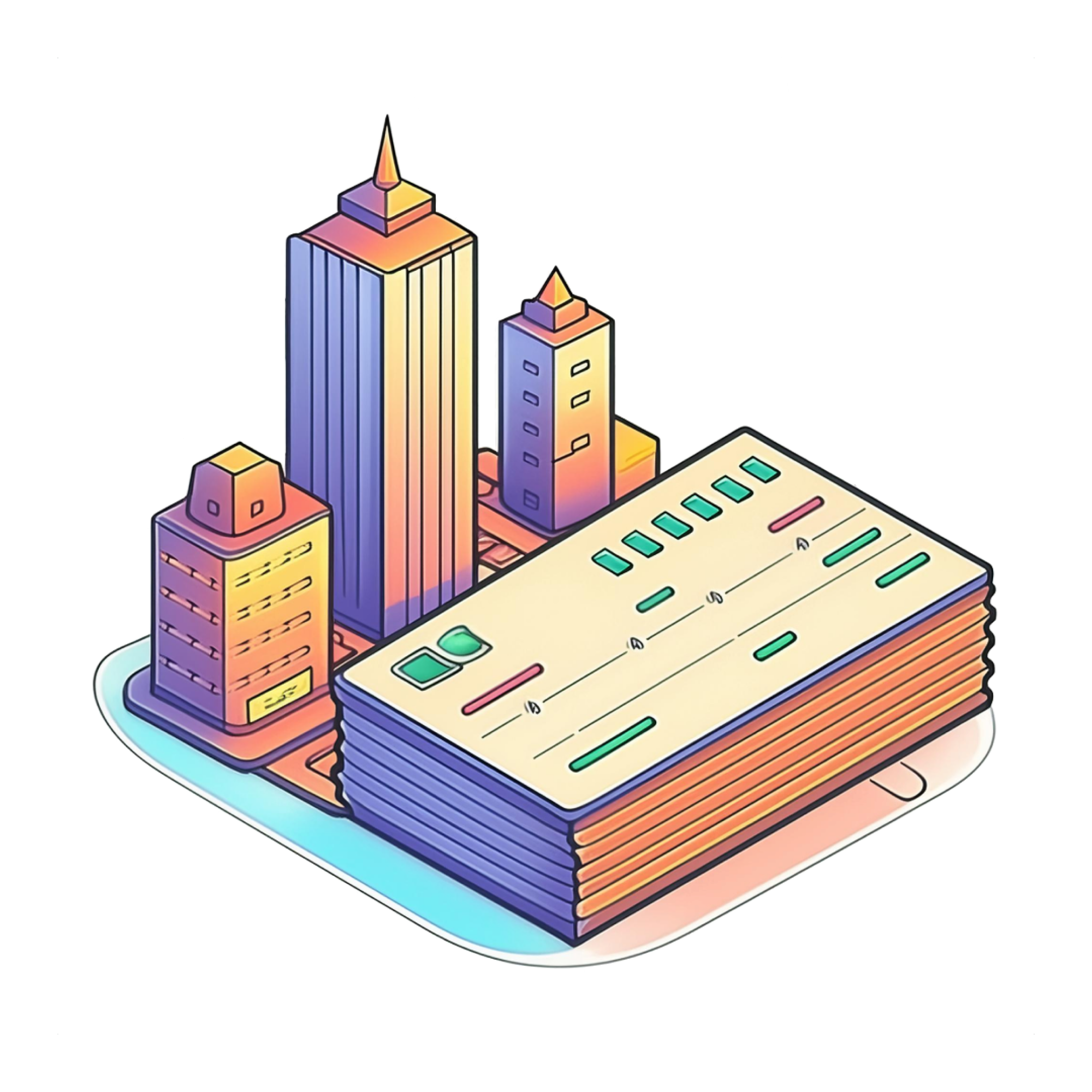
債券の黄金時代?債券ETFへ注目が集まる理由
2024年、米国の債券ETF(上場投資信託)には年初から7月下旬までに約1500億ドル(約23兆円)が流入し、過去最高を記録しました。2年間の純流出から一転、高利回りと利下げ見込みが投資家に好機をもたらしています。本記事では「債券投資に注目が集まる理由」を解説します。利下げ見込みで債券ETFに資金流入足元では利下げに伴う債券価格の上昇を見込んで、債券ETFが人気化しています。債券価格の変動要因として、短期金利に対する投資家の見通しが大きな役割を果たします。連邦準備理事会(FRB)が9月に利下げに踏み切ることはほぼ確実との見方が市場で広がる中、投資家は利回りが高水準のうちに債券を確保しようとしています。現在、債券の利回りとパフォーマンスは約20年ぶりの高水準にあります。8月23日時点のS&P 米国債 7-10年指数で測定される米国債(満期が7年以上、10年未満)の1年リターンは約8.7%、S&P グローバル先進国社債指数で測定される投資適格社債の1年リターンが約10.8%と、どちらも全世界株式(オール・カントリー)の米ドルベースでの10年平均利回り9%と同等の水準にあります。 安全性の高い金融商品でも十分なリターンを狙えることが示されていることから、格付け最高位の債券から得られるトータルリターンに焦点を当てた金融商品を購入する投資家も多くなっています。米資産運用大手ブラックロックの債券部門最高投資責任者(CIO)であるリック・リーダー氏は「現在、債券で得られる利回りと収益率は非常に魅力的であり、債券にもっと資金が流入すると予想する」と語ります。景気後退リスクをヘッジする手段にもまた、米国市場の懸念がインフレから景気後退に変わったため、債券は株式市場の混乱に対するヘッジとしての価値を増しています。8月初旬には景気後退懸念を受け、2023年3月に銀行危機への不安が台頭して以来の債券相場上昇となりました。ただし、8月2日以降に発表された米指標では、リセッション(景気後退)の兆候は示されず、ゴールドマン・サックスは今後1年以内に米国が景気後退に陥る確率を20%に引き下げています。債券投資大手ピムコは「株式のバリュエーションに無理が生じている可能性があることは、債券にとって好都合」であり、「長期的に見渡せる範囲でリセッションがなければ、アクティブ債券投資は良好な成績を残せるだろう。リセッションがあれば、さらに成績は良くなる」と説明しています。債券ETFであれば、債券投資が簡単に債券ETFはすでに複数の商品が含まれているため、1回の取引で分散効果が得られ、また最低投資額が1万円代と小口のものが多くなっています。一方で、直接投資の場合は債券の取引単位は大きく、個人では取引できる銘柄が限られます。さらに、ETFは「Exchange-Traded Fund(上場投資信託)」の名前にもある通り上場しているため、取引所が空いている間リアルタイムで取引を行うことができ、債券に直接投資するときには得られない流動性も提供します。運用管理においても、債券ETFであれば株式と一体に証券口座内で管理できるため、損益状況やポートフォリオが把握がしやすいというメリットが挙げられます。

【バフェットのポートフォリオ解説】アップル株なぜ半減?2銘柄への新規投資も明らかに
ウォーレン・バフェット率いるバークシャー・ハサウェイ(BRK.B)の2024年6月末時点でのポートフォリオが、8月14日に米証券取引委員会(SEC)に提出された報告書「フォーム13F」にて明らかになりました。本記事では、バフェット氏のポートフォリオを紹介の上、今回新たに投資が明らかになったアルタ・ビューティーとハイコについて解説します。2024年9月末時点でのポートフォリオについては、以下の記事をご覧ください。バフェットポートフォリオの中身上位10銘柄で90%以上、アップル株は半減も引き続き1位バフェット氏は集中度の高いポートフォリオを運用していることで知られ、上場ポートフォリオは41社で構成されているにもかかわらず、上位5銘柄で70%以上、上位10銘柄は90%以上占めています。上位保有銘柄アップル(AAPL) : 30.1%バンク・オブ・アメリカ(BAC) : 14.7%アメリカン・エキスプレス(AXP) : 12.5%コカコーラ(KO): 9.1%シェブロン(CVX): 6.6%オキシデンタル・ペトロリアム (OXY): 5.8%クラフト・ハインツ(KHC): 3.8%ムーディーズ(MCO): 3.7%チャブ(CB): 2.5%ダビータ(DVA): 1.8%特筆すべきは、4-6月にアップル株の保有を50%近く削減したことでしょう。一部のアナリストは、アップルの長期的な成長能力に少しでも懸念があれば、バフェット氏は全ポジションを手じまいしていた可能性が高いとし、アップル株の保有削減は「単なるリスク管理」または「経済情勢の悪化への備え」であるとの考えを示しています。5月15日に開示された、バークシャーの2024年3月末時点のポートフォリオでは、アップル株は4割近くを占めていましたが、今回の株式売却により保有比率は3割へ低下しました。バフェット氏は、7月以降にアップル株をさらに売却したかどうかを明らかにしていませんが、5月時点では「アップルが年末までバークシャーにとって最大の保有株であり続けると予想している」と述べています。また、ポートフォリオの中で2番目に大きなポジションを占める、バンク・オブ・アメリカ株も7月中旬以降にポジションを8.8%削減していますが、開示されているのは6月末時点でのポートフォリオのため、古い保有状況が示されています。投資縮小の理由や意図について、バフェット氏はこれまでのところ明らかにしていません。化粧品小売と航空機器部品メーカーへのへの新規投資が明らかにそのほか、注目を集めたのはアルタ・ビューティー(ULTA)とハイコ(HEI.A)への新規投資です。アルタ・ビューティーは年商が1兆円を超える米国最大の美容小売チェーンで、米国全50州に約1,395店舗を展開しています。百貨店コスメを自宅近くで試せるのが魅力であり、ポイント獲得プログラムには4,300 万人以上の会員がいます。アルタの株価は、同社が成長鈍化の可能性を警告したことから低迷しており、予想株価収益率 (PER)は12.8倍と非常に割安で取引されていました。アルタのポジションは約2億6000万ドルに相当し、バークシャーにとっては少額の保有となります。ハイコは、民間航空機の交換部品や防衛製品の部品製造するほか、世界の主要航空会社を顧客とする保守サービスを提供しています。航空機部品の製造は当局の認証が必要なため参入障壁が高く、製造業に珍しく営業利益率が20%を超えています。ハイコの株価は、同社製品に対する高い需要と市場でのプレゼンス拡大から年初来約35%上昇しています。バークシャーは、2016年に航空機部品メーカーのプレシジョン・キャストパーツを321億ドルで買収しており、航空宇宙分野にも精通しています。手元資金は2005年6月以来の最大にバークシャーは2024年4-6月期に755億ドル相当の株式を売り越したため、現金と米短期債保有額を合計した広義の手元資金は6月末時点で2769億ドル(約40兆5700億円)に達し、過去最高値を更新しました。バークシャーは最低300億ドルの現金を保有することを約束していますが、適正価格で購入できる企業全体や個別株が見つからない場合には、現金を蓄積させることが多くなっています。バフェットポートフォリオを簡単コピー?ブルーモ証券では、2024年6月末時点でのバークシャーのポートフォリオをワンタップでコピーし、投資を始めることができます。株式のみで構成されるポートフォリオのほか、米短期債を含む手元資金を反映したポートフォリオのコピーもできますし、そこから変更を加えてオリジナルのポートフォリオの作成も可能です。

5年に1度の相場下落?個人投資家にとってピンチかチャンスか
過去1ヶ月間を振り返ると、7月上旬の最高値から相場は大きく下落し、個人投資家の資産も大きく目減りしていますが、実は日本の個人投資家にとって今回は5年に1度くらいの大きさのインパクトでした。本記事では、過去の相場動向・景気循環の歴史・資産別での変動を分析することで、①今回は日本の個人投資家には5年に1度のイレギュラーだった、②下落のダメージは分散していた投資家ほど小さかった、③5年に1度の相場下落でも慌てず「長期・積立・分散」を継続すべき、点を解説していきたいと思います。日本の個人投資家には5年に1度のイレギュラーだった株安・円高が重なり、日本人にとってコロナショック以来の相場下落2024年7月から1ヶ月間の相場下落は、過去10年の円建てS&P500の推移で見ると、2020年のコロナショック以来の下落幅だったことが分かります。下落率で比較をするとコロナショック当時(2020/2/20-2020/3/23)の下落率は-34%、今回下落(2024/7/10-2024/8/5)の下落率は-18%と、それでもコロナショックの時の方がインパクトは大きかったです。一方、ドル建てS&P500はここまでの下落になっていないので、今回下落は「株安」と「円高」が重なったことによるダブルパンチが問題の本質でした。円建てS&P500のチャートドル建てS&P500のチャート出所:S&P Globalまた、米国市場としてはコロナショックと現在までの間に「FRB利上げ」によって株価が低迷した時期があった(2022年)のですが、その時期はちょうど円安が進行していたため、日本の個人投資家は円建てで資産を見た時に大きなロスは出ませんでした。ドル円と米国株式の変動方向が揃ったことが、今回下落が日本人にとって「コロナショック以来」の出来事になった背景にあります。過去10年で見ると「コロナショック」「今回の円高・株安ショック」が2つの大きな暴落で、さらにその前10年間を振り返ると「ドットコムバブル崩壊」「リーマンショック」があるので、今回下落は「5年に1度」と呼んで良い相場変動だと言えます。今回の相場下落が続くかは米国経済のソフトランディング次第景気には拡大期と後退期が存在し、現在は2020年4月以降の景気拡大期と捉えられています。FRBの利上げによるインフレ抑制が、この景気拡大期を終わらせて米国経済が景気後退に入るかが、相場の低迷が続くか上昇に戻るかの大きな岐路になります。「ハードランディング」シナリオは、FRBの高金利政策継続の影響で米国経済が景気後退に入るパターンです。この場合は平均10ヶ月間ほど経済活動が停滞し、株価の上がりにくい状態が続くことになります。このシナリオに対する懸念から、直近の株式市場は乱高下していました。「ソフトランディング」シナリオは、景気後退を経ずにインフレ率が下がり、米国金利が低下して景気拡大が続くパターンです。過去最長では10年間も景気拡大が続いたことがあるので、長い場合だと2030年まで景気拡大となることもあり得ます。過去には、1991−2001年の景気拡大期は、途中でFRBが利上げをしても景気後退を起こさなかった「ソフトランディング」が成功した事例として有名です。8月12日現在の最新見通しでは、JP Morganが年内の景気後退入りの確率を35%、2025年下半期までの景気後退入りの確率を45%と見込んでいます。出所:JETRO(日本貿易振興機構)今回下落のダメージは分散していた投資家ほど小さかった債券や金を組み込んだポートフォリオのダメージが比較的小さかった2024年7月10日を相場の頂点として、2024/7/10-2024/8/9の1ヶ月間の資産別の株価変動を比較したのが以下のグラフです結果はダメージの小さい方から、金(GLD)が+2.37%、米国短期国債(SHV)が+0.06%、世界株式・オルカン(VT)が-4.19%、S&P500(VOO)が-5.04%、FANG+(NYFANG)が-13.47%、日経平均(NIKKEI)が-16.96%、NVIDIA(NVDA)が-22.36%で、この期間のドル円は-9.31%でした円高を避けて日本株式に投資していたら良かったかというとそうでもなく、日本株は過去1ヶ月の間に-16%も下落しており、米国株式や世界株式と比較しても大きなマイナスとなっています。円高効果と合わせてS&P500に投資しているのとマイナスは大きく変わりませんでした。S&P500かオルカンかも大きな論点ではなく、オルカンの構成要素で米国株式が6割で、米国市場が落ちる時は世界的にも株価が落ちるため、誤差程度の差分しか出ていません。株式の集中という意味では、NVIDIA単体に投資していた場合はドル建てで-20%(円建てではおよそ-30%)と、かなり大きなマイナスになりました。一方、テクノロジーセクターに集中したFANG+インデックスは-13%、S&P500指数では-4%と、分散するほどにマイナスが小さかったことが分かります。さらに異なるアセットクラスで見ると、債券はほぼ変動せず、ゴールドはむしろやや上昇と、下落局面において全く異なる動きを見せています。債券や金をポートフォリオに入れてリスクヘッジしていた場合、ダメージを緩和できていた可能性が高いです。まとめると、今回のような下落局面では当たり前ですがリスクの高いポートフォリオほどマイナスが大きく、ダメージの大きさとしては「テック株集中」>「株式分散」>「バランス型(債券・金など組み合わせ)」という順番になりました。相場下落時にダメージを抑える効果のある資産については以下記事も参考にしてみてください。時間分散できていた投資家はインパクトが小さい保有資産の分散度合いでインパクトを分析しましたが、加えて投資タイミングの時間分散についても考えます。ポートフォリオの中身以外の観点から、今回の相場下落で「勝ち組」だった投資家を分類すると、以下のように整理できます。①大幅下落時に資金投入できた人:日経平均が歴代1位の下落幅だった8月5日など、大きく相場が落ちたタイミング(その後反発上昇するタイミング)で資金投入できた投資家は、全体がマイナスの期間でもプラスのリターンだった可能性があります。実際に8月5日の開場時に投資した場合、S&P500は1週間で4%も上昇しています。②投資余力をまだ残している人:まだ相場が底をついているか不透明なこともあり、今後追加で資金投入する余力を残している投資家は、下落からの回復局面でリターンを得られる可能性があるので、資金投入の時期次第ではリターンを向上させられます。③積立投資をしている人:そもそも積立で定期的に投資しているタイプの人で、いつ市場が底を打っても特定の一時点で集中投資する場合に比べてリターンが平準化されます。今回のような下落局面においても買いを継続的に入れているため、リターンにプラスの影響があったはずです。また、これまで投資してきた人は今回ショックで大きくダメージを受けていますが、最近投資を始めた人(まだ資金をそこまで投資に回していない人)は傷が浅いので、実は最近投資を始めた(これから始める)人にとっては有利な環境でもあります。5年に1度の相場下落でも慌てず「長期・積立・分散」を継続投資をやめたり、リスクの高い取引に走らないこと今回のような大幅下落に直面して、個人投資家として「やるべきではないこと」は以下のような行動になります。①投資をやめてしまうこと:今回の下落を受けた損切りで投資をやめてしまうことです。資産運用は下落時も上昇時も保有し続け、長期で負けないことが大事なので、下落局面でも歴史から長期の上昇を信じて投資し続けましょう。また、一度投資から資金を引くと、日々忙しい中で市場をチェックして再び戻ってくることは難しいです。②短期逆転トレードを狙うこと:一時的な損失を取り返すため、ハイリスク・ハイリターンな取引に手を出すこともお勧めできません。具体的にはレバレッジ型の取引や上下の激しい小型株への集中投資が挙げられます。今回の相場下落は、分散していれば-20%くらいの減少でしたが、さらにレバレッジがかかっていると-60% 超の下落となり、そこから巻き返すのにはかなり時間がかかってしまいます。※ 参考:24/7/10-24/8/9でSOXL(半導体セクターの3倍レバレッジETF)に投資した場合、ドル建てでも-54%の下落となります(円建てでは-60%以上)③上昇した銘柄を後追いすること:市場全体が下落する中でも、決算結果が良好だった銘柄などは上昇することがあります。こうした銘柄はいつも以上に目立ちますが、後追いで投資してもそこから短期での株価上昇は難しいケースもあります。「この企業は長期的になくならそうだから」でも「ブランドが好きだから」でも良いので、足下の株価上昇以外で自分が納得できる理由がある場合に投資すると良いでしょう。相場を気にしすぎず、積立投資でどっしり構えるくらいが良い最後に、今回の下落相場と足下で不安定な市場動向を受け、個人投資家の資産運用としてのアドバイスを3つご紹介します。①短期の変動を気にしすぎない:自分の資産変動はどうしても気になりますが、長期目線の投資であれば短期変動は気にし過ぎないことも大事です。本記事のようなコンテンツも気になる方のために書いていますが、資産運用の方針がクリアならそこまで日々のニュースを追わなくても良いです。②積立投資で下落相場の果実を得る:今後の相場がどちらに転んでも勝てるように、積立投資で定期的に資金投入するとリターンが安定するのでお勧めです。株安・円高のニュースが入った場合でも、「定期的に投資するタイミングで安く買えて良いか」とも思えるので、精神衛生上もプラスです。③投資余力あれば下落時に追加投資:まだ投資余力のあって相場動向も追いたい方は、さらなる下落があったタイミングで追加的に資金投入して、銘柄の平均取得単価を下げることも効果的です。ただ、相場の底を見極めて投資実行するのはかなり難しいので、ある程度下落した時に入れられていたらプラスくらいに捉えると良いでしょう。ブルーモで資産運用されているユーザーも長期目線の方が多いので、相場下落時もむしろ追加投資する方がいたり、最近リリースされたリバランス付き自動つみたて投資機能を活用される方が多いのが特徴的でした。資産運用の原則である「長期・積立・分散」については、以下記事もご覧ください。

ソフトランディングとは?米景気と株価は今後どうなるか
本記事では、「ソフトランディング」について解説のうえ、米景気と株価の今後の見通しについて市場関係者の見方を紹介いたします。ソフトランディングとはソフトランディングとは、急激な景気の悪化を引き起こすことなく、インフレを抑制し、適度な景気減速を実現することをいいます。本来は、ロケットや飛行機が緩やかに着陸する様子を意味する言葉ですが、経済用語として広く使われるようになりました。反対に、経済政策の結果、急激な景気後退に陥ることを「ハードランディング」といい、ソフトランディングの対義語として使われます。景気後退懸念から米国株式市場は大幅下落米株式市場は、連邦準備理事会(FRB)によるソフトランディングの実現への期待が株価の追い風となっていたところ、7月の雇用統計などの経済指標が予想外に軟調となり、米景気のハードランディングが懸念され、市場心理は一気にリスク回避に傾きました。しかし、低調な雇用統計の背景としてハリケーンの影響があったとの疑いが根強く、その後に7月のISM非製造業景気指数が51.4を記録したこと等から、景気後退懸念は行き過ぎとの見方が広がりました。また8月7日には、JPモルガンの最高経営責任者(CEO)ジェイミー・ダイモン氏が「米経済がソフトランディングする確率は35~40%程度」、「クレジットカードの借り手の債務不履行は増加しているものの、米国は現在景気後退には陥っていない」との見立てをCNBCのインタビューで明らかにしています。JPモルガン・チェースのトレーディングデスクは、米国株式市場の下落について、押し目買いのチャンスに近づいているとの見解を示しており、株価が強く反発するかどうかは消費者物価指数(CPI)、小売売上高といった今後の経済指標次第と述べています。市場は大幅利下げによる景気テコ入れに期待7月30-31日に開催された米連邦公開市場委員会(FOMC)の定例会合の会見では、パウエル議長から9月にも利下げに動く可能性があるとの見解が示されました。エコノミストの多くは、景気の下支えに向けてFRBが今年の残りの3会合で0.25ポイントずつの利下げを行うと予想していますが、直近のFedWatchでは9月会合で0.5ポイントの利下げを織り込んでいるほか、9月と11月会合の両方で0.5ポイントの利下げが行われると予想する大手銀行もあります。また、今月の22〜24日には、経済シンポジウム「ジャクソンホール会議」が開催され、市場ではパウエル議長が利下げの時期や想定する利下げ幅について言及する可能性があると例年以上に注目が集まっています。パウエル議長は、ジャクソンホール会議の冒頭演説をFRBの見通しを方向づける場として利用することが多くありました。今後の注目のイベント8月14日 消費者物価指数(CPI)8月15日 小売売上高8月22〜24日 ジャクソンホール会議8月28日 エヌビディア(NVDA)決算8月31日 個人消費支出(PCEデフレータ)

利下げ・大統領選で恩恵を受ける?バフェットポートフォリオに注目すべき理由
本記事では、ウォーレン・バフェットの2024年4-6月に行われた最新の売却動向を解説しつつ、バフェット氏のポートフォリオと金利・大統領選動向の関係について考察をします。バフェット氏の過去のポートフォリオや資産運用手法については過去の記事で解説していますので、関心のある方はあわせてご覧ください。バフェットポートフォリオに大きな変化アップル株の保有が半減8月3日、バフェット氏率いるバークシャー・ハサウェイは、4-6月にアップル株の保有を50%近く削減したことが明らかになりました。バークシャーは1-3月にもアップルの保有を10%以上減らしており、その際は投資家に対し、売却益にかかる税率が背景にあると説明していました。一部のアナリストは、アップルの長期的な成長能力に少しでも懸念があれば、バフェット氏は全ポジションを手じまいしていた可能性が高いとし、アップル株の保有削減は「単なるリスク管理」または「経済情勢の悪化への備え」であるとの考えを示しています。5月15日に開示された、バークシャーの2024年3月末時点のポートフォリオでは、アップル株は4割近くを占めていましたが、今回の株式売却により保有比率は3割へ低下しました。2024年3月末時点での上位保有銘柄アップル(AAPL) : 40.8%バンク・オブ・アメリカ(BAC) : 11.8%アメリカン・エキスプレス(AXP) : 10.4%コカコーラ(KO): 7.4%シェブロン(CVX): 5.8%オキシデンタル・ペトロリアム (OXY): 4.9%クラフト・ハインツ(KHC): 3.6%ムーディーズ(MCO): 2.9%チャブ(CB): 2.0%ダビータ(DVA): 1.1%バンカメ株も投資縮小また、バークシャーは、ポートフォリオの中で2番目に大きなポジションを占める、バンク・オブ・アメリカ株も7月中旬以降にポジションを8.8%削減していることが報道されています。投資縮小の理由や意図について、バフェット氏はこれまでのところ明らかにしていません。バフェットポートフォリオは4セクターに集中バークシャーのポートフォリオは、テクノロジー、金融、エネルギー、生活必需品セクターの4セクターに集中しており、直近の売却状況を鑑みると、 S&P500と比較して金融、エネルギー、生活必需品セクターの比率が高くなっています。利下げ・トランプトレード注目の「金融」、「エネルギー」セクターバフェット氏は、長らく金融株を多く保有していることで知られていますが、近年はエネルギーセクターへの投資も増やしており、シェブロンとオキシデンタルの2社でポートフォリオの1割程度を占めています。直近の米国株式市場では、米連邦準備制度理事会(FRB)による利下げ観測の高まりを機に、割高感のある大型グロース株から割安感のあるバリュー株や中小株に投資資金がシフトする動きが見られ、公益・金融株等が買われました。また、金利の引き下げがドル安につながり、他の通貨を使用する国際バイヤーによるドル建て石油の需要が高まる可能性も指摘されています。一方、金融・エネルギー関連の銘柄は、ドナルド・トランプ氏が、金融規制の緩和や石油・天然ガス投資や掘削活動の拡大方針を表明しているため、2024年大統領選でトランプ氏が再選した場合に恩恵を受けると期待されています。ただし、トランプ氏は石油・ガス業界に対して友好的であるものの、原油価格にとってはリスクが高いことに注意が必要です。ハリス政権が誕生した場合も、原油価格には好材料となり、エネルギーセクターは恩恵を受ける可能性があると考察されています。ハリス氏は以前、石油開発等に用いられる「フラッキング(水圧破砕法)」へ反対の姿勢を示していましたが、直近ではフラッキングを禁止することはないと主張を覆しています。不人気な「生活必需品」セクターで好調なコカ・コーラゴールドマン・サックスの顧客向けレポートによると、過去8回の連邦準備理事会の利上げサイクルにおいて、利下げ開始時点でパフォーマンスの良かったセクターは、1番目が「ヘルスケア」セクター、次いで2番目が「生活必需品」セクターでした。しかし、今のところ生活必需品セクターはセクターローテーションで大きな恩恵を受けていません。ウォール・ストリート・ジャーナルによると、同セクターは世界的に販売量を伸ばしているものの、特に米国の低所得消費者の間で価格決定力が不安定であることが背景にあるといいます。ただし、バフェット氏が長年絶賛するコカ・コーラは生活必需品セクターのなかで最も好調で、4-6月期のオーガニックグロースによる売上成長率は15%を記録したと報告しています。これは、消費不振の時期においても、同業他社よりも値上げを実施できる企業であり、ブランドの強さを物語っている可能性があります。不透明な投資環境で好まれる高配当株米国株式市場は、景気動向・FRB(米連邦準備理事会)の政策動向・地政学的な懸念など、当面は先行きの不透明感が払しょくされない状況が続くことが想定されます。このような環境下においては、安定したインカムゲインを得られる高配当株式への投資も有効な選択肢の一つとなります。バフェット氏は、2023年2月に公開された「株主への手紙」で、成功の秘訣としてコカコーラを例に挙げ、配当を支払う強固で確立されたビジネスの価値を説明しています。「1994年にコカ・コーラから受け取った現金配当は7500万ドルでした。2022年にはその配当が7億400万ドルに増加しました。成長は毎年、誕生日のように確実に起こりました。チャーリーと私がする必要があったのは、コカ・コーラの四半期ごとの配当金小切手を現金化することだけでした。我々はこれらの小切手が今後も増加する可能性が非常に高いと期待しています。」現在バークシャーのポートフォリオは年間約60億ドルの配当収入を生み出していますが、その7割以上は5社に由来しています。バークシャーの2023年年間配当収入 上位5銘柄バンク・オブ・アメリカ(BAC): 9億9,150万ドルオキシデンタル・ペトロリアム(OXY):8億9,750万ドルアップル(AAPL):8億6,930万ドルシェブロン(CVX):8億2,210万ドルコカコーラ(KO):7億7,600万ドル
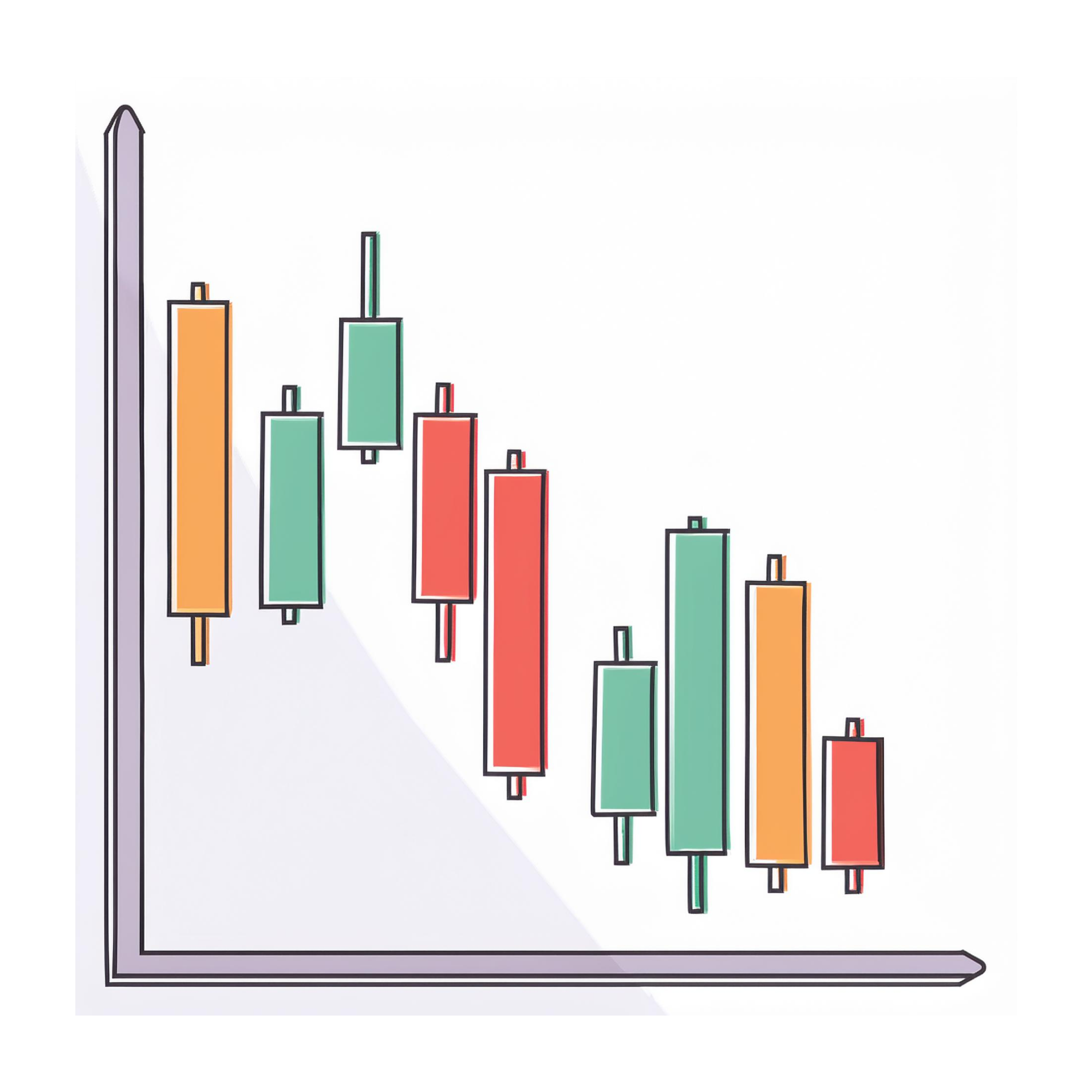
日経平均は歴史的暴落。今後の長期投資で気をつけるべきこと
8月5日の市場で日本株は大きく下げ、日経平均は下落幅-4451円(歴代1位)、下落率-12.4%(歴代2位)と、歴史に残る暴落の日となり、その余波は世界全体に波及していきました。本記事では、①今回の暴落で何が起きたか、②過去の暴落との比較、③今後の長期投資で気をつけるべきこと、を解説していきたいと思います。はじめに:相場下落時も「長期・積立・分散」が大事今回のような大きな暴落があった時でも、目的が資産運用であれば「長期・積立・分散」を守り、相場が下がった時ほどむしろ安く買えるチャンスと捉え、積立投資ならやめないことが重要です。8月5日の日経平均暴落後、鈴木財務大臣の記者会見コメントで以下のように発信しています。「新NISAをきっかけに投資を始めた方々に動揺が生じているという報道を目にしている。新NISAについては、相場の下落等の市場変動が進む中にあっても、長期・積立・分散投資の重要性を考慮して、冷静に判断していただきたい。金融庁としては、長期・積立・分散投資の重要性について広報・周知を行うとともに、国民の皆さんの金融リテラシー向上に向けて、関係方面と連携してさらに取り組んでいきたい」ブルーモでも、「長期・積立・分散」の重要性について解説した記事をリリースしているので、そちらも是非ご覧ください。今回の暴落で何が起きたか8月5日:日経平均の暴落を皮切りに世界全体で株安前週金曜日に公表された米国失業率が予想より悪かったため、米国には景気後退の懸念があり、日本市場も月曜日は下落すると見られていました。しかし、始まってみると日経平均は想定以上の大幅下落となり、早々にTOPIXでサーキットブレーカーが発動され、市場はパニック状態になります。また、米国市場の不安定化が円キャリー取引(金利の低い円を借りて米国で投資すること)のポジション縮小につながり、8月5日は円高もさらに進行して、開場時の145円が一時的に141円台までいきました。円高が進むと企業の業績不安から一層株安圧力となり、結果的に日経平均は-12.4%というブラックマンデー以来の歴史的な暴落で終わります。米国の景気後退不安と、時差から開場の早かった日本市場での歴史的な暴落を受け、アジア・ヨーロッパ市場も全体的に株価が下落します。特に韓国・台湾は8−9%と大きな下落幅でした。米国市場も下落から始まり、ISM非製造業指数の結果が予想を上回ったことでやや持ち直したものの、S&P500は-3%、NASDAQは-3.4%の下落で終えています。レバレッジのかかった市場構造が下落を拡大した今回の暴落は、ファンダメンタルズ(根本的な)要因としては、米国の景気後退懸念と中東情勢の悪化があります。しかし、株価がここまで急落したのには日本市場を取り巻く2つのレバレッジ取引があったと考えられます。それは「ヘッジファンドの円キャリーへのレバレッジ」と「日本の個人投資家の信用買い」です。1つ目は、円キャリー取引を行っていたヘッジファンドは利幅を増やすため、更にレバレッジをかけていました。今回の円高と米国市場不安定化に伴いポジションのリスクが上昇したため、ファンド全体のリスク管理の観点から、彼らは通貨以外の資産でもレバレッジを解消し、様々な株が売却されました。2つ目は、日本の個人投資家が上昇相場の中でレバレッジをかけた取引を続けており、信用取引の買いポジションは18年ぶりの高水準となっていました。8月5日の想定外の相場下落で、このポジションに対して追証(借入を維持するために追加で現金を拠出しないといけなくなること)が発生し、差し入れられないと判断した個人投資家の投げ売りが発生しました。この2つのレバレッジ取引の構造が、日銀の追加利上げと米国市場の不調により崩れ、一気に大きな下落へとつながったと考えられます。過去の暴落との比較過去の日経平均暴落と比較以下が過去の日経平均下落率ランキングです。1位はブラックマンデー(香港市場の下落に端を発したNY市場の大幅下落に引きずられた暴落)、3位はリーマンショック、4位は東日本大震災です。それ以降はやや古いものもありますが、5位はスターリン暴落(スターリンの死後、ソ連の政策転換による軍需減少を想定した暴落)、9位はスイスIOSショック(スイスの投資会社が日本株を売却するという噂を発端とする下落)、10位は英国のEU離脱ショックです。出所:日経平均プロファイルこれらを大きく分類すると、①自然災害・戦争(東日本大震災)、②金融危機(リーマンショック)、③一時的な市場動揺による下落(その他)、となります。今回の暴落は特に災害や金融危機を原因とするものではないので、この勢いで落ち続けたりする(リーマンショックのように)ものではないと考えるのが妥当でしょう。③のパターンで例えばブラックマンデーだと3ヶ月後には暴落前高値を更新して、日本経済はバブル景気に入っていきました。過去の米国株式市場の下落と比較日本の日経平均の暴落は、世界的な危機の発生ではないように見えるので、特に米国株に投資する個人にとって気になるのが、米国市場の停滞はいつまで続くかという点です。今回は特にどこで底をつくか(最大下落幅に達するか)を見ていきます。過去の米国株式市場の大幅下落イベントを以下で比較しています。金融危機と自然災害は動きが異なるので除いて、ドットコムバブル崩壊とFRB利上げショックを詳細に分析します。米国株市場にとってのワーストケースは、今回の相場上昇が「AIバブル」であり、その崩壊とともに2000年のドットコムバブル崩壊と同程度の影響が出る場合です。この点については、市場が最高値だった24年7月時点においても、テック株はドットコムバブルの最高潮と比較すると割安に評価されていたので、現時点では経済全体の停滞につながる可能性は低いと見られています。では、次にFRB利上げショック(FRBの急速な利上げにより、テック株を中心に株価が大幅下落したことを指す)と比較をすると、当時はインフレ率が高く、FRBとして利上げを緩めるオプションはなかったことから、株価の停滞打破は企業業績のみに依存した状態でした。それに比べて、2024年8月5日時点の市場は、FRBが利下げ余地を残しつつ景気は沈静化してきており、この沈静化が景気のハードランディングにならないか懸念されている状態です。よって、FRBにはまだ利下げによって経済を刺激する余地があるため、停滞状態を打破するチャンスは2022年当時より大きいと言えます。今後の長期投資で気をつけるべきこと冒頭でも紹介したように、「長期・積立・分散」の原則を守ることが大事で、その上で注目すべきポイントをいくつか紹介します。まず、相場を読み切るのは不可能な前提で、絶好の買い場となる下落時の投資機会を逃さないため、下落途中でも(むしろ下落途中こそ)積立での投資を継続していくことが重要です。過去の事例をみると、①一時的なショックで数ヶ月で市場は最高値に戻る(ブラックマンデー後の日本市場のケース)、②停滞が継続して年末年始ごろに底値になる(FRB利上げショックのケース)、③経済が長期停滞して2年後に底値になる(ドットコムバブルのケース)、というのが起こり得るオプションです。もし、定期的な積立投資だけでなく、機動的に資金投入する場合、現在のマーケットが①~③のいずれにいるかを判断することが必要です。今後の経済指標、テック企業の決算、FRBの金融政策は、基本的なことですが大きな変数なので、ある程度見ておくと追加での資金投入をする際の参考になると思います。個人投資家の皆さんには、生じている危機の正体と影響範囲を冷静に理解して、合理的な投資行動をとっていただければ幸いです。
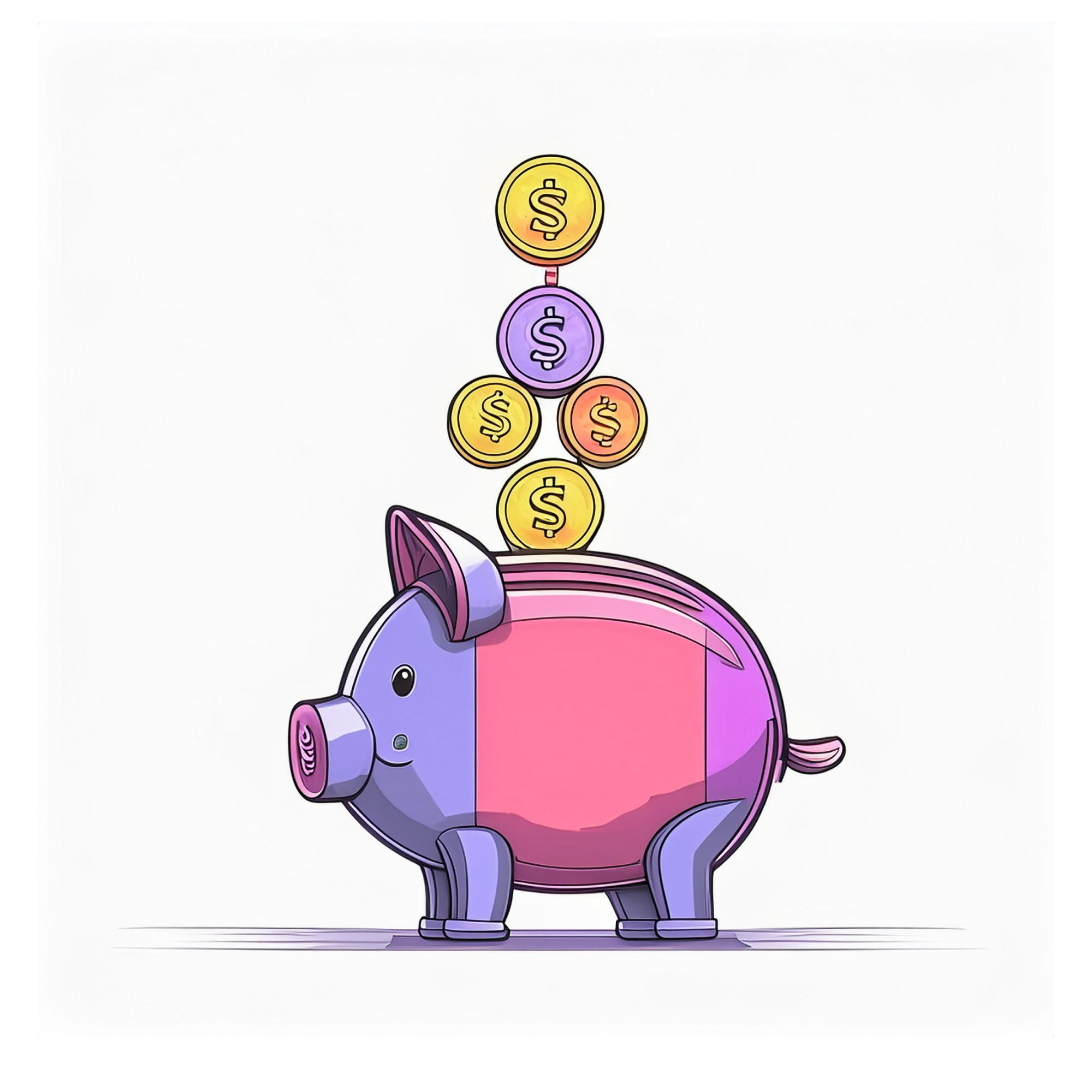
相場下落時に振り返る、資産運用の王道「長期・積立・分散」
本記事では、相場が不安定で心配になる方向けに、資産運用の王道である「長期・積立・分散」の原則を紹介したいと思います。資産運用の王道は「長期・積立・分散」資産運用では「長期・積立・分散」の3つの原則が大事だと言われています。一時的な相場下落の影響は避けられない前提で、それでも資産運用を成功させるためのコツを紹介します。大前提として「ハイリスク・ハイリターンの一発逆転」を狙うのではなく、「負けずに長期的に一定のリターンを出す」ことを目的としています。長期投資であれば負けにくい過去の米国株市場を振り返ると、「15年超の長期で切り取ればどの期間でもプラス」ですが「短期で切り取るとマイナスになる場合もある」ということが分かります。つまり、時間軸が短期であればリターンを出すのは相場次第となり難しいですが、時間軸が長期であればリターンを出せる確率は上がります。実際に、今回の調整局面よりも遥かに世界全体に暗雲が立ち込めていた2007年のリーマンショックの場合、株価の下落幅は50%を超えていますが、それでも6年間で相場は回復しています。つまり、リーマンショック前の最高値で投資をしても、6年待てばリターンはプラスになることが分かります。しかし、これは一時的にマイナスが出ても、長期投資を継続して待つ必要があることを示してもいます。長期投資目線で、一時的な相場下落があっても辞めずに続けられるかどうかが、資産運用のスキルとしては重要です。つみたて投資をすれば相場の影響は受けにくい「安値で買って高値で売る」は理想ですが、相場を読み切って実行するのは限りなく難しいです。資産運用の観点からできるリスク回避策は「高値のタイミングでまとめて投資することを避ける」ことになります。例えば、先ほどのリーマンショックの例だと、ショック直前の高値のタイミングで全額を投資した場合、回復するまでに6年間かかりますが、高値の前後にタイミングを分散して投資することで、資産全体をプラスにするスピードをあげることができます。これは、「一番安い時に全額投資する」という最も大きいリターンを得られる可能性を捨てることで、「一番高い時に全額投資する」という最も大きい損失を出す可能性も排除することを意味します。なので、資産運用では「一気に投資する」ではなく「積立で徐々に投資する」ことが大事であり、その観点からブルーモでも「リバランス付き自動つみたて投資機能」をリリースしています。また、このように定期的に一定額を入金して投資する手法は「ドルコスト平均法」と呼ばれています。相場に関わらず一定額を定期的に入金することで、値下がりした時は多く、値上がりした時は少なく資産を買付け、平均購入単価(投資元本)を抑える効果が期待できます。つみたてすると下落局面でも感情に左右されず買い付けられるので、相場下落時の購入チャンスを逃しにくいというメリットがあります。ポートフォリオを分散することでリスクを下げられる資産運用する上での最後の原則は「ポートフォリオのリスク分散」です。価格変動の大きいテクノロジー企業の株を集中保有するポートフォリオは、当たればリターンは大きいですが、下落局面では大きな損失を出す可能性があります(これが「リスクが高い」という意味になります)。リスクを抑えたポートフォリオを作ることで、相場下落局面でも影響を限定的にすることが可能です。実践的に紐解くと、ポートフォリオのリスク分散をする上で重要なファクターは「銘柄の数」「銘柄の価格変動の大きさ」「銘柄同士の相関」になります。「銘柄の数」を増やすためには、ブルーモであれば個別株でも1%単位から細かく銘柄を組み込むことができますし、より簡単にはETFを組み入れることで投資する銘柄数を簡単に増やすことができます(ETFは数十から数千の銘柄に分散投資しているため)。「銘柄の価格変動の大きさ」を抑えるためには、個別株であればテクノロジー株だけではなく高配当株を組み入れたり、株式だけでなく債券のETFも組み入れることが有効です。「銘柄同士の相関」を抑える(=ある銘柄が下落する時に他の銘柄は上がるようにしてリスクを相殺する)ためには、個別株であれば業種を分散して保有したり(テクノロジー株とエネルギー株など)、米国株と価格の相関の低い資産を組み入れたり(債券・金・グローバル株式など)することが有効です。下落相場は初心者が資産運用を身につけるための試練今回のような相場下落は必ず定期的に発生します。直近では、コロナショックや2022年の米国利上げのショックで市場は大きく落ち込みました。短期的に資産が目減りすると損失に怖くなり、資産運用を中断するパターンもありますが、一度資金を引き上げると戻ってくるハードルも高いです。「もっと下がるかも」と待っている間に株価が上がって資金を入れにくくなり、そのうち日々の忙しさの中で忘れ、結果的に資産運用を続けられなくことが多いです。今回紹介した「長期・積立・分散」の原則を守れば、過去に例のない世界的な災害などが起きない限り、マイナスで終わる可能性は低いので、原則を信じて資産運用を続けていただきたいと思っています。2024年夏の相場下落を振り返る最後に、2024年の上昇相場は7月中旬から大きく調整局面に入り、特に日銀の利上げもあった7/29-8/2の市場は円高と株安が重なり、資産価格が急激に落ち込むことになりました。大きな相場下落前の環境(2024年7月頭まで)を整理すると、株式市場はAI普及の加速によりNVIDIAを筆頭とする半導体銘柄の成長に牽引されていた米国の大型テクノロジー銘柄の占める時価総額比率は歴史的高水準だったFRBの利下げ延期に加えて日銀の利上げ遅れにより歴史的な円安が続いていたという状況でした。こうした中、米国企業の第3四半期決算の内容が振るわず、経済指標も予想より悪化していたことで、米国の景気後退リスクが意識されました。これにより、1と2で過熱していた市場は一気に反転下落が始まり、米国市場全体の大幅下落につながりました。また、日銀の利上げが予想以上に早く実行されたことにより、急速に円キャリー取引が巻き戻され(円を借りてドルに投資する取引が解消され)、急速な円高が進みました。今回の相場下落は、戦争・パンデミック・金融システム危機のような世界的な災害が発生したわけではなく、金融政策とAIでの相場過熱が原因である点が重要です。状況が悪化すれば、FRBの利下げ幅の拡大や日銀のさらなる利上げ延期で経済を刺激するオプションもあるため、底の見えない落ち込みになるリスクは低いと考えられます。

ハリス氏対トランプ氏で接戦予想の米大統領、株価にどう織り込むか
本記事では、接戦が予想される米大統領選が米国株市場に与える影響を考察します。「トランプラリー」、「トランプトレード」やトランプ氏再選が米国株市場に与える影響については過去の記事で解説していますので、関心のある方はあわせてご覧ください。支持率横並び、接戦予想の米大統領6月の第1回討論会、7月のトランプ氏の暗殺未遂事件を受けて、今年の大統領選挙戦はトランプ候補優位との見方が強まっていましたが、バイデン氏の選挙戦撤退から大統領選の先行きに対する不透明感が強まっています。民主党は8月19日から22日までシカゴで開催される党大会で新たな候補者を選出する必要がありますが、ハリス副大統領が候補とされています。ブルームバーグの世論調査によると、選挙戦の結果を左右する可能性のある激戦7州全体でのハリス氏の支持率は48%、トランプ氏は47%と1ポイント差に迫る接戦になっており、ロイター通信の調査では、ハリス氏がトランプ氏を2ポイント上回っていました。11月の投票までは様子見ムードかアナリストらは、政治ニュースで市場は変動するものの、11月の投票を前に多くのことが変わる可能性があり、投資家の関心はファンダメンタルズ・FRB(米連邦準備理事会)の政策動向・地政学的な懸念の3つであると想定しています。特に、金利と企業の利益成長に焦点が当てられており、2024年上期は生成AIへの期待が市場の成長を牽引し、S&P500のリターンの30%はエヌビディア1社によるものでした。また、9月の利下げを確信するにつれて、地政学的リスクへの注目が高まりつつあります。7月30-31日に開催された米連邦公開市場委員会(FOMC)の定例会合の会見では、パウエル議長から9月にも利下げに動く可能性があるとの見解が示されています。市場関係者の多くは、ウクライナ戦争、ガザとイスラエルの紛争、米中関係の継続により、地政学的緊張から下半期に逆風が強まることを懸念し、下落リスクを回避するポートフォリオへ調整しています。一方、防衛関連株セクターを追跡する指数は7月に9.2%上昇し、2022年10月以来の最大の値上がりとなりました。これは、S&P500指数全体の1.1%上昇の8倍以上のパフォーマンスでした。大統領選挙年は、夏季にサマーラリーが期待され、その後9月10月は選挙を目前としマーケットは様子見へ。選挙を終え、大統領が決定した後から年末にかけて株価が再び上昇に転じるというのが大統領選挙年のアノマリー(規則性や傾向)となっていますが、2024年の夏については米大統領選を巡る不透明感から、夏枯れとなる可能性も指摘されています。また、UBSは2024年末までにS&P500が5,900前後で推移するという基本シナリオは、民主党政権が法人税を上げたり、トランプ氏が選挙演説で掲げたほどの高関税を課したりした場合を除き、ほとんどの政治シナリオに沿うとの見解を示しています。
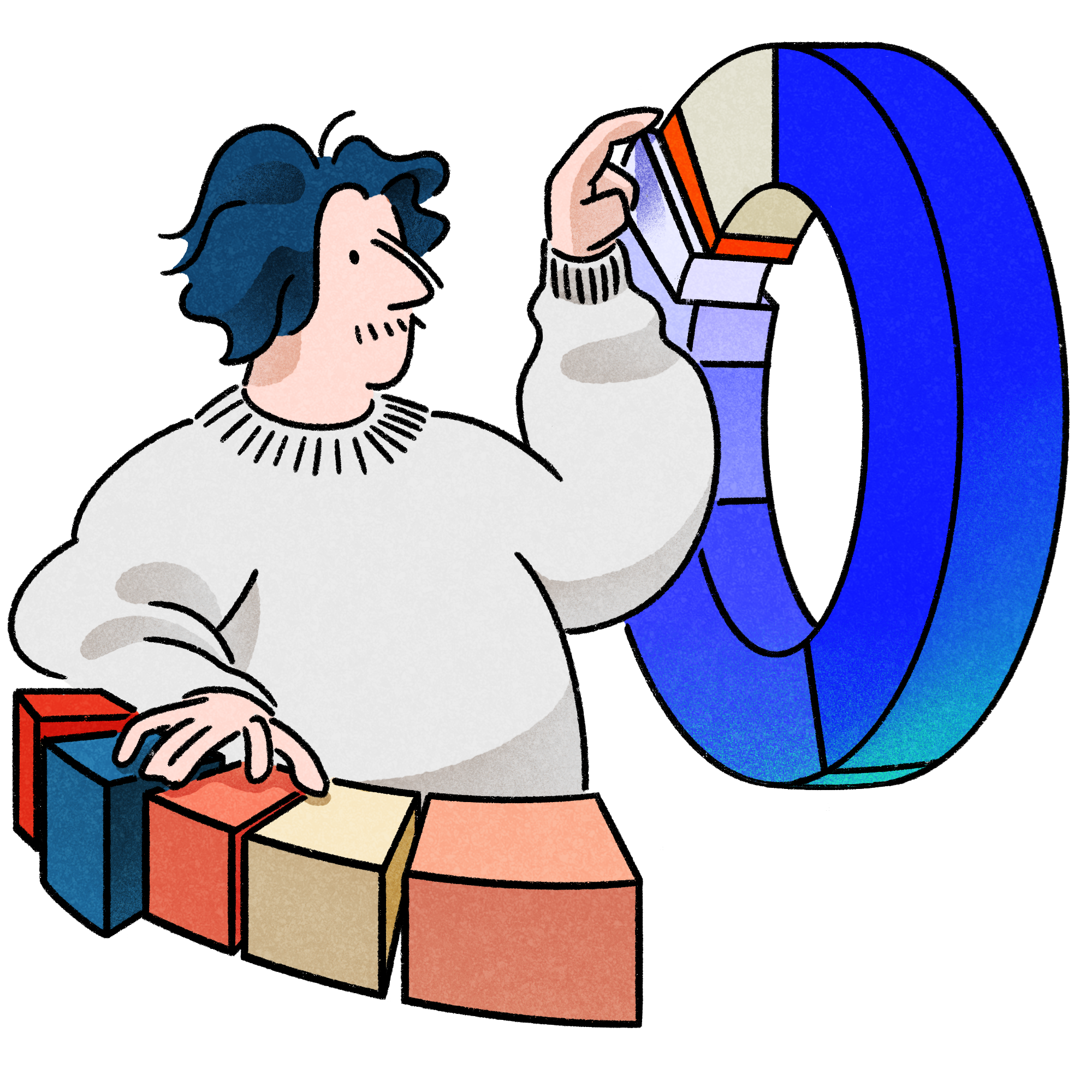
リスクオフとは?相場下落時の3つのオプション
こんにちは、ブルーモ証券代表の中村です。米国株市場は近年右肩上がりで上昇していますが、上昇相場には「調整」と呼ばれる短期的な下落局面が必ず生まれます。これは、過熱した株価を適正水準に修正するような取引が生まれ、それまでとは逆方向に株価が揺れることを意味します。上昇相場の中で投資を始めた方も多く、下落局面を初めて経験する方もいると思うので、相場が下落した時にどうすれば良いのか、いくつか判断材料を提供できればと思います。ブルーモでは、リバランス機能によってポートフォリオの組み替えを簡単に実行できるので、今後の運用を迷っているユーザーの皆さんも是非読んでみてください。(最終更新:2024年8月)目次前提:長期投資であれば時間は味方リスクオフとは?「何もしない」以外の3つのオプションオプション1:株式に追加投資していくオプション2:安全資産の比率を高めるオプション3:一時的に安全資産に逃避する安全資産とは?おすすめのリスクオフ先米国短期債券ゴールド2024年の調整局面4月:米国利下げ延期見通しと中東情勢で、上昇相場に調整が入った7月:過熱した株価に企業業績が追いつかず、調整局面へ下落相場の中でも上がっているポートフォリオは?前提:長期投資であれば時間は味方まず基本的な部分ですが、長期で分散した投資をしている場合、足下の相場が下落しても慌てる必要はありません。投資期間が1ヶ月のような短期ではなく、10年以上のような長期であれば、世界経済が成長する中でリターンが出る確率は高いです。以下は当社HPにも掲載している過去30年の株式相場推移ですが、少なくとも米国市場は過去に大きなショック(ドットコムバブル、リーマンショック、コロナショック)もありましたが、長期的に株式市場は上昇しています。もう少し細かく月次のS&P500指数の動きから、各ショックの継続期間と下落幅をまとめたものは以下になります。足下の相場下落はここまで大きな話になっていませんが、ワーストシナリオを知る意味で参考になります。なので、長期的な資産運用をするのであれば「ここで投資をやめる」は得策ではなく、「何もしない」でも大きな問題はないです。ただ、足下の下落に対して何か動きたい方に向けて、いくつかのオプションを解説したいと思います。リスクオフとは?「何もしない」以外の3つのオプション投資用語で「リスクオフ」とは、投資家が相場の下落に備えて金融資産をリスクの高い商品からリスクの低い商品(安全資産)に移すことを言います。逆に「リスクオン」とは、投資家がリスクの高い商品に移行することを指します。足下の相場に対して「リスクオフ」をするかどうかは、今後の市場に対する見立てに依存します。以下に「何もしない」パターン以外の投資オプションを、市場への見立てによってまとめました。オプション1:株式に追加投資していく仮に足下の相場下落が一時的な場合、下落した価格で投資できるチャンスと考えることができます。投資からのリターンは、投資している銘柄の平均取得単価(投資時の株価平均)と時価の差分で生まれるので、株価が低い時に資金をたくさん入れると、当然ですが将来上昇した時のリターンも大きくなります。なので、投資銘柄の平均取得単価を下げるため、新たに現金を投入して追加投資することがオプションになります。注意点としては、株価の下落がさらに続く場合、追加投資分も含めてしばらく損失が出るので、相場の下げ止まりに確信が持てない場合、分割して徐々に資金を入れていくのが得策です。積立投資設定をしている方は、何も設定を変えないと基本はこのオプションで投資が続きます。オプション2:安全資産の比率を高める相場が下落しても影響を受けない安全資産のポートフォリオ比率を高め、相場変動に対する影響を中和するオプションで、今回のオプション1とオプション3の中間に当たります。具体的には株式・暗号資産・不動産といったリスクの高い商品を売却し、債券などのリスクの低い商品に投資するリバランスを実行することになります。相場変動への影響中和は下落時も上昇時も同じなので、相場上昇時のリターンも限定的になる点には注意が必要です。基本は一時的に安全資産の比率を高める想定ですが、今回のような相場下落に備え、安全資産をこの先もある程度組み込むのも良いでしょう。オプション3:一時的に安全資産に逃避する3つ目は相場下落に対して最も大きな動きになりますが、一時的にポートフォリオ全体を安全資産で構成してリバランスするというオプションになります。相場下落の影響は全く受けなくなるので、どれだけ市場が悪化しても資産が減ることはなくなります(安全資産そのものに変動がある場合を除く)。「ここで投資をやめる」に近いように感じるかも知れませんが、大きな違いは「一時的なこと」「安全資産からも一定のリターンを期待する」点にあります。「一時的なこと」とは、上昇のタイミングでのリスクオン(安全資産から株式等にリバランスすること)を実行し、上昇局面でのリターンを取り逃がさないことを意味します。このオプションを取る場合、いつ戻すかをその後も検討するのが大事です。安全資産とは?おすすめのリスクオフ先現金以外の安全資産として、ブルーモからも投資できる代表的なものを2つ紹介します。うまく活用すれば下落相場でも一定のリターンを期待できます。米国短期債券安全資産の一番代表的なものは債券(特に国債)です。債券は一定の利率を設定して発行された借入のための有価証券です。国債であれば借入元は政府なので、(特に先進国なら)債務不履行のリスクはほとんどなく、利率から安定したリターンを期待できます。今回の相場下落の大きな要因にもなっている「米国の高金利」ですが、これは裏を返すと米国の債券の利率が高いことを意味しています。なので、米国債に投資することで相場変動を回避しつつ、日本の金利よりは遥かに高いリターン(2024年4月時点で年利回り5%程度)を得ることができます。ただし、リスクオフを目的に債券投資する場合、気をつけないといけないのが「短期債であること」です。長期債の場合、金利が上がると価格が下がる関係にあるため、米国の利下げがさらに遅れるとそのタイミングで価格下落に直面するリスクがあります。ブルーモでも取り扱っている具体的な商品としては、「米国短期国債ETF(SHV)」と「米ドル建て投資適格変動金利ETF(FLRN)」がリスクの低さからおすすめです。米国短期国債ETF(SHV)残存期間1年未満の米国債に投資するETFで、流動性が極めて高いため、金利が上下してもほとんど価格が変動しません。過去5年間の値動きでも、+0.47%~-0.71%の間でしか動いておらず、ほぼ現金見合いとも言える変動の低さです。ここまで安全だとリターンも低そうですが、足下の米国金利の高さから分配年利回りは2024年4月時点で5.27%と、安全資産としては安定したインカムリターンを提供してくれます。米ドル建て投資適格変動金利ETF(FLRN)こちらは変動金利債に投資するETFで、投資債券の金利自体が市場水準に合わせて変動するので、金利の影響での価格変動は限定的です。こちらも2024年4月時点の分配金利回りは5.97%と、一定のインカムリターンを提供してくれます。SHVも同様ですが、短期債は金利が下落するとそれに伴い分配金利回りもすぐ下がるので、将来的にも年5%のリターンを約束されているわけではなく、金利下落局面(そしておそらくは株価上昇局面)での見直し検討は必要です。ゴールドもう一つの代表的な安全資産がゴールド(金)です。信用リスクのない(投資先が破綻したりがない)現物資産として、金はリスクオフのタイミングで買われる傾向にあります。最近は世界の中央銀行が運用先として金を買っていることから、さらに相場が上がっており、株式市場が下落する中でも金は上がり続けています。金に手軽に投資する方法は、ETFを購入することで、ブルーモでもゴールドETF(GLD)を取り扱っています。ゴールドETFは過去5年で83%上昇しており、過去1ヶ月間でも9.3%上昇しています。ただし、短期債と違って、金は現物資産の取引状況によって下落する可能性もあるので注意が必要です。資産価格の変動をどれだけ排除したいかで、短期債ETFにするかゴールドETFにするかを決めると良いでしょう。2024年の調整局面2024年の相場は年間で好調なものの、何度か調整局面が出ています。ここでは7月末時点での調整局面を紹介します。4月:米国利下げ延期見通しと中東情勢で、上昇相場に調整が入った2024年第2四半期は世界的に株式市場が調整局面に入り、4/15-4/19の1週間で米国のS&P500指数は3.8%下落、日本の日経平均も5%下落するなど、大きな市場変動が起きています。そもそもの話として、4月に入ってからの株式市場で何が起きているかを振り返ります。2024年の株式相場は、米国での利下げ期待により好調でした(上昇を続けていました)。利下げで企業業績が良くなり、株価上昇を見越した投資家が米国株への投資を進めたことで、相場全体が上がっていました。ここに「利下げ延期見通し」と「中東情勢の不安定化」が飛び込んできました。「利下げ延期見通し」は、米国経済の強すぎる指標(物価指数など)が明らかになることで、FRBが利下げを予想通りには実行できない見通しが出てきたことを意味します。経済が強いのは良いことなのですが、結果的に利下げ延期見通しになって株式相場を下落させています。「中東情勢の不安定化」は、イスラエルと周辺勢力の関係が悪化することで原油の流通に問題が出て、原油価格の高騰から経済の低成長につながるのではないかという株価を伸びにくくしています。大きな危機が顕在化している状況ではなく、米国に限れば実体経済は堅調ですが、上記による不確実性から株式市場のリスクオフが進んでいるのが現状です。7月:過熱した株価に企業業績が追いつかず、調整局面へ2024年第2四半期は、4月の調整局面後、7月頭まで半導体中心に株価の急上昇が続きました。物価・景気の鈍化がFRBの利下げ期待を引き上げ、NVIDIAはじめ半導体企業の好業績がテクノロジー銘柄の株高を牽引しました。しかし、7月中旬くらいから大型テクノロジー株への過度な資金集中を避けるための資金流出が始まり、過熱した半導体相場も米中関係への懸念から調整が入りました。また、2024年第3四半期発表の決算も、NVIDIAを除くM7銘柄はMetaとAppleを除いて内容は期待に満たないもので、これまで高金利で抑制が必要だった米国企業業績に陰りが出てきて、それが株価の下落につながりました。9月の利下げは市場に織り込まれる中、製造業指数などで景気鎮静化のシグナルが出ると、景気後退(=企業業績の悪化)シグナルと捉えられ、株価が下落する関係も出てきました。これは、2024年上半期の市場が景気鎮静化が利下げ期待につながって株価上昇をもたらしたのと、大きく異なる傾向です。下落相場の中でも上がっているポートフォリオは?ブルーモでは、「週間比ランキング」から直近でどんなユーザーのポートフォリオが評価損益で上昇しているか分かります。2024年4月の調整局面での動きを見ると、高配当株の公式ポートフォリオをコピーして運用しているユーザーのポートフォリオが伸びていました。具体的には「ダウの犬」「高配当株式セレクション」の公式ポートフォリオは週間比で1.8%くらいの上昇を見せていました(同期間でS&P500は3.8%下落)。また、債券ETFをミックスした公式ポートフォリオも価格変動しておらず、一定の分配金利回りがあることを考えると、これらのポートフォリオをコピーして運用している場合もリスクオフ時の投資としてはうまくいっていそうです。セクター特化のポートフォリオでは、「小売・生活必需品」「金融サービス」の週間比上昇が大きく、リスク時に強いセクターも見えています。