ライブラリー

日銀利上げ観測後退、円安進行──「対日関税25%」が市場に与える影響とは
7月7日(米東部時間)、トランプ米大統領は日本からの輸入品に対し、8月1日から25%の関税を課すと表明しました。ただし、市場開放や非関税障壁の撤廃などに応じれば「課税措置を修正する可能性もある」と譲歩の余地を残しています。本記事では、対日関税が市場に与える影響と今後の焦点を解説いたします。3週間の「猶予延長」も楽観できずかつてトランプ氏が日本に対して「30%〜35%の関税」を示唆していたことを考えると、25%という水準は最悪の事態は回避できた内容とも言えます。しかし、8月1日という関税発効日は、7月20日に参院選を控える日本にとっては、交渉材料を提示しづらいタイミングであり、実質的な交渉期間は限られています。仮に参院選後に政権の枠組みが変化すれば、関税協議の行方にも不透明感が増す可能性があります。日銀の利上げ観測が後退、長期金利は上昇今回の発表は、日銀の金融政策スタンスにも影響を与えています。次回の日銀会合(7月30〜31日)は関税猶予期間中となるため、新たな判断を下すことは難しくなりました。このため、市場では「早ければ10月にも利上げ」との観測が後退し、一部では利上げが2026年1月にずれ込むとの見方も浮上しています。一方で、財政悪化懸念から、超長期金利には上昇圧力がかかっています。7月8日の債券市場では、30年国債利回りが一時3.09%と、前日比12.5ベーシスポイント急上昇しました。みずほ証券の大森翔央輝チーフ・デスク・ストラテジストは「もはや理由のいかんを問わず、損失を抱えたポジションを解消しようとする投げ売りが加速している状況だ」と指摘。超長期債の脆弱性が再び浮かび上がりました。円安圧力の高まり為替市場でも影響が顕在化し、円は一時1ドル=146円台まで下落。円安を後押しする背景には以下のような構造的な要因があり、対日関税は円安を連想させる要素が多いというのが市場の共通認識です。高関税による輸出減少 → 貿易収支悪化日本企業の米国生産移管 → 対外直接投資の増加企業収益の圧迫 → 賃上げの鈍化 → 日銀利上げ後退利上げ観測の後退は円売りの地合いを強め、さらにしばらく円高方向に向かう材料は見当たらないとの見方が広がっています。今後の注目は、相互関税が米国内インフレを招く可能性に対する市場の反応です。仮に批判が高まれば、トランプ政権としても内容の見直しに動く可能性も否定できません。ただし、関税引き下げに代わって利下げやドル安誘導政策に軸足を移すとの見方も根強くあります。

2025年夏、米国株はサマーラリーか夏枯れか?今後の市場はどちらへ動く
7月末に大型ハイテク銘柄の決算報告やFOMC(米連邦公開市場委員会)といった重要イベントが控えるなか、市場では「サマーラリー」と「夏枯れ相場」という対照的なアノマリー(規則性や傾向)に注目が集まっています。本記事では両者の特徴を解説しつつ、2025年夏の米国株市場を展望していきます。 2025年後半の米国株見通しについては過去の記事にて取り上げていますので、ご関心のある方はあわせてご覧ください。2025年はサマーラリーか夏枯れ相場か「サマーラリー(Summer Rally)」は、夏季に株式市場が上昇する傾向を指し、米国では独立記念日(7月4日)からレイバーデー(9月第1月曜日)までの期間に見られます。機関投資家が夏季休暇の前に買いを入れる動きや、需給の偏りが要因とされています。なかでも、2025年のような大統領選挙翌年の7月は好調なパフォーマンスとなる傾向があり、1950年以降、7月のS&P500指数平均リターンは2.2%となっています。一方で「夏枯れ相場」とは、機関投資家の不在により株式市場の取引高が減少し、相場が上がりにくく、悪材料に反応して株価が下振れしやすい相場を指します。一般的には一時的な調整とされ、長期的な市場の健全性を損なうものではありません。株高の勢いは夏に持ち越されるか足元では、6月までの上昇を受けて、7月相場にも強気な見方が広がっています。Carson Groupチーフ・ストラテジストのライアン・デトリック氏は「5月・6月に株式市場が好調であると、その勢いは7月以降にも引き継がれる傾向がある。過去16回の類似ケースでは15回で下半期も上昇した」と指摘します。また、米ドル安(3年ぶりの安値水準)や中東の地政学リスク後退も米国株への買い意欲を後押ししています。センチメントにも変化が見られます。今後6ヶ月間の市場の方向性に関する個人投資家の意見を測定するAAIIセンチメント調査では、6月25日時点の調査では弱気派(40.3%)が強気派(35.1%)を上回っていたものの、7月2日には強気派(45.0%)が弱気派(33.1%)を逆転。投資家心理は改善傾向にあり、サウンドハウンドAI(SOUN)、ソーファイ・テクノロジーズ(SOFI)といったモメンタム株の物色も、投資家のリスク選好姿勢を裏付けています。株高は一部銘柄に依存、ハイテク決算が市場の方向性を左右か現在S&P500の予想PERは約22倍程度と高水準ですが、生成AIブームの追い風を受けた成長株への選好は根強く、特にエヌビディア(NVDA)は再び過去最高値を更新し、指数に対する影響力を強めています。ただし、株高は一部のハイテク銘柄に偏っており、S&P500構成銘柄の約30%は50日移動平均線を下回る状況となっています。中小型株を中心としたラッセル2000指数や、ダウ平均株価の軟調さもこの構造を裏付けており、テクノロジー株、特に「マグニフィセント・セブン」の決算結果は、市場全体の方向性を左右する重要イベントとなるでしょう。米関税や金融政策を巡るリスク要因は依然存在一方、投資家心理の重石となっているのが、米関税政策と金融政策の不確実性です。直近では、トランプ大統領が8月1日の相互関税発動日は確定しているとしつつ、各国から提案があれば延期も検討する用意があると述べましたが、アナリストらは、関税発動期限を緊張の大幅な高まりなく乗り越えることができれば、短期的には懸念事項が一つ減ると指摘しています。金融政策では、7月29〜30日のFOMCでFRB(米連邦準備制度理事会)が9月の利下げに含みを持たせるかが注目されます。現在FedWatchの9月利下げの織り込みは50%を超えていますが、パウエル議長は利下げについては引き続き「データ次第」と様子見の姿勢を崩しておらず、FOMCで引き続き慎重な姿勢が示された場合は、株価の調整リスクも残ります。今後の注目イベント7月15日:消費者物価指数(CPI)7月16日:生産者物価指数(PPI)7月17日: 小売売上高7月29-30日:FOMC8月1日:相互関税発動日
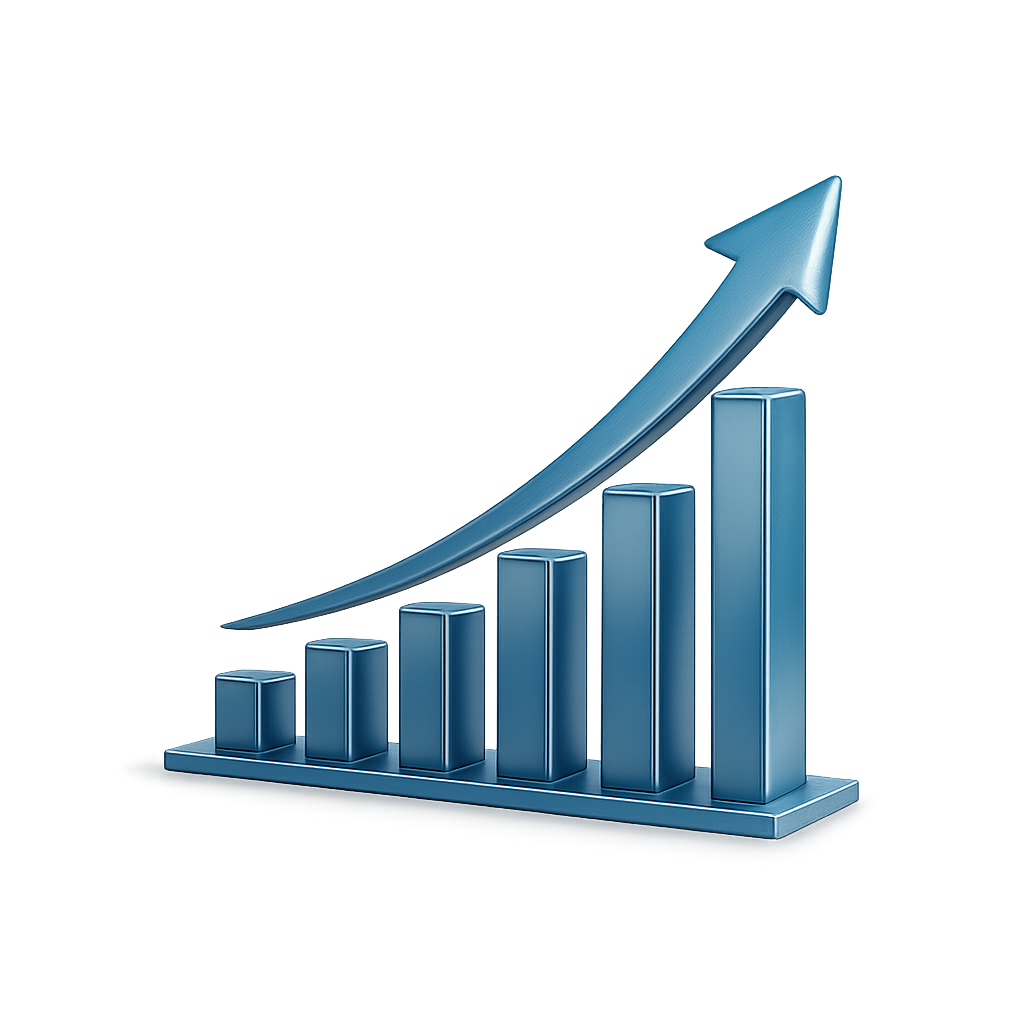
雇用統計が予想を上回り、米国経済の堅調さから株価は最高値を更新|米国市場サマリー
先週は、米雇用統計の好調、FRBによる利下げ慎重姿勢、米中を含む通商問題の進展を受け、全体として堅調な展開となりました。週前半はOracleの好決算や銀行株への規制緩和期待から投資家心理が改善し、主要指数が揃って上昇しました。一方、パウエルFRB議長が議会証言で利下げに慎重な姿勢を示したことで一時的に上値が抑えられる場面も見られました。しかし、週半ば以降、ベトナムとの貿易合意やNVIDIAをはじめとする半導体株の好調さを背景に市場は再び上昇基調を強めました。週末に発表された6月の米雇用統計が市場予想を上回る強い内容となり、景気懸念が後退。S&P500とNASDAQは連日のように史上最高値を更新し、四半期の節目を好調に締めくくりました。なお、7月4日は独立記念日のため休場でした。全体的には、好調な企業決算と底堅い経済指標に支えられ、主要指数は週間ベースで上昇して取引を終えました。為替は、強い米雇用統計で一時145円台までドル高・円安が進みましたが、米財政・通商政策の不透明感が上値を抑え、週を通じて144円台を中心に上下動。終値は144.47円前後と、週初比では小幅なドル高で終了しました。米国株式市場:予想を上回る雇用統計で米経済の堅調さが示され、株価は最高値を更新6月30日(月) 米国株式市場は主要3指数がそろって上昇し、第2四半期を好調に締めくくりました。ダウ工業株30種平均は0.5%、S&P500は0.6%、NASDAQは0.5%上昇しました。Oracleの決算が市場予想を上回ったことが好感され、株価が4%上昇したほか、銀行株もFRBの規制緩和期待から堅調でした。一方、原油価格の軟調さを受け、エネルギー株は売られる展開となりました。7月1日(火) 市場は小動きで、S&P500とNASDAQは僅かに下落し、ダウは小幅に上昇しました。パウエルFRB議長が議会証言で利下げに慎重な姿勢を示したことが市場の上値を抑える要因となりました。また、トランプ政権の税制改革法案への注目が再燃し、利益確定の動きが見られました。Teslaは中国販売の伸び悩みが指摘され、株価が2.1%下落しました。7月2日(水) 市場は再び反発し、S&P500とNASDAQが史上最高値を更新しました。ベトナムとの貿易合意や半導体株の好調さが相場を支援しました。特にNVIDIAがAI需要の拡大を背景に時価総額4兆ドルに迫る勢いで株価が3.8%上昇しました。また、ADP雇用統計が市場予想を下回ったことで利下げ期待がやや高まり、株式市場への資金流入を後押ししました。7月3日(木) 強い米雇用統計が好感され、市場は続伸しました。ダウは0.8%、S&P500は0.8%、NASDAQは1.0%上昇し、いずれも史上最高値を更新しました。6月の非農業部門雇用者数が予想を上回ったことで、経済の強さが改めて意識されました。Nikeは四半期決算が予想を大きく上回り、株価が9.5%急伸しました。一方、利下げ観測後退で一部の高成長株が利益確定売りに押されました。7月4日(金) 独立記念日のため米国株式市場は休場となりました。為替市場:雇用統計でドル高になるも、税制・通商政策の不透明感から大きく動かず為替は中東情勢や米雇用統計、米財政・通商リスクを背景に144~145円台を中心とした上下動が続きました。週初はドルがやや弱く、月曜30日には約143.90円で始まりました。7月1日はドルが下落し143.41円まで円高が進んだ一方、米雇用統計の予想超えによって再び144円台半ばへ戻りました。週末にかけては、税制・通商政策における不透明感がドルの重しとなり、円が若干買い戻されながらも相場は144~145円のレンジで収まりました。結果として、週末終値は144.47円付近で終えました。ブルーモの公式Xでは決算や指標の速報をお届けしているので、興味ある方はフォローしてみてください。https://x.com/Bloomo_invest
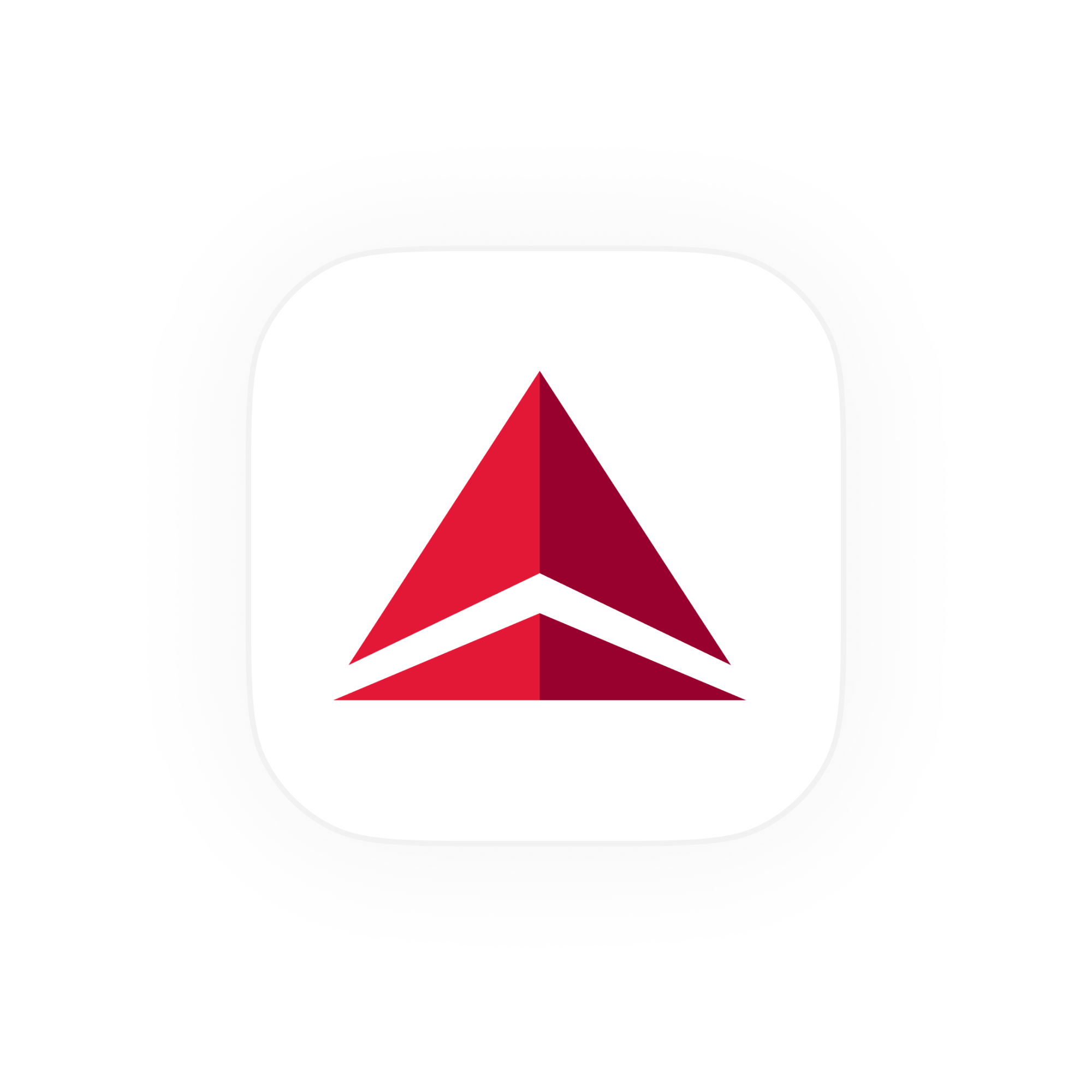
【デルタ航空決算(2025年2Q)】国内需要の停滞、回復の鍵は国際線とコスト管理(Delta Air Lines)
本記事では、デルタ航空(DAL)の2025年4月発表2025年度第1四半期決算を振り返り、7月に控える2025年度第2四半期決算の見どころを解説します。前回の決算では増収ながら国内需要の減速を認め、下期の座席供給を前年並みに抑える方針を示しました。今回の決算ではEPS1.70~2.30ドルの会社予想に対し、市場コンセンサスは約2.04ドルとやや強気ですが、燃料価格の低下と国際・プレミアム需要がどこまで利益を下支えできるかが焦点です。前回決算の振り返り(2025年第1四半期)デルタ航空の第1四半期決算では、売上高が140億ドルとなり、前年同期比で微増しました。一方、調整後1株当たり利益(EPS)は0.46ドルで、前年の0.45ドルからわずかに増加し、市場予想の0.40~0.44ドルを上回りました。国際線とプレミアムクラスの需要は引き続き堅調で、特に太平洋路線の売上は業績を下支えしました。また、アメリカン・エキスプレスとの提携による収入は20億ドルに達し、前年同期比で13%増加しました。これらの高マージンセグメントが全体の収益を下支えしています。しかし、国内線の一般キャビン需要は低迷し、収益性を示す指標(TRASM)は前年より1%低下しました。デルタ航空の経営陣はこれを受け、「国内の需要成長は一旦ピークを迎えた」として、下半期に予定していた座席供給の拡大を撤回し、前年並みに抑える慎重な戦略へと方針を転換しました。決算発表後の主な動きとニュース決算発表後、デルタ航空の株価は時間外取引で8.6%上昇しましたが、その後、米国政府による関税措置再開への懸念が市場を覆い、デルタ航空を含む航空株全般が下落基調に入りました。また、デルタ航空は機内サービスの充実にも力を入れており、主要路線で無料の高速Wi-Fiの導入を拡大し、ビジネス客の囲い込みを強化しています。一方で、世界経済の減速や新たな貿易摩擦への懸念が再び高まり、特に米国内の法人旅行やレジャー需要が今後も軟調に推移するのではないかという見方も出ています。今回決算の注目ポイント今回の第2四半期決算では、デルタ航空が前回示した業績予想では、EPSは1.70ドルから2.30ドル、売上高は前年同期比でマイナス2%~プラス2%という比較的広いレンジが設定されています。一方、市場のアナリストたちは、EPSを平均で約2.04ドルと予想しており、やや強気の見通しとなっています。業績の改善を支えるのは、引き続き海外路線とプレミアムクラスの好調な需要です。前回決算では特に太平洋路線の売上が前年同期比16%伸びていましたが、この傾向が今回も続くかどうかは重要な注目点です。また、燃料価格が低下していることや、高収益が見込めるロイヤルティプログラム(マイレージプログラム)と提携カード収入の維持ができるかどうかにも関心が集まっています。逆に懸念材料としては、国内需要のさらなる悪化や、下期の座席供給の抑制に伴う座席当たりのコスト上昇のリスクがあります。また、米政府が再び貿易摩擦を強めたり、燃料価格が反転して上昇したりすれば、株価には追加的な圧力がかかるでしょう。株価への影響と今後の見通し株価の短期的な動きを考えると、今回の決算でデルタ航空が示した見通しの上限(EPS2.30ドル以上)を上回り、通期見通しを再び積極的に示せれば、市場は再評価し、株価の回復が期待できるでしょう。一方、EPSが1.90~2.10ドル程度の中立的な結果であれば、株価は現在のレンジ内で推移する可能性が高いと考えられます。もし、EPSが1.80ドルを下回り、需要の弱さが一層強調されるようであれば、株価は再び下落基調に入り、年初来安値を更新する展開もあり得ます。まとめと個人投資家としての対応デルタ航空の2025年第1四半期決算は、国際線とプレミアムクラスの堅調な需要に支えられ、一定の成果を上げました。しかし、国内線の需要低迷や経済の不確実性といった課題も残されています。個人投資家としては、同社の今後の業績動向や経営戦略の進展を注視し、投資判断を行う必要があります。特に、国際線需要やプレミアム収入の堅調さを維持しながら、国内線の需要低迷をどれだけ抑制できるかが焦点となります。さらに、燃料コストのメリットを最大限に活用できるか、そして年間見通しをどのように修正・提示してくるのか、という点も株価動向に直結します。

【米国株見通し】S&P500相次ぐ年末目標上方修正、強気相場継続なるか
2025年第2四半期、S&P500は2023年以来、ナスダック総合指数は2020年以来の大幅上昇となり、米国株は過去最高値で四半期を終えました。 本記事では、市場関係者による2025年後半の米国株見通しを紹介します。S&P500、相次ぐ年末目標の上方修正足元では、米国株の好調を受けて、ウォール街でS&P500の年末目標の引き上げが相次いでいます。主要金融機関・調査会社による2025年末のS&P 500の目標値ファンドストラット: 6600モルガン・スタンレー:6500ヤルデニ・リサーチ:6500ドイツ銀行:6550シティ:6300UBS:6200ゴールドマン・サックス:6100バークレイズ:6050JPモルガン:6000ファンドストラット:年末6600予想ファンドストラット・グローバルアドバイザーズのトム・リー氏は、AI関連企業を中心に企業業績が堅調で、関税問題の影響も予想より小さく、インフレ圧力も抑えられていることから、S&P500指数の年末目標を6600に設定しています。同氏は、関税懸念に敏感に反応していた市場が、現在むしろ企業業績や経済指標、そしてAI関連の投資動向に注目しており、楽観的なムードが広がりつつあると指摘。また、ISM製造業指数が50を下回る「景気後退圏」で推移していることから、まだ景気の谷にある可能性が示されており、指数が50を超えれば新たな強気相場への転換するとの見通しを示しました。懸念点としては、ワン・ビッグ・ビューティフル・ビル法案(税制改正草案)が米国債務の持続可能性に与える影響があるものの、ここ数週間の市場の反応を見ると、投資家は「単なる予算の問題」として捉えていないようだと述べています。モルガン・スタンレー:年末6500予想モルガン・スタンレーのストラテジスト、マイケル・ウィルソン氏は、年内2回の利下げが実施される可能性があることから、S&P500指数の年末目標を6500と予想しています。同氏は、4月に市場が一時的に下落したものの、すでに底を打ち、現在の反発局面はより持続的な上昇トレンドの始まりであると見ています。関税問題についても、市場はトランプ前大統領の姿勢が今後軟化する可能性を織り込み始めており、過度な懸念は不要だと指摘。企業業績も予想以上に底堅く、収益の上方修正が相次いでいることが強気の背景にあります。また、中東の地政学リスクや原油価格の動向が落ち着きを見せていることから、経済全体としての不透明感は後退しつつあると判断しています。ヤルデニ・リサーチ:年末6500予想ヤルデニ・リサーチのエド・ヤルデニ氏は、S&P500指数の年末目標を6500に設定し、「現在は明確なブルマーケットであり、1960年代半ば以降の最も優れた強気相場のリターンに匹敵する可能性がある」と述べています。同氏は、地政学リスクや関税圧力等の逆風にもかかわらず、関税不安の緩和やAI関連企業への投資増加、今後の利下げ見通しなどを根拠にリバウンドを強調。S&P 500は2030年までに10000まで上昇しうると楽観的なシナリオを示しています。一方で、現状は「マイルドなバブル(melt‑up)」に近い状態であり、実際にバブルへと発展する可能性をリスクとして提示。特に市場心理が過熱しすぎるタイミングには「急落リスク」も視野に入れるべきだと警鐘を鳴らしています 。ドイツ銀行:年末6550予想6月2日、ドイツ銀行は関税の影響緩和や好調な経済見通しを理由に、S&P500指数の年末目標を6150から6550に引き上げました。過去2年間の株高をけん引した多額の資金流入と強力な自社株買いが2025年も続き、S&P500構成銘柄の1株利益は282ドルと見通しました。シティ:年末6300予想シティグループは、これまでの予想を上回るAI関連銘柄の強さや企業の業績改善、インフレの落ち着きなどを背景に、S&P500指数の年末目標値を5800から6300に引き上げました。同社は「金利がピークを打ち、関税に対する過度な懸念も後退している」と分析しており、テックセクターを中心とした投資家のリスク選好が継続していることから、中期的には6500も視野に入ると述べています。UBS: 年末6200予想6月26日、UBSグローバル・ウェルス・マネジメントは、貿易摩擦の緩和や底堅い四半期の企業利益見通しを踏まえ、2025年末のS&P500指数の目標を従来の6000から6200に引き上げました。また、「経済が関税の一時的な影響に適応すれば、2025年後半には成長とインフレが改善し始めるだろう」という見通しを示し、2026年の年末目標についても6400から6500に上方修正しました。ゴールドマン・サックス:年末6100予想ゴールドマン・サックス・グループのデービッド・コスティン氏は、関税率の低下、経済成長の改善、景気後退リスクの減少を織り込み、6ヶ月後(2025年末)の目標株価を5900から6100に引き上げ、12ヶ月後の目標株価を6500としました。同行は、S&P 500企業の1株当たり利益が2025年に前年比7%増の262ドル、2026年には同じく7%増の280ドルになると予想し、これらの予想は「2025年第1四半期の業績が予想を上回り、今後数四半期における米国経済の成長見通しが力強いことを反映している」と述べています。バークレイズ:年末6050予想6月4日、バークレイズは関税不安の収束や企業業績の回復を材料に、S&P500指数の年末目標を5900から6050に引き上げました。同社は関税について、来年は今年と比較して追加の直接的な影響はないと予想されるが、成長とインフレへの二次的な影響は来年まで及ぶ可能性があると述べました。また、来年末のS&P500種指数の目標を6700ドル、構成銘柄の1株利益285ドルと見通しています。JPモルガン:2025年末までに6000予想6月5日、JPモルガンのストラテジスト、ドゥブラヴコ・ラコスブジャス氏は、S&P500指数の年末目標を5200から6000に引き上げました。同氏は「上昇余地はほとんど残されていない」と述べ、現在の株価水準は多くのポジティブ材料をすでに織り込んでいると指摘。AIブームや関税リスクの後退を認めつつも、今後のリスク管理の重要性を強調しました。また、相場の主導役が、これまでの強気相場をけん引してきた大型テクノロジー企業に再び戻ると予想。最も確信度の高い取引としてモメンタム株、特にハイテク7社「マグニフィセント・セブン」や半導体、その他AI関連の銘柄を挙げています。

中東情勢の安定化とFRB利下げ見通しで株価は最高値へ|米国市場サマリー
先週は、イスラエルとイランの停戦報道による地政学リスクの後退や、FRBによる早期利下げ期待の高まりを背景に、全体として堅調な展開となりました。原油価格が急落したことでインフレ懸念が和らぎ、市場心理が改善。また、パウエルFRB議長が議会証言で慎重な姿勢を示したことで利下げ観測が一段と強まり、株式市場への資金流入を後押ししました。特にTeslaやBroadcom、Nikeなどが好材料で大きく上昇したほか、FRBが銀行のレバレッジ規制緩和を示唆したことで金融株も買われました。米中間でレアアース供給に関する合意が成立したことも投資家心理を支援し、週末にはNASDAQとS&P500が過去最高値を更新。NASDAQは4月の安値から20%超の回復を見せ、「強気相場」入りを明確にしました。結果として、主要指数は週間を通じて強い上昇基調を維持しました。為替は、中東情勢の緊張再燃で週初に146円台へ上昇しましたが、その後は地政学リスクの後退と米利下げ期待が強まったことで円高方向へ戻し、週末は144円台半ばで終了。週間では上下に振れる展開でした。米国株式市場:中東情勢の沈静化と米中協議進展でリスクオン、株価は最高値へ6月23日(月) 原油先物が一時+6%高から-7%安へ急反落し、インフレ懸念が後退したことで買いが優勢となり、ダウは+0.9%(+375ドル)、S&P500は+1.0%、NASDAQは+0.9%で反発しました。FRBボウマン副議長が「7月会合での利下げも排除せず」と発言し、金利先安観が強まったことも追い風でした。個別では Tesla がロボタクシー実証開始を受けて8%超急伸し指数をけん引、エネルギー株は原油安で軟調でした。6月24日(火) イスラエル‐イラン停戦報道で地政学リスクが緩和し、原油続落とともに金利低下期待が高まり、ダウ+1.19%、S&P500+1.11%、NASDAQ+1.43%と続伸しました。Broadcom がHSBCによる格上げで過去最高値を更新し、半導体株が全面高。FRBパウエル議長の議会証言は「当面様子見」の姿勢にとどまり、利下げ観測を裏付ける形となりました。引け後には FedEx が決算を発表し、時間外で売られました。6月25日(水) パウエル議長2日目証言を控え様子見が強まり、ダウ-0.25%、S&P500横ばい、NASDAQ+0.31%とまちまち。Tesla は欧州販売不振報道で下落し、FedEx と General Mills も弱い業績見通しで売られました。一方、引け後の決算で Micron Technology が予想を上回るガイダンスを示し、時間外で急伸。中東情勢が小康状態を保つなか、指数は高値圏で足踏みしました。6月26日(木) 好調な米耐久財受注・新規失業保険申請の減少を背景に景気懸念が後退し、ダウ+0.9%(+404ドル)、S&P500+0.8%、NASDAQ+1.0%へ上昇。FRBが大手銀行のレバレッジ規制(eSLR)緩和案を公表し、JPMorgan Chase や Goldman Sachs など金融株が全面高となりました。また、銅高を受け Freeport-McMoRan や Southern Copper が買われ、景気敏感株に資金が循環しました。6月27日(金) 米中レアアース供給加速の合意と利下げ期待を背景に、S&P500とNASDAQが終値ベースで史上最高値を更新し、それぞれ+0.52%、NASDAQも+0.52%、ダウは+1.00%で締めくくりました。好決算と関税対策を示した Nike が15%急伸し、消費関連を押し上げた一方、中国向け売り上げ懸念で MP Materials などレアアース関連が下落。トリプルウィッチング(株価指数・個別株先物・オプション同時清算)による出来高急増も相場を活性化させました。主要3指数はいずれも週間で上昇し、NASDAQは年初来高値を更新しました。為替市場:中東情勢安定化からドル高になるも、FRBの利下げ観測が出て円高に戻す為替は中東情勢と米金融政策の見通しを背景に上下に揺れ動きました。週明けの23日は、中東の軍事緊張が高まる中で安全通貨としてのドル需要が強まり、ドル/円は145円台後半から146円台へと急伸。原油価格の上昇により対円で約2.4%の急落となりました。24日以降はリスク環境がやや落ち着きを見せ、米連邦公開市場委員会(FOMC)への思惑からドルが若干軟化。テクニカル的には145円~146円のレンジ内で推移しました。米中の地政学リスク後退とも呼応し、27日には一時144.38円まで下押しされ、週末には144.6円で取引を終えました。全体として、週前半の地政学ショックによるドル高が中心となる一方、週後半にはやや落ち着いた動きに。これは、地政学リスクだけでなく米金利政策への思惑が両通貨の行方を左右したことを示しています。ブルーモの公式Xでは決算や指標の速報をお届けしているので、興味ある方はフォローしてみてください。https://x.com/Bloomo_invest

タイガー・グローバルとは?投資戦略と2025年最新ポートフォリオを解説
本記事では、2020年にヘッジファンド収益ランキングで世界首位となり、投資家に100億ドル以上の利益をもたらしたタイガー・グローバル・マネジメント(Tiger Global Management)を紹介します。同社の創業背景や投資戦略、そして2025年3月末時点の最新ポートフォリオを解説します。Tiger global managementとはタイガー・グローバル・マネジメントは2001年に設立され、ニューヨーク市に本社を置く世界有数のヘッジファンドです。テクノロジーセクターへの集中投資で知られつつも、消費財、フィンテックといった幅広いセクターに投資しており、これまでに20以上のファンドを組成し、運用資産残高は700億ドルを超えています。創業者のチェイス・コールマン氏は、1997年から2000年にかけて著名投資家の故ジュリアン・ロバートソン氏(タイガー・マネジメント創業者)の下で投資の基礎を学びました。ロバートソン氏は、ジョージ・ソロス氏と並んで20世紀が生んだヘッジファンドの大御所と称され、築き上げた純資産総額は40億ドルを超えます。同氏の掲げた「最も長期成長を望める企業の株式を購入し、経営が悪い企業を空売りする」という運用手法は、現在のタイガー・グローバル・マネジメントの投資の核となっています。2000年にロバートソン氏がタイガー・マネジメントを閉鎖した際、コールマン氏は2,500万ドル以上の運用資金を託され、2001年にヘッジファンド「タイガー・テクノロジー」を設立(後に現社名へ改称)しました。2003年にはプライベート・エクイティ(未上場企業)投資に進出し、Facebook(現メタ・プラットフォームズ)やLinkedIn、JDドットコムなど、当時まだ黎明期にあったテック企業へのベンチャー投資を展開。これにより、上場・未上場の双方に投資する「クロスオーバー投資」のパイオニアとして名を馳せるようになります。コールマン氏はメディアへの露出を避けることで知られ、運用そのものに専念する姿勢を貫いています。近年は、AIやクラウド関連のグロース株への投資を積極的に進めており、2023年〜2024年第1四半期の公開株式ポートフォリオの収益率は80%超と、S&P 500のリターン(約35%)を大きく上回る成果を上げています。同時に、AI関連銘柄に偏重しすぎない分散投資も図っており、2024年の投資家向けレターでは、ポートフォリオのうち約30%は非AIセクターであり、これらのポジションも過去15カ月で約2倍に成長し、ヒット率は80%に達したと報告しています。Tiger Global Managementのポートフォリオ5月15日に米証券取引委員会(SEC)に提出された報告書「フォーム13F」により、タイガー・グローバル・マネジメントの2025年3月末時点でのポートフォリオが明らかになりました。上位10銘柄が全体の約63%を占めており、「マグニフィセント・セブン」で知られる大型テック銘柄が上位に並びます。上位保有銘柄メタ・プラットフォームズ(META) : 16.2%マイクロソフト(MSFT) : 8.81%シー(SE): 7.87%アルファベット(GOOGL) : 5.99%アマゾン・ドット・コム(AMZN): 4.71%テイクツー・インタラクティブ (TTWO): 4.55%エヌビディア(NVDA): 4.47%イーライリリー・アンド・カンパニー(LLY): 4.15%アポロ・グローバル・マネジメント(APO): 3.20%フラッター・エンターテインメント(FLUT): 2.81%生成AI領域への強気姿勢公開株式ポートフォリオは、生成AIサービスの成長に最も直接的な恩恵を受ける4大ハイパースケーラー(メタ、マイクロソフト、アルファベット、アマゾン)が全体の三分の一以上を占めています。2025年の第一四半期には、多くのヘッジファンドがDeepSeekショックやトランプ関税への警戒から、マグニフィセント・セブン銘柄を売却する中で、タイガー・グローバル・マネジメントはマイクロソフト株を約17%、アマゾン株を2.7%買い増し、メタとアルファベットについては売却せず保有を継続しました。一方で、ショートポジションを活用したリスクヘッジをしており、同四半期はショートポジションが主要リターンドライバーとなっていることが報告されています。また、半導体セクターについては選別が進んでいます。同四半期に、エヌビディア株を13%、台湾セミコンダクターズ(TSM)株を17%、ブロードコム株を23%増やす一方で、クアルコム(QCOM)やアーム・ホールディングス(ARM)の株式は全て売却し、AIインフラを支える中核企業に絞った投資方針が読み取れます。デジタルエンタメ分野への投資も維持また注目すべきは、ポートフォリオ上位にデジタルエンターテインメントやゲーム分野の企業が多く含まれている点です。シー、テイクツー・インタラクティブ、フラッター・エンターテインメントなどは、いずれもZ世代以降の「消費の主戦場はリアルからデジタルへ」という潮流を踏まえた構成で、これらのポジションも維持されました。シーは、東南アジア最大のECプラットフォーム「Shopee」や、世界的なモバイルゲーム開発会社「Garena」、急成長中のデジタル金融サービス「Monee」を傘下に持ちます。同社はシンガポールが拠点のため、トランプ政権による関税強化の影響も比較的軽微と見られています。テイクツー・インタラクティブは、人気ゲーム『グランド・セフト・オート(GTA)』シリーズの開発元で、最新作『GTA VI』は2026年5月26日発売予定。ウォール街では、2027年度の予約額が90億ドルに達するとの予測も出ています。フラッター・エンターテインメントは、米国のスポーツベッティング最大手で、オンライン賭博の拡大に乗じて成長を加速させています。著名投資家のポートフォリオを簡単コピー?ブルーモ証券では、2025年3月末時点でのタイガー・グローバル・マネジメントのポートフォリオをもとに、同様の構成銘柄・投資比率で投資を始められるサービスを提供しています。ウォーレン・バフェット氏など他の著名投資家の最新ポートフォリオも閲覧、カスタマイズ可能。気に入った銘柄構成をベースに、自分好みのポートフォリオを簡単に作成できます。

なぜ日銀は国債買い入れ減額を緩和?財務省も異例の長期債発行見直しへ
6月17日、日本銀行(日銀)は政策金利を0.5%程度に据え置くとともに、国債買い入れ額の削減ペースを2026年4月以降に緩和する計画を発表しました。2026年3月までは引き続き国債の月間購入額を四半期ごとに4000億円ずつ削減し、2026年4月から2027年3月までは四半期ごとに2000億円ずつ削減。2027年第1四半期の月間購入額を約2.1兆円にする方針です。本記事では、新たな減額計画の背景や市場の反応を整理しつつ、今後の国債需給における注目点を解説します。なぜ日銀は減額ペースを緩和したのか現在、日本の超長期国債の利回りは発行開始以来の最高水準に達しており、日銀の国債買入れ方針は市場の注目を集めていました。日銀は2024年末時点で国債残高の約半分を保有しており、国債市場における最大の保有者です。今回の措置について、日銀は「国債市場の機能改善と安定の両立」を狙いとしています。植田総裁は記者会見にて「長期金利は金融市場で形成されることが基本」とした上で、国債買い入れの減額は金利形成の自由度を高めるものの、ペースを急ぎすぎるとボラティリティの急拡大を招き、経済に悪影響を与える可能性があると指摘しました。減額ペースの緩和は、こうしたリスクを回避し、市場の安定性への配慮に基づいたものと説明しています。市場では、発表内容は概ね事前の予想通りと受け止められ、目立ったサプライズはありませんでした。ただし、一部市場関係者からは「金融政策の正常化が一歩後退した」との指摘もあり、今回の対応が超長期ゾーンを中心とする国債需給悪化への対症療法的な措置であるとの見方もあります。また、米国の財政悪化懸念やトランプ政権の通商政策に対する不透明感を背景に、世界的に長期金利が上昇する中、日本の長期金利急騰によるグローバル金融市場の混乱を回避したいという意図も透けて見えます。財務省も異例の対応──超長期債発行を年度途中で見直し一方、超長期債の需給悪化を受けて、財務省も動きを見せています。6月20日に開かれた国債市場特別参加者(プライマリーディーラー、PD)会合では、2025年度の国債発行計画の変更案が提示され、20〜40年の超長期債の年間発行額を計3.2兆円減額する方針が明らかになりました。事前報道の予想を約9000億円上回る規模となり、20年債の減額幅は倍に拡大されました。補正予算によらず、年度途中で発行計画が見直されるのは極めて異例であり、超長期債市場の需給悪化に対する危機感の強さがうかがえます。今後の注目点とリスク要因今後、超長期債の流動性の回復とボラティリティの抑制が進むかは、7月以降の長期債・超長期債入札において投資家の堅調な需要が確保できるかにかかっています。また、金融政策を巡るリスクとして、トランプ政権との貿易交渉も引き続き注視が必要です。関税引き上げは日本企業の業績や賃金動向に影響を与える可能性があり、日銀の利上げタイミングにも関わってくるでしょう。先週行われた、石破首相とトランプ大統領の会談では貿易協議に進展は見られず、米国が設定した相互関税の猶予期限(7月9日)が迫る中、政権関係者から合意時期は「秋以降になる可能性が高い」との見方も出ています。こうした不確実性が払拭されない限り、日銀としても積極的な金融正常化には踏み切りづらい状況が続くと見られます。今後の注目イベント6月24日:20年債入札7月1日:10年債入札7月3日:30年債入札7月9日: 相互関税の猶予期限
.png)
【ナイキ決算(2025年4Q)】在庫改善と中国回復が業績底打ちへの試金石に(NIKE)
本記事では、ナイキ(NKE)の2025年3月発表2025年度第3四半期決算を振り返り、6月に控える2025年度第4四半期決算の見どころを解説します。株価は年初来20%程度の下落で低迷するなか、今回の決算では「減収幅の着地」「在庫圧縮とコスト削減の進捗」「中国・デジタル販売の回復度合い」が最大の焦点となります。前回決算(2025年第3四半期)の概要ナイキの前回の決算(2025年3月発表)では、売上高は前年同期比で約9%減少し113億ドルとなりました。為替の影響を除いた場合でも7%の減収と苦しい内容でしたが、一方で市場予想を上回る1株あたり利益(EPS)0.54ドルを達成しました。これは市場の予測である0.28ドルを大きく上回る内容だったため、収益面での改善期待から一時的に株価が支えられました。ただし、粗利益率は値引き販売の影響で前年より悪化し41.5%となり、利益率回復の難しさも同時に示されました。経営陣は決算説明会で「Win Now(今すぐ勝つ)」という経営戦略を推進し始めたことで、今後の収益回復に自信を示したものの、次の四半期(今回の決算)に関しても10%台前半の売上減少を予告するなど、依然として慎重な見通しを示しています。決算後の主な動きとニュースこうした業績低迷を受けて、ナイキは収益改善を目指し、2025年4月に世界全体の従業員の約2%に相当する1,600人以上を削減する人員整理を発表しました。また、ナイキにとって長く課題となっている在庫過剰の問題については、2025年4月以降アウトレット店舗を活用した在庫整理が順調に進み始めているとの見方があり、ようやく改善方向に向かっているという報告もあります。ただし、これらは値引き販売に頼った面も強く、収益性にはまだ不安が残っています。海外市場の中でも特に重要な中国市場は、売上が前年比17%減と依然低調な状態が続いています。また、2025年6月には期待された人気ブランド『スキムズ(Skims)』との女性向け商品の共同ブランドの立ち上げが生産遅延により延期されるなど、製品戦略でもつまずきが見られます。一方で『Vaporfly 4』や『Streakfly 2』など高性能ランニングシューズの新製品が投入され、製品ラインの刷新が一定の評価を得ていることも事実です。今回の決算(2025年第4四半期)の注目ポイント今回の決算で投資家が最も気にするべきポイントは、やはり売上高の減少幅が実際にどの程度に収まるかという点です。経営陣が予告した10%台前半の減収という予測よりも改善が見られれば、市場予想を上回る結果として株価の短期的な反発を促す可能性があります。また、在庫問題の改善がさらに進展しているかどうかも注目されます。在庫が想定より大幅に減少し、粗利益率が改善方向に向かう見通しが示されれば、業績の底打ち感が高まり株価へのプラス材料になるでしょう。逆に、在庫整理が思ったより進まず追加の値引きが発生する場合、利益率改善の遅れとして株価へのマイナス材料となります。さらに、中国を中心とした海外市場での需要回復度合いも大きな焦点です。中国市場での売上回復が遅れれば、ナイキのグローバルな収益改善ストーリーに水を差すことになります。この他にも、オンライン直販(DTC)分野での回復状況や、マーケティング投資とコスト削減のバランスをどう取るかといった戦略的なポイントにも注目が集まります。特に、2024年のパリ五輪に向けたマーケティング投資が費用対効果を発揮しているかどうかは、今後の業績見通しを占う意味でも重要です。株価への影響と投資家の対応ナイキの株価は2025年に入ってから約20%下落し、59ドル前後という低水準で推移しています。これは市場がナイキの業績改善に対し慎重な見方を崩していないことを示しています。今回の決算結果次第で、株価は短期的に大きく上下する可能性があります。売上や在庫整理が市場予想より好転していれば、一時的に株価の反発が見られるでしょう。一方、引き続き中国市場が弱含みであったり、追加の値引きが利益を圧迫したりすれば、さらなる株価下落もあり得ます。個人投資家としては、今回の決算では単なる数値だけでなく、ナイキ経営陣が描く2026年度以降の成長戦略や具体的な改善策に注目することが重要です。特に在庫整理やコスト削減の実行度合いが示されれば、長期的な視点で株価回復の可能性を探る上で良いヒントとなるでしょう。業績低迷期は株価のボラティリティが大きくなりがちです。個人投資家の皆様には、リスク管理として投資の規模やタイミングを慎重に検討し、落ち着いた対応をお勧めします。
.png)
【ウォルグリーンブーツアライアンス決算(2025年3Q)】業績底打ちを占う再編加速、買収動向も株価の鍵に(Walgreens Boots Alliance)
本記事では、ウォルグリーンブーツアライアンス(WBA)の2025年4月発表2025年度第2四半期決算を振り返り、6月に控える2025年度第3四半期決算の見どころを解説します。前四半期(2Q)は売上高386億ドルで前年同期比4.1%増と増収を確保した一方、のれん減損などの影響で調整後1株利益(EPS)は0.63ドルへ半減、フリーキャッシュフローも赤字が続きましたその後、配当停止や大量閉店、さらにはシカモア・パートナーズによる買収合意など激震が相次ぎ、株価は低迷したままです。今回決算ではコスト削減の実行度合いとヘルスケア事業の再建が焦点となり、買収成立の行方も絡んでボラティリティの高い値動きが予想されます。前回決算(2025年第2四半期)の振り返り前回(2025年度第2四半期)は、売上高が386億ドルとなり、前年同期比で4.1%増加しました。一方、収益面では依然として課題が残り、調整後の1株あたり利益(EPS)は0.63ドルとなりました。この背景には、薬局部門における処方箋の取扱いが増えた一方で、美容品や季節商品といった小売販売の落ち込み、さらに関連会社VillageMDの事業価値の減損(約58億ドル)などの一時的なコスト増があります。結果として、フリーキャッシュフローも大きく赤字となり、WBAの経営課題が改めて浮き彫りになりました。決算発表後の主な動きとニュースWBAは前回の決算発表前から事業再編策がとられており、市場は期待と不安を交錯させながら現在も株価が推移しています。さらに3月には、大規模な店舗再編が発表されました。2025年中に米国内で新たに500店舗を閉鎖し、累計で1,200店規模を整理するという計画です。また、ヘルスケア事業の再編も急速に進めており、かつて成長を期待されたVillageMDについても一部店舗の整理や持分の売却検討が報じられました。最も大きなニュースは、3月下旬に明らかになったプライベートエクイティのシカモア・パートナーズによる買収提案です。WBAを最大237億ドル(1株あたり11.45ドル)で買収し、株式を非公開化するという基本合意が成立し、同社を巡る経営環境は大きく変化しています。今回決算(2025年第3四半期)の注目ポイント今回の決算で投資家が最も注目すべきポイントは、WBAが収益悪化をどこまで抑えられるかということです。前回好調だった薬局部門の売上高が今回も伸びを維持し、収益改善に貢献できるかが第一のポイントになります。また、WBAは1年間で10億ドル規模のコスト削減を掲げていますが、これが実際にどれほど効果を出しているのか、営業費用の削減が進んでいるのかについて、具体的な数字が求められます。さらに重要なのがキャッシュフローです。VillageMDなどの資産整理に伴う追加の減損費用や、米国のオピオイド問題関連の和解金支払いなどが再びキャッシュフローを圧迫する可能性があります。今回の決算ではこうした特別要因が再び利益を押し下げていないか、注意が必要でしょう。そしてもう一つの大きな焦点が、買収提案に関する動向です。買収に関する進捗状況が示されるか、正式な業績見通し(ガイダンス)が再び提示されるかが、株価の短期的な動きを左右する重要な要素になるでしょう。特に、現在の市場株価とシカモアが提示している買収価格との差が縮まるかどうかにも市場は注目しています。株価への影響と今後の見通しWBAの株価は現在、1月中旬以降から10%以上下落したまま低迷が続いています。配当停止や店舗閉鎖、事業再編による将来不安が重なり、買収期待で一時的に上昇したものの、その後は再び低調な動きを見せています。今回の決算発表前後では、市場参加者は株価が上下10%程度動く可能性を想定しています。コスト削減が具体的に成果を出し、キャッシュフロー改善の兆しが見えれば、短期的な反発(リリーフラリー)が起こる可能性があります。一方、減損損失の再発や買収の不透明感が続けば、株価の下押し圧力が強まる恐れもあります。個人投資家としては、この決算で薬局事業の回復やコスト削減策の進捗を確認するとともに、経営陣の買収プロセスに関する説明にも注目しておく必要があります。まとめと個人投資家としての対応WBAは現在、大胆な再編と買収による非公開化という二つの大きな変化の真っただ中にあります。今回の決算はその方向性や経営再建の成果を確かめる重要な局面です。特に収益回復が明確になれば、株価も底打ち感が出てくる可能性があります。しかし、経営の混乱や追加の減損リスクなど、マイナス面も決して軽視できません。このため、投資家の皆様は、決算発表をきっかけに予想される株価の大きな動きに備え、慎重に変化の方向性を分析しながら対応していくことをお勧めします。

【マイクロン・テクノロジー決算(2025年3Q)】HBM急伸の勢い継続か、巨額投資の影響も焦点に(Micron Technology)
本記事では、マイクロン・テクノロジー(MU)の2025年3月発表2025年度第2四半期決算を振り返り、6月に控える2025年度第3四半期決算の見どころを解説します。前四半期はAI向け高帯域幅メモリ(HBM)の急伸で大幅増益を達成し、会社側ガイダンスでも“過去最高売上”が示唆されています。一方で競合サムスンの追い上げや大型投資によるキャッシュフロー懸念もあり、株価は年初来50%超上昇後に神経質な値動きが続いています。前回(2025年第2四半期)決算のポイント前回決算(2Q)は売上高80.5億ドル(前年同期比38%増)と、業績が大幅に改善しました。利益面でも、非GAAPベースの1株利益(EPS)が1.56ドルと前年同期から約3.7倍となり、業績回復が鮮明となりました。特に、売上増加の背景には生成AI向け高帯域幅メモリ(HBM)需要の急速な拡大があります。データセンター向けDRAMの売上は四半期として過去最高を記録し、HBM関連だけで10億ドルを突破しました。こうした強い成長を背景に、会社側は2025年3Qについても「売上高88億ドル±2億ドル、EPSは1.57ドル±0.10ドル」と強気な見通しを示しました。一方、利益率の改善も注目すべき点で、純利益率は前年同期の14%から20%へと回復しました。これにより営業キャッシュフローも前年同期比で約3倍に増加するなど、好調さが目立つ決算でした。決算後の主な動きとニュース前回決算以降もマイクロンの事業環境には重要な動きがありました。その一つが、次世代HBM3Eメモリの量産を開始したことです。特にNVIDIA向けに供給を始めたことで、株価も一時的に上昇しました。さらに6月には、マイクロンが米国国内での設備投資計画を当初の想定から2000億ドル規模へと大幅に拡大することを発表しました。米国内のDRAM生産比率を40%まで引き上げることを目指し、競争力を長期的に高める狙いがあります。ただ、これほどの巨額な投資は財務上の負担が大きく、将来的なフリーキャッシュフロー(FCF)の圧迫が懸念されています。競合の動きも重要です。5月には韓国サムスン電子がHBM3Eの量産を開始し、主要顧客向け供給準備を整えていると報道されました。これにより競争激化や価格低下圧力が意識され、マイクロンの株価にもネガティブな影響がありました。また、Bloomberg Intelligenceは2033年までにHBM市場規模が今後大きく成長すると予測しており、長期的にはマイクロンにとって追い風となる材料です。アナリストは2025年通期のEPS予想を6.21ドルと前年の10倍近くになると見込んでおり、業績への期待は依然として非常に高い状態が続いています。今回決算で特に注目すべき点は?今回の2025年第3四半期決算ではいくつかのポイントに注目が集まっています。まず、市場の予測値と実績がどうなるかです。アナリストの売上予想は会社のガイダンスをやや下回る水準(84~86億ドル、EPS1.4~1.6ドル)にあり、市場の予想を上回る好決算(ビート&レイズ)であれば、株価にさらなる上昇の可能性があります。また、引き続きHBM関連の売上拡大のペースが焦点となります。前回四半期で急伸したHBMが今後どの程度まで成長を続けられるか、具体的な売上数字や経営陣のコメントが重要になります。特に会社はHBM売上について「年間ベースで数十億ドル規模」と見込んでいるため、この進捗が注目されます。次に、大型投資計画の影響です。米国への2,000億ドルの巨額設備投資は中長期的には市場競争力を高めますが、一方で短期的には財務面への負担増が懸念されます。今回決算では、投資に伴うキャッシュフローの見通しや財務戦略について、明確な説明が求められています。さらに、競合との価格競争状況や中国市場をめぐる地政学リスクも無視できません。特に、サムスンやSK HynixとのHBMのシェア争いが価格プレミアム維持に悪影響を及ぼす可能性があります。また米中関係の緊張がマイクロンのサプライチェーンに与える影響も市場の懸念材料として引き続き注意が必要です。株価への影響と個人投資家の対応ポイントマイクロン株は今年に入ってから既に約40%以上上昇し、6月中旬時点でPER約28倍まで買われています。これはAI関連銘柄としての注目が高まっているためですが、逆に言えば業績予想を少しでも下回ると大きく売られやすい水準でもあります。現在の市場環境では、決算発表当日のオプション市場が±7~10%程度の株価変動を想定していることから、結果次第で株価が大きく動く可能性が高いと見ておいた方が良いでしょう。今回の決算において個人投資家が特に注意すべきポイントは、HBM関連の売上高や利益率の推移、設備投資に伴う財務状況、そして次四半期の会社側ガイダンスの内容です。特にカンファレンスコールでの経営陣のコメントは、投資計画の資金調達方法や競争戦略について重要なヒントを与えてくれるでしょう。以上を踏まえ、短期的な株価変動を覚悟しつつ、中長期的な視点でマイクロンの成長ストーリーを冷静に分析していくことをお勧めします。

中東情勢が株価の重しに。FOMCと日銀会合の結果、金利差が意識され円安に|米国市場サマリー
先週は、イスラエル‐イラン紛争を巡るヘッドラインとFOMC後のタカ派スタンスが交錯し、方向感に欠ける一週間となりました。週明けは原油急落を追い風にハイテク株が買われ、NASDAQが+1.5%でスタートしましたが、翌日は戦線拡大懸念と弱い小売売上高で主要3指数がそろって約0.8%下落しました。FOMCは利上げを見送りつつ「関税で夏場にインフレが上振れし得る」と警戒を示し、株価の戻りを抑えました。週末金曜日はトリプルウィッチングでは出来高が跳ね上がったものの、ダウ+0.1%、S&P500-0.2%、NASDAQ-0.5%で動かず。結果、週間ではダウ横ばい、S&P500-0.2%、NASDAQ+0.2%と強弱が分かれ、原油・金利・地政学要因が投資家心理を揺さぶる展開でした。為替は、144円台後半で始まり、中東リスクで一時円買いとなったものの、FOMC据え置きや日米金利差拡大観測からドル買いが優勢となり、20日終値は146.10円でした。米2年債利回り上昇がドルを支え、Juneteenthの薄商いとトリプルウィッチングのフローも絡んで上値を試す展開となり、週間では約1.4円のドル高・円安となりました。金融政策の方向性乖離を背景に、円が安全資産として買われにくい構図が鮮明でした。米国株式市場:イスラエル・イラン紛争が株価の重しに、FOMCは金利を据え置き6月16日(月) 米国株式市場は反発し、ダウ工業株30種平均が317ドル高(+0.75%)、S&P500が+0.94%、NASDAQが+1.52%と主要3指数そろって上昇しました。イスラエルとイランの空爆による原油供給懸念が後退し、原油価格が下落したことが買い安心感を誘いました。セクターでは情報技術とコミュニケーションがけん引し、Advanced Micro Devicesが8.8%高、U.S. Steelが日本製鐵の買収承認を受けて5.1%高。一方、Sarepta Therapeuticsは遺伝子治療の2例目の死亡報告で42%急落しました。6月17日(火) 中東情勢の悪化が再び市場心理を冷やし、ダウは299ドル安(-0.70%)、S&P500は-0.84%、NASDAQは-0.91%で終了。原油高を背景にエネルギー株は上昇したものの、太陽光関連銘柄が米上院による税控除段階的廃止案で急落(Enphase Energy-24%、Sunrun-40%)。テクノロジー大手も軟調でTeslaが4%下落しました。米5月小売売上高が予想外の減少となり景気懸念も加わりました。6月18日(水) FOMCは政策金利を据え置きましたが、パウエル議長が「関税の影響で今夏はインフレが上振れし得る」と発言し、序盤の上げを相殺。ダウは-0.10%、S&P500はほぼ横ばい(-0.03%)、NASDAQは+0.13%と小動きで終えました。業種別ではITが堅調で、Stablecoin企業 Circle Internet が米上院の規制法案可決を受け33.8%高、Nucorは好調な利益見通しで3.3%高。エネルギー株は原油反落を受け軟調でした6月19日(木) Juneteenth National Independence Dayの祝日で市場休場6月20日(金) 週末を控え投資家がイスラエル‐イラン紛争の拡大リスクを警戒するなか、ダウは35ドル高(+0.08%)と小幅高となった一方、S&P500は-0.22%、NASDAQは-0.51%で3日続落。四半期末の「トリプルウィッチング」に伴う出来高急増も相場を不安定にしました。個別では、好決算と通期売上高見通し引き上げで Kroger が9.8%急伸、Accenture は新規受注減少を嫌気して6.9%下落。半導体・メガキャップ株は軟調で NVIDIA などが指数の重しとなりました。為替市場:日米金利の乖離が意識され、安全資産としての円逃避も進まず円安へ為替は米長期金利動向と中東情勢をにらみつつ、週を通じて円安基調が続きました。16日はイスラエル―イラン衝突への警戒感から一時円買いが入ったものの、米金利の底堅さが下支えし、終値は144.74円でした。17日は日本銀行が政策金利と国債買い入れ計画を据え置いたことが「慎重姿勢」と受け止められ、ドル買いが優勢となり145.28円で引けました。18日はFOMCが金利を据え置き、パウエル議長がインフレ上振れリスクに言及した一方、弱い米小売売上高が重しとなり、145円近辺でもみ合い、終値は145.12円でした。19日は米国のJuneteenth祝日で薄商いの中、中東リスクとタカ派的なFRB見通しを背景にドル高が続き、145.46円へ小幅続伸しました。20日は地政学リスクへの警戒による安全資産としてのドル需要と四半期末のポジション調整が重なり、日中高値146.23円を付けた後、終値は146.10円となりました。ドルは対円で3週間ぶりの高値を更新し、週間では約1.36円(+0.9%)のドル高・円安です。日銀とFRBの政策スタンスの乖離が改めて意識され、地政学リスク下でも円が「安全資産」として買われにくい構図が浮き彫りになった一週間でした。ブルーモの公式Xでは決算や指標の速報をお届けしているので、興味ある方はフォローしてみてください。https://x.com/Bloomo_invest
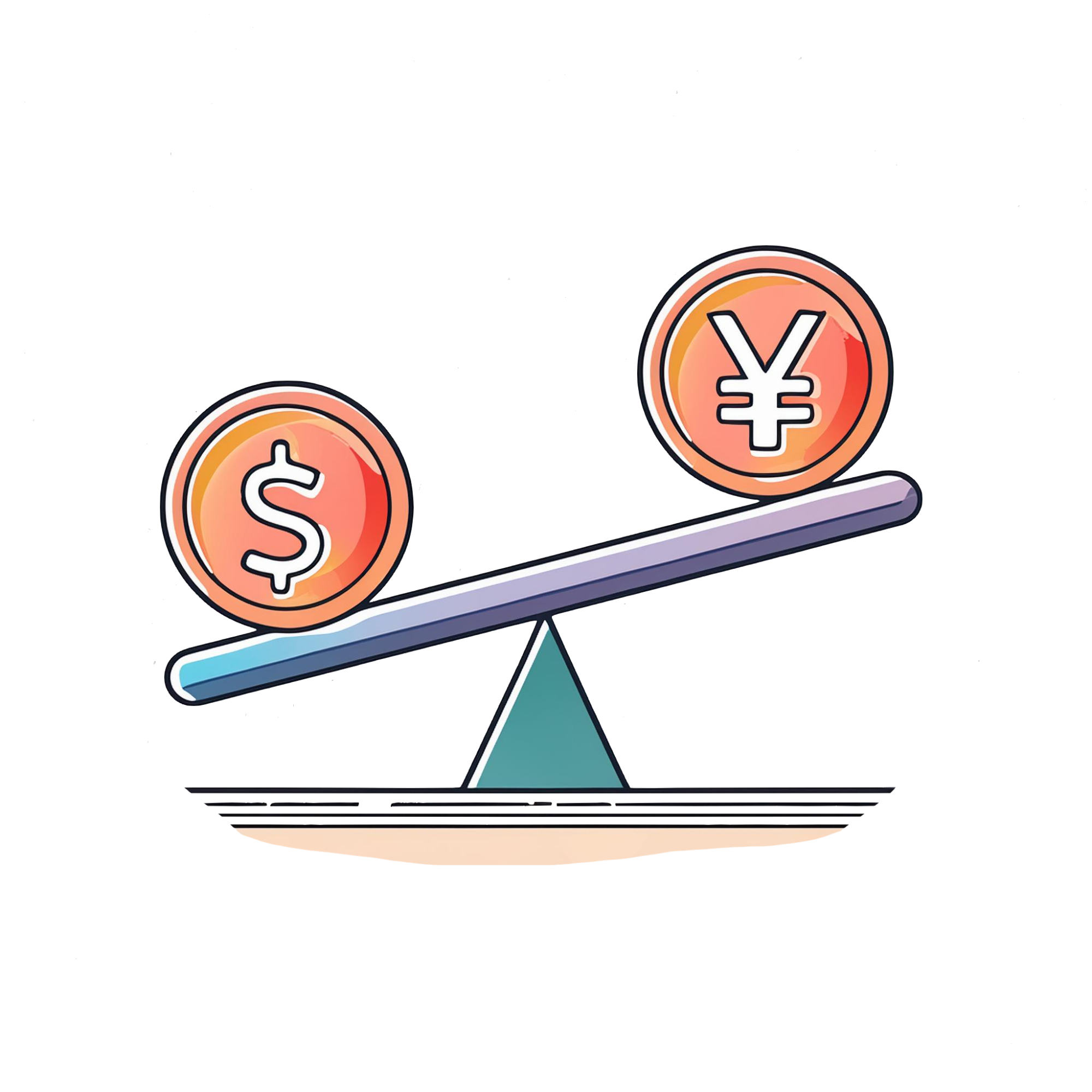
キャリートレードとは?日本の金利上昇がもたらす円キャリートレード解消リスク
本記事では、「キャリートレード」の基本的な仕組みを解説した上で、円キャリートレードの巻き戻しリスクと、日本の長期金利上昇が円キャリートレードに与える影響について掘り下げていきます。キャリートレードとは「キャリートレード」とは、金利の低い通貨で資金を調達し、高利回りの資産に投資することで、その利回り差から利益を得る投資手法です。例えば、円を借りて米国のハイテク株や新興国通貨建て債券といった相対的にリスクの高い資産に投資し、最終的に外貨を円に戻して元本を返済するという流れが挙げられます。為替レートが安定していれば、調達金利と投資先利回りの差による利益が期待できますが、為替変動や金融政策の転換によって損失を被るリスクもあります。なお、金融用語で「キャリー」とは、保有資産から継続的に得られる金利や収益のことを指します。なぜ「円」がキャリートレードの調達通貨として選ばれるのか円キャリートレードが本格的に広がったのは、1999年に日本でゼロ金利政策が導入されたことが契機でした。デフレと低成長が続いた日本では、日本銀行(日銀)がマイナス金利政策やイールドカーブ・コントロール(YCC)など、長期にわたり緩和的な金融政策を継続してきました。特に、2013年の量的・質的金融緩和以降は、米国の利上げ局面と円安の進行が重なり、円キャリートレードは活発化。円は「低コストで借りやすい通貨」として、国際金融市場での地位を確立しました。また、為替のボラティリティが比較的低いことも調達通貨としての魅力を高めています。2022~2023年にかけては、米連邦準備制度理事会(FRB)が政策金利を5%超に引き上げる一方、日銀はゼロ金利を維持。結果として金利差が拡大し、キャリートレードは一段と活性化しました。2025年6月時点、日銀の短期金利は0.5%にとどまっており、円キャリートレードの環境は依然として存在しています。円キャリートレードの巻き戻しとは「巻き戻し」とは、キャリートレードによって積み上げられたポジションが、何らかの要因で一斉に解消される動きを指します。これは、金融政策の転換や市場のボラティリティ上昇などをきっかけに発生しやすく、投資家はリスク資産の売却と同時に、調達通貨である円の買い戻しに動きます。レバレッジをかけた取引が多いため、巻き戻しは急激に進行し、株式・債券市場を含む幅広い資産価格の下落を引き起こすことがあります。2024年以降、日銀はマイナス金利とYCCを終了し、政策正常化に舵を切りました。利上げは一時停止中とはいえ、日本国債の利回り上昇観測は資金調達コストの上昇を意味するため、円を借りてリスク資産に投資するメリットが低下しつつあります。昨年8月に円キャリートレードの巻き戻しが進み、急激な円高が発生したことも記憶に新しいところです。日本の長期金利上昇がキャリートレードに与える影響現在、日本の長期金利は過去最高水準付近で推移しており、キャリートレード解消への警戒感が市場で高まっています。この状況に対し、ソシエテ・ジェネラルのアルバート・エドワーズ氏は最近の顧客向けレポートで、日本国債の利回り急上昇により、米国の株式・国債市場の支えとなってきた日本の資金が急激に流出する可能性を指摘。これにより、米国のハイテク株など、円キャリートレードの恩恵を受けてきた資産が下落するリスクがあるとしています。一方、円キャリートレードの巻き戻しが昨年8月のように急激に進むとの見方には慎重論もあります。資産運用会社アムンディのガイ・ステア氏は、「大きなキャリーポジションは通常、為替トレンドが強いとき、または為替ボラティリティが非常に低いとき、そして短期金利差が大きいときに積み上がる」と述べ、短期金利差が縮小している現在、昨年よりも円の空売りポジションが減少していると指摘しています。アムンディのデータによると、2024年第2四半期には米日2年国債の利回り差は4.5%だったのが、直近では3.2%まで縮小し、キャリートレードの収益性を低下させています。日本の金融政策が大きな転換点を迎える中、円キャリートレードを取り巻く環境も徐々に変化しつつあります。特に、円金利の上昇は国際的な資金フローや米国市場のリスク資産価格にも影響を及ぼす可能性がある点で、投資家にとって重要な視点となります。

イーロン・マスクCEOとトランプ大統領の関係が与えるテスラ株への影響とは
イーロン・マスク氏とドナルド・トランプ大統領の関係は、米国株市場における政治リスクの典型例として浮上しています。特にテスラ株は、両者の確執によって大きく振れ、単なる企業業績だけでなく、政権との関係性や政策の方向性といった外部要因に大きく左右される銘柄となっています。 両者の関係の推移(2016~2025年)2016年、マスク氏はトランプ氏の大統領当選を受けて政権の経済諮問委員に就任。当初は協調姿勢を見せましたが、2017年のパリ協定離脱に抗議して辞任し、気候政策を巡る立場の違いが浮き彫りになりました。その後2020年には、コロナ禍によるカリフォルニア州の工場閉鎖命令に反発したマスク氏を、トランプ氏がSNSで支持。再び接近の兆しを見せたものの、2022年にはマスク氏がフロリダ州知事ロン・デサンティス氏の支持を示唆すると、トランプ氏は激しく非難。以降、両者の関係は冷却化しました。2024年の大統領選ではマスク氏が最終的にトランプ陣営に巨額献金を行い、選挙戦を側面支援。トランプ氏が再選を果たすと、2025年にはホワイトハウス内にマスク氏主導の政府改革タスクフォースが設置され、一時的な蜜月が復活します。マスク氏は行政の無駄を削減する「政府効率化」プロジェクトの中心人物として政権内で重用され、SpaceXの宇宙通信インフラやAI開発推進といった分野でも協業が見込まれていました。しかし、2025年春に提出された大型減税・歳出法案「Big Beautiful Bill」にEV補助金の撤廃が含まれていたことをきっかけに、両者の関係は急速に悪化。マスク氏は法案を「財政規律を無視し、EV産業を冷遇するもの」と批判。トランプ氏は「マスクは補助金目当て」と反発し、テスラやSpaceXに対する連邦契約・補助金の見直しを示唆しました。この対立は短期間で一気に激化し、マスク氏はSNSで「トランプ大統領は弾劾されるべき」と投稿。さらに、政権がテスラ車の認証や政府調達の面で冷遇している可能性に言及するなど、直接的な企業運営への干渉を警戒する姿勢を鮮明にしました。トランプ氏もマスク氏を「恩知らず」と非難し、Starlinkや宇宙インフラ事業への契約停止にまで言及するなど、対立は制御不能なレベルにまで達しました。2025年6月のテスラ株急落(14%下落)の背景2025年6月5日、マスク氏とトランプ氏の確執が鮮明になる中、テスラ株は1日で14.2%下落。時価総額ベースでは約1,520億ドルが失われました。これはテスラにとって過去最大級の下落であり、政治的発言が株価に直撃する構図が改めて浮き彫りとなりました。背景には、(1)EV補助金撤廃の具体化、(2)政府契約打ち切りリスクの高まり、(3)ホワイトハウスとの関係断絶による将来的不確実性、といった複数の懸念が市場に波及したことがあります。投資家の売買動向ヘッジファンド:トランプ政権との関係悪化を“売り材料”と見なし、テスラ株の空売りを急増。6月5日の1日で約40億ドルのショート利益を得たとされます。アクティブ運用機関:ARK Investなどがテスラ株の一部を売却。政権リスクと収益鈍化の両面からポジションを減らす動きが見られました。個人投資家:下落を押し目と見て買い向かう層も多く、リテールは同日ネットで2億ドル以上の買い越し。レバレッジ型ETF(TSLLなど)への資金流入も増加しました。オプション市場:プットオプションの建玉が過去最高水準に膨らみ、ヘッジ需要の高まりと市場の警戒感が顕在化しました。市場では、「政治的な期待が剥落したことで、テスラ株のバリュエーションが現実に引き戻された」との評価が支配的となりました。テスラに影響を与える3つの構造リスク1. 政治リスクトランプ政権が政敵への報復的姿勢を見せた場合、テスラやマスク氏が関与するSpaceX・Starlinkなどの連邦契約が打ち切られる可能性があります。また、NHTSA(運輸省)による自動運転認可や安全審査にも政治的圧力がかかる恐れがあります。こうした契約の打ち切りは、マスク氏の資産構成にも影響を与え、テスラ株の売却圧力につながる懸念もあります。2. 政策リスクEV購入補助金の廃止、EVユーザーへの追加課税、州独自のZEV(ゼロエミッション車)義務撤廃などが含まれます。特に補助金撤廃はJPモルガンの試算で年間利益に最大12億ドルの影響とされ、テスラの利益構造に大きな圧力をかけます。また、中国製電池・パーツへの関税引き上げや米中対立の再燃により、テスラのコスト構造が不安定になる可能性もあります。上海工場に依存するグローバル供給体制が不安定化すれば、生産計画や価格戦略に影響を及ぼしかねません。3. ブランドリスクマスク氏の政治的発言やSNS上の言動が、テスラのブランドイメージを傷つけるリスクがあります。民主党系リベラル層はマスク氏の右傾化に反発し、保守層はトランプ批判に反発。結果的に「両サイドからの離反」が起こる可能性が指摘されており、顧客基盤の縮小に直結する懸念があります。また、環境志向の高い層や若年層がSNS上で「反マスク」的ムーブメントを強めることにより、購買意欲の低下やリセールバリューの下落といった間接的影響が出る可能性もあります。今後3〜6ヶ月の注目イベントと株価への影響予想直近の急落劇を受け、今後数ヶ月間のテスラ株は引き続き政局や政策ニュースに敏感な展開が予想されます。個人投資家が適切な判断を下せるよう、この先3〜6ヶ月の主要なイベント・ニュースフローと、そのテスラ株への潜在的影響を整理します。以下に、政策スケジュールや外部環境の主なポイントをまとめました。EV税額控除の撤廃法案の行方 2025年夏〜秋(議会審議)7,500ドルの税優遇廃止が成立すれば需要減退・利益圧迫要因となり、年間12億ドル規模の減益試算となります。成立阻止ならポジティブ材料になります。米中通商協議と関税措置 2025年後半(首脳会談模索)トランプ政権による対中関税・輸出規制の強化リスクとなります。車両関税や電池素材の供給制限が生じればコスト増で株価下押し要因となるでしょう。逆に首脳会談で摩擦緩和なら調達コスト改善に寄与し好材料になります。実際6月には鉱物紛争が一時懸念されました。自動運転規制の動向 2025年内(FSD調査結果等)NHTSAによる「完全自動運転(FSD)」機能の調査や、運輸省によるロボタクシー車両の認可動向に注視します。政権が非協力的なら認可遅延・追加規制の可能性もあります。ロボタクシー実証実験(2025年6月予定)への政府対応も焦点となります。前向きな規制緩和なら株価の追い風になります。政治・政策を巡る不透明感はテスラの評価に強く影響を与え続けます。両者の関係改善の兆しが見えれば、再評価の機運が高まる一方、対立が長期化すればバリュエーションの修正圧力が続くと見られます。政策リスクと感情的対立が株式市場に波及する構図は、今後の米国株全体にも示唆を与える重要なテーマといえるでしょう。
.png)
【クローガー決算(2025年1Q)】デジタル戦略と新経営体制の行方(Kroger)
本記事では、クローガー(KR)の2025年3月発表2024年度第4四半期決算を振り返り、6月に控える2025年度第1四半期決算の見どころを解説します。前四半期はデジタル強化とコスト抑制で底堅さを示した一方、経営トップ交代やアルバートソンズとの統合断念など構造的な変化が相次ぎました。市場は同社が「日常必需品+デジタル会員基盤」というハイブリッド戦略を維持しつつ、物価動向と競争激化のはざまで利益成長を確保できるかを注視しています。前回(2024年度第4四半期)決算の振り返りクローガーは2025年3月6日に2024年度第4四半期(2025年2月1日締め)の決算を発表しました。売上高は343億ドルとなり前年同期比で減少しましたが、燃料や売却済み事業を除く既存店売上高は前年同期比2.4%増加し、安定的な業績を示しました。また、調整後の1株当たり利益(EPS)は市場予想を上回る1.14ドルを記録し、利益水準も堅調でした。特に評価されたのは利益率の改善です。粗利益率は在庫管理の改善やコスト削減の取り組みにより22.7%まで高まりました。さらに、デジタル売上高が前年同期比11%増加し、年間デジタル売上が130億ドルに達したことも、デジタル戦略の成功を印象付けました。クローガーはまた、通期業績見通しを「燃料を除く既存店売上高2〜3%増、調整後EPSは4.60〜4.80ドル」と発表しました。これに加え、自社株買いを総額75億ドルの枠内で加速的に進めることも明らかにし、株主還元策への積極姿勢を示しました。前回決算以降の主なニュース決算後に最も注目されたニュースは経営陣の交代でした。3月初旬、長年CEOを務めていたロドニー・マクマレン氏が個人的な行動が倫理規定に反したとして辞任を余儀なくされました。暫定的な後任として、元ステイプルズCEOのロン・サージェント氏が取締役会長兼CEOに就任しました。一時的な不安感が市場に広がったものの、株価への影響は限定的で、会社のガバナンスへの信頼は概ね維持されています。また、大きな戦略転換として、総額246億ドル規模で進められていた同業大手アルバートソンズの買収がFTC(連邦取引委員会)や州裁判所による差し止めにより頓挫しました。さらにアルバートソンズ側からクローガーが訴えられる展開になっています。この合併が実現しなかったことで期待されていたシナジー効果は失われましたが、財務的な柔軟性が保たれたと見る投資家もいます。今回(2025年6月)決算の注目ポイント今回の決算で投資家が注目すべき主なポイントは三つあります。一つ目は燃料を除く既存店売上高が引き続きガイダンスの上限近く(3%増)を達成できるかどうかです。食品業界では競争激化が続いており、生鮮品の価格競争が利益率を圧迫する可能性もあります。販売数量の維持・拡大がどの程度可能かが焦点です。二つ目はデジタル販売の成長持続性です。前四半期のデジタル売上は11%増と好調でしたが、宅配や店頭受け取りを中心としたデジタルサービス「Boost」の拡大が粗利益率改善に引き続き寄与するか注視されます。三つ目はコスト管理の徹底と収益性維持です。特に人件費の上昇が続くなかで、販管費をどこまで抑制できるかが重要です。さらに買収の中止に伴う訴訟費用や関連コストがどの程度影響するかも気になります。株価の動向と投資家への示唆2025年6月10日時点のクローガーの株価は65.37ドルで、4月22日の史上最高値72.63ドルからは約10%下落した水準にあります。現在の株価指標を見ると、株価収益率(PER)が約15.9倍、株価純資産倍率(PBR)は約1.6倍で、食品小売業界としては妥当な水準と評価されています。直近では、CEO交代や買収断念の影響による株価調整局面から徐々に回復しています。今回の決算が好調な内容であれば、過去の高値圏への再接近も十分考えられます。ただし、FTCとの訴訟問題や今後の訴訟費用、物価動向などの外的要因が短期的な不安要素として残っており、投資判断には慎重な姿勢が求められます。まとめと個人投資家への提言今回のクローガー決算では、デジタル販売の継続的な拡大と既存店売上高の堅調な推移、経営陣交代後のコスト管理力が焦点となります。訴訟関連費用や外部環境の影響を冷静に見極める必要はありますが、安定した財務基盤や株主還元方針に対する市場の評価は高く、中長期的な視点から投資を検討する価値は十分あるでしょう。投資家は今回の決算発表を受けて、株価の一時的な変動に惑わされず、堅実に業績トレンドを確認しつつ、投資戦略を慎重かつ柔軟に構築していくことが望ましいでしょう。