ライブラリー
.png)
【デル・テクノロジーズ決算(2026年1Q)】AIサーバーの収益化とPC市場回復の行方に注目(Dell Technologies)
本記事では、デル・テクノロジーズ(DELL)の2025年2月発表2025年度第4四半期決算を振り返り、5月に控える2026年度第1四半期決算の見どころを解説します。今回の決算は、AIサーバー需要の拡大による成長力と、低迷が続くPC市場の回復状況を見極める重要な節目となります。本稿では、前回決算の概要、その後の主要な動向、そして今回の決算で個人投資家が特に注目すべきポイントを整理し、株価への影響について考察します。前回決算の振り返り2025年2月に発表された2025年度第4四半期(2024年11月〜2025年1月)の決算では、売上高が239億ドルとなり、前年同期比で7%増加しました。特に注目されたのは、インフラストラクチャ事業(ISG)の好調さで、売上は114億ドルと前年同期から22%の大幅増加を達成しました。中でもサーバーとネットワーキング分野の伸びが顕著で、AI関連の受注が大幅に伸びたことが要因でした。一方でPC事業(CSG)は法人向けこそ堅調でしたが、個人消費者向けが弱含んだことで、全体としては1%の小幅な増収にとどまりました。また、調整後1株利益(EPS)は2.68ドルを記録し、市場予想を上回るとともに過去最高を更新しました。年間では売上高が955億ドル、営業キャッシュフローは45億ドルを確保しました。自社株買いについても50億ドル規模で実施され、資本還元の姿勢を積極的に示しました。2月以降の主な動向前回決算以降の大きな話題は、デルがAI市場にさらに積極的に踏み込んだことです。5月初旬に開催されたイベント「Dell Technologies World 2025」では、NVIDIAと協力して新たなAI基盤である「Dell AI Factory」を発表しました。これは企業が効率よくAIを導入し、運用できるようにする取り組みで、デルのAI市場に対する本気度が明確に示されました。さらに、新型の「PowerEdge XE9シリーズ」を投入し、NVIDIAの最新GPUを最大限搭載することで、AIモデルのトレーニング速度を従来の4倍に引き上げることに成功しました。これに加えてAMDやクアルコムとの協力も進んでおり、デルは多様なAI製品ラインナップを拡充しています。証券アナリストの評価も高まっています。例えばモルガン・スタンレーは、AI関連サーバー市場が年間で約200億ドル規模の事業機会となるとの見通しから、デルの目標株価を従来の89ドルから126ドルへと大幅に引き上げました。今回決算で注目するポイント今回の決算発表ではまず、AIサーバー関連の受注残高が実際にどの程度売上として計上されているかに注目です。前回発表された受注残は約90億ドルでしたが、これが順調に売上として反映されているかどうかが成長継続の指標となります。また、PC市場の動向も重要なポイントです。法人向け需要は底堅いものの、個人消費者向けPC市場の回復が進んでいるかどうかが注目されます。特に、新たに投入されるAI機能を搭載したノートPCがどの程度売上に寄与し、平均販売単価の改善に役立っているかを確認する必要があります。さらに、利益率とキャッシュフローの推移にも注意が必要です。新製品の初期投資コストが発生している中で、前回同様の高い営業利益率(9%前後)が維持されているか、フリーキャッシュフローが年間目標の半分程度を順調に達成しているかを確認することが、投資家の信頼を得る重要な要素となります。最後に、資本還元策の進展や、通期の売上見通しに対する経営陣のガイダンスにも注目が必要です。特に、自社株買いを継続的に実施する余力が示されるか、そして年間ガイダンスを引き上げるのか、それとも慎重な姿勢を維持するのかで株価の動きが大きく左右される可能性があります。株価動向と投資家への示唆2025年5月22日時点のデルの株価は114ドル台で推移しており、年初来の上昇率は約80%と、市場平均を大幅に上回っています。AIインフラ需要を反映した成長期待が株価を押し上げている一方で、株価売上高倍率(PSR)は約1.2倍程度と、競合企業に比べ割安感も残ります。AI関連の受注が順調に売上に転換され、利益率が維持されれば、株価はさらに高値を目指す展開が期待できます。しかし、AI関連サーバーの受注消化が想定を下回る場合や、PC市場の回復が遅れる場合には、短期的な株価調整リスクも意識する必要があります。その際は、100ドル付近までの調整も考えられますので、投資家は決算後の経営陣の説明を慎重に確認する必要があります。デル・テクノロジーズは現在、AI分野への積極的な投資と既存事業の回復という2つの重要課題に取り組んでいます。個人投資家の皆さまにとっては、AIサーバーの売上寄与度、PC市場の回復状況、キャッシュフローや利益率の動向を慎重に確認し、ご自身の投資戦略に照らして適切な判断を下すことが大切です。
.png)
【シノプシス決算(2025年2Q)】AI需要取り込みと大型買収の進展が株価を左右へ(Synopsys)
本記事では、シノプシス(SNPS)の2025年2月発表2025年度第1四半期決算を振り返り、5月に控える2025年度第2四半期決算の見どころを解説します。個人投資家にとって、米半導体設計ソフトウェア大手のシノプシスの今回の決算は、同社がAI関連需要を取り込みながら、進行中の大型買収を円滑に進められるかどうかを見極める重要な機会となります。本稿では前回決算のポイントとその後の主なニュースを踏まえ、今回決算の注目すべき要素を整理し、株価への影響を考察します。前回決算(2025年度第1四半期)の振り返りシノプシスが2月に発表した2025年度第1四半期決算は、売上高が14億6,000万ドルで、前年同期と比べ約4%の減収となりました。ただし、調整後EPS(一株あたり利益)は3.12ドルを記録し、市場予想を上回る結果でした。この背景には、次世代AI向けの半導体設計案件が順調に拡大していることが挙げられます。特に注目されたのは、経営陣が示した第2四半期の見通しでした。次世代AIサーバー向けチップ設計などの受注が想定以上に好調であるとして、第2四半期の売上予測を15億9,000万~16億2,000万ドルに引き上げました。ただし、中国市場向けライセンスの伸びが鈍化している影響で、通期売上高予想は67億5,000万~68億ドルと慎重な姿勢を維持しました。この結果を受け、株価は決算発表後に約2%の上昇に留まりました。前回決算以降の主な動向第1四半期決算以降、シノプシスは積極的にAI分野での競争力強化を図っています。3月中旬にはNVIDIAとの協業を拡大し、設計プロセスを従来比で最大30倍高速化できるAI対応の新フローを発表しました。これにより、半導体設計の効率化と高付加価値化が一層進むことが期待されます。また、同社独自のAIベースの設計支援技術である「AgentEngineer」構想を打ち出しました。これにより、回路検証プロセスをAIエージェントが補完し、設計人員を増やすことなく開発期間の短縮を実現するとしています。さらに、4月には世界最大手の半導体受託製造企業TSMCの最先端プロセス技術向けEDA(電子設計自動化)フローの認証を取得し、微細化が進む半導体製造への対応力も強化しました。もう一つの大きな話題は、約350億ドル規模のAnsys買収の進展です。英国の競争当局であるCMAが3月に第一段階の審査を条件付きで通過させたことを皮切りに、日本やトルコなど複数の国の当局からも続々と承認を得ています。シノプシスの経営陣は、2025年上半期中に買収を完了できるとの見通しを示しています。今回決算(2025年度第2四半期)の注目ポイント今回の決算において個人投資家がまず注目したいのは、AI関連ライセンスの成長率です。NVIDIAやTSMCといった大手企業との協業を通じて、次世代AIチップ設計向けのライセンス販売が増加しているとされます。この部門の成長率が前年を上回る水準を維持できるかどうかが、成長持続性を占ううえで重要になります。次に、Ansys買収に関連する費用を吸収した上での営業利益率の推移です。第1四半期の非GAAPベースの営業利益率は32%程度でしたが、大型買収に伴う追加コストが重なっても30%以上を確保できるかどうかが焦点です。コスト管理が上手くいけば、投資家の間で収益力に対する信頼感が高まるでしょう。さらに、中国市場への依存度が下がる中で、代替となる米国や台湾市場の売上拡大が確認されるかどうかにも注目です。地域別売上の動向を慎重に確認することが、今後のリスク評価に役立つはずです。株価への影響と投資家への示唆5月下旬時点のシノプシスの株価は約503ドル前後で、年初来で約18%上昇しており、市場全体を上回るパフォーマンスを示しています。足元の株価売上高倍率(PSR)は約11倍と、過去平均をやや上回る水準にありますが、AI関連需要の強さと買収の進展が明確に確認されれば、さらなる株価の上昇余地があります。逆に、営業利益率の低下や中国市場の影響が想定以上に大きければ、短期的な調整リスクもあり得るでしょう。個人投資家にとっては、決算発表後の経営陣のガイダンスやカンファレンスコールで示されるAnsys買収スケジュール、AI製品の導入状況、地域別売上見通しなどを詳しくチェックし、中期的な投資判断に役立てることが重要です。シノプシスは半導体設計市場において独自のポジションを確立しつつあり、AI関連の需要拡大やAnsysとの統合シナジーなどの材料もありますが、同時に大規模な買収に伴うリスクも伴います。投資家は慎重に情報を精査し、冷静な判断を行うよう心掛けてください。
.png)
【ヒューレット・パッカード決算(2025年2Q)】AI対応PCと印刷事業の収益改善が株価の鍵を握る(HP)
本記事では、ヒューレット・パッカード(HPQ)の2025年2月発表2025年度第1四半期決算を振り返り、5月に控える2025会計年度第2四半期決算の見どころを解説します。米国の大手テクノロジー企業、ヒューレット・パッカードは、2025年5月28日(米国時間)に2025年度第2四半期(2〜4月期)の決算発表を予定しています。今回の決算は、個人投資家にとって同社の今後の成長性や収益力を測る重要な機会となります。ここでは前回決算の振り返り、以降の主要なニュース、そして今回の決算で確認すべき注目点を整理し、株価への影響を分析していきます。前回(2025年度第1四半期)決算の振り返りヒューレット・パッカードは、2025年2月27日に第1四半期(2024年11月〜2025年1月期)の決算を発表しました。売上高は135億ドルで前年同期比2.4%の増収となり、久々のプラス成長を示しました。特にパーソナルシステムズ部門(PC事業)が好調で、法人向けモデルの販売単価上昇を背景に部門売上は前年同期比で3%増加し、営業利益率も6.6%に改善しました。一方、印刷事業は消耗品需要の低迷などから売上が前年比で9%減少し、営業利益率も16%まで低下しました。しかし、全社的な調整後1株利益(EPS)は0.81ドルとなり、市場予想をわずかに上回る内容でした。同社経営陣は、通期のフリーキャッシュフロー目標を40億ドル付近に据え置き、年間5%超の自社株買いを継続すると表明しました。ただし、第2四半期のEPSガイダンスを0.75〜0.85ドルと市場予想の0.86ドルより控えめに設定したことから、決算後の株価はやや下落する場面もありました。2月以降の主なニュースと動向決算発表後のヒューレット・パッカードは、新たな製品戦略や事業構造改革を進めています。3月の世界的な展示会「CES 2025」において、同社はAI機能を搭載した新型PCを発表しました。このAI対応PCは、インテルの最新プロセッサやNVIDIA製GPUを搭載し、端末内で小規模なAIモデルを稼働させ、ユーザーの利便性とセキュリティを向上させることが特徴です。同社は、この新製品を通じて法人顧客の買い替え需要を喚起し、市場シェア拡大を目指しています。また、構造改革として新たに1,000〜2,000名規模の人員削減を実施し、年間約3億ドルのコスト削減を図ることも発表しました。さらに、環境問題への取り組みとして、欧州市場を中心にリサイクル材を利用したインクカートリッジの割合を2026年までに30%に引き上げるという目標を掲げ、環境配慮型製品の拡充も進めています。こうした取り組みは、今後の競争力向上とコスト削減効果が期待されるため、市場でも一定の評価を得ています。今回決算(2025年度第2四半期)の注目ポイント今回の決算で個人投資家が注目すべき最初のポイントは、パーソナルシステムズ部門(PC事業)におけるAI対応PCの初期の販売状況です。特に、法人向けモデルの平均販売価格の上昇やサービス契約の付帯率が順調に伸びているかが重要です。この数値が良好であれば、同社のAIを活用した付加価値戦略が市場に評価され、株価の上昇材料となる可能性があります。2つ目の注目点は、印刷事業の利益率回復です。前回は16%まで低下した営業利益率が、価格改定やコスト削減施策によって改善しているかが焦点となります。印刷事業は安定的なキャッシュフロー源として重要な役割を担っているため、利益率が17%以上に回復していれば、通期目標達成への期待感が高まります。最後の注目点は、フリーキャッシュフローの進捗と自社株買いの状況です。同社は通期で約40億ドルのフリーキャッシュフローを目指していますが、上半期の実績がこの目標の半分以上を確保できているかが確認ポイントです。キャッシュフローが順調であれば、自社株買いのペースを維持もしくは加速することが可能であり、株価の下支え要因となります。株価への影響と投資家への示唆5月22日時点でのヒューレット・パッカードの株価は34.5ドル前後で推移しています。株価水準は過去の平均と比較して割安な水準にあり、今回の決算がポジティブであれば、直近高値の38ドル台への上昇が見込まれます。一方、PCや印刷事業で予想を下回る結果が示された場合、株価は30ドル前後まで調整されるリスクもあります。個人投資家としては、AI対応PCの販売状況、印刷事業の利益率改善、キャッシュフローの進捗といった具体的な指標を重視することが重要です。これらの数値を丁寧に確認し、投資判断に役立てることで、短期的な株価動向に惑わされず、冷静な判断が可能となるでしょう。ヒューレット・パッカードは、成熟市場においてもAI活用などの付加価値を高める戦略で競争力を維持しようとしています。今回の決算発表は、その成果を具体的に評価する絶好の機会です。ぜひ、今回の記事を参考に、ご自身の投資方針に合わせて判断を進めてください。
.png)
【セールスフォース決算(2026年1Q)】生成AI戦略の進捗と利益率維持が株価の鍵(Salesforce)
本記事では、セールスフォース(CRM)の2025年2月発表2025年度第4四半期決算を振り返り、5月に控える2026会計年度第1四半期決算の見どころを解説します。今回の決算発表は、同社のAI戦略の進捗と収益性の持続性を評価する重要な機会となります。前回の決算では、売上高、営業利益率、キャッシュフローで過去最高を更新しましたが、生成AIへの投資や構造改革によるコスト増加が課題となっています。今回の決算では、生成AI関連製品の初期売上、利益率の維持、拡大した自社株買い枠の進捗が注目されます。前回決算のハイライト2025年2月26日に発表された2025会計年度第4四半期(2024年11月〜2025年1月)の決算では、売上高が100億ドル(前年同期比8%増)、調整後EPSが2.78ドルと市場予想を上回りました。営業キャッシュフローは131億ドルで前年同期比28%増加し、フリーキャッシュフローは124億ドルで31%増となりました。また、Data CloudおよびAI関連の年間経常収益(ARR)は9億ドルに達し、前年同期比で120%増加しました。Agentforceは、リリースから90日間で3,000件以上の有料契約を獲得し、企業のAI導入を加速させています。以降の主要な動向前四半期以降、SalesforceはAI戦略をさらに強化しています。Agentforceの導入が進み、企業のデジタル変革を支援しています。また、Data Cloudの利用が拡大し、企業のデータ活用を促進しています。これらの取り組みにより、SalesforceはAIとデータの統合による新たな価値提供を目指しています。今回決算の注目ポイント生成AI製品の立ち上がりAgentforceの導入状況とData Cloudの収益貢献度が注目されます。これらの製品が売上成長にどの程度寄与するかが、今後の成長戦略の鍵となります。利益率とコスト構造AI関連投資や構造改革によるコスト増加が利益率に与える影響が注目されます。前四半期の非GAAP営業利益率33%を維持できるかが、収益性の持続性を評価する上で重要です。株主還元と現金創出力拡大した自社株買い枠の進捗と、キャッシュフローの成長が注目されます。これらの要素が株主価値の向上にどのように寄与するかが、投資家の関心を集めています。株価動向と投資家への示唆2025年5月22日時点でSalesforceの株価は283.42ドルと年初来で約18.2%下落しており、S&P 500指数(約-0.7%)を大きく下回るパフォーマンスとなっています。また、現在の株価水準は過去10年の株価売上高倍率(PSR)のレンジ上限付近で推移しているため、決算内容次第ではバリュエーションが調整される可能性もあります。ガイダンスの据え置きや利益率低下が示されると、260ドル前後まで調整が進む可能性もあるため、注意が必要です。ただ、アナリストの多くはAIを中心とした長期的な収益成長に期待しており、今後の製品戦略がうまく展開されれば株価が再評価される余地も大きいとみています。売上成長が加速し、高い利益率を維持しつつ株主還元策が拡充されることが確認されれば、短期的にも株価が再び320ドルを目指す展開になる可能性が高まります。まとめSalesforceは、AIとデータの統合による新たな価値提供を目指し、生成AI製品の導入やData Cloudの拡大に注力しています。今回の決算では、これらの取り組みが業績にどのように反映されるかが注目されます。個人投資家は、生成AI製品の売上寄与度、営業利益率のトレンド、自社株買いの進捗といった指標を注視し、今後の投資判断に活用することが重要です。

【オクタ決算(2026年1Q)】AI投資の効果と成長持続力が株価浮上の分岐点に(Okta)
本記事では、オクタ(OKTA)の2025年3月発表第4四半期決算を振り返り、5月に控える2026会計年度第1四半期決算の見どころを解説します。2025年5月27日(米国時間)に予定されているオクタの2026会計年度第1四半期決算は、同社のAI戦略と収益性の持続性を評価する重要な機会となります。前回の決算では、売上高が6億8,200万ドル、調整後EPSが0.78ドルと市場予想を上回り、株価は急伸しました。しかし、通期ガイダンスの据え置きにより、投資家の間には慎重な見方も残っています。本稿では、前回決算の要点、以降の主要な動向、そして今回の決算で注目すべきポイントを整理し、株価への影響を考察します。前回決算のハイライト2025年3月に発表された第4四半期決算では、売上高が前年同期比13%増の6億8,200万ドル、調整後EPSが0.78ドルと、いずれも市場予想を上回る結果となりました。特に、サブスクリプション収益が6億7,000万ドルと全体の大部分を占め、前年同期比13%の成長を示しました。残存パフォーマンス義務(RPO)は42億1,500万ドルで前年同期比25%増、12カ月以内に計上されるcRPOも15%増と、将来の収益見通しも堅調でした。調整後営業利益率は17%に改善し、EPSは0.78ドルに到達しました。これらの好調な業績を受けて、発表直後に株価は19%上昇しました。以降の主要な動向第4四半期決算以降、オクタはAI時代に対応した製品戦略を加速させています。4月には、AIエージェントやAPIキーなどの非人間アイデンティティを可視化・制御する新たなプラットフォーム機能を発表し、企業が人間と同様にこれらのアイデンティティを管理できるようにする取り組みを強化しました。また、開発者向けには「Auth for GenAI」を公開し、生成AIアプリケーションにネイティブで認証・認可を組み込むことが可能となりました。これらの新機能は、AIエージェントのセキュリティ強化と企業のゼロトラスト戦略の推進に寄与すると期待されています。今回決算の注目ポイントRPOとcRPOの成長率アナリストの予想では、第1四半期の売上高は6億7,800万〜6億8,000万ドル、調整後EPSは0.78〜0.80ドルと見込まれています。特に注目されるのは、RPOとcRPOの成長率です。前四半期のRPOは42億1,500万ドル、cRPOは15%増でしたが、今回も同様の成長を維持できるかが焦点となります。AI関連投資と営業利益率AIエージェントや非人間アイデンティティ管理に関する新製品の投入により、研究開発費の増加が予想されます。その中で、前四半期に達成した17%の営業利益率を維持できるかが、収益性の持続性を評価する上で重要です。通期ガイダンスの見直し現在の通期売上見通しは28億5,000万〜28億6,000万ドルとされていますが、新製品の市場での反応や受注状況によっては、ガイダンスの上方修正があるかもしれません。反対に、据え置きや慎重なコメントが続けば、株価に対する圧力となる可能性もあります。株価動向と評価2025年5月22日時点でのオクタの株価は約124ドルで、年初来約14%の上昇となっています。株価売上高倍率(PSR)は約4.3倍と、同業他社と比較して割高感はなく、好決算が発表されれば、さらなる上昇余地があると見られます。一方で、予想を下回る結果となれば、株価の調整も考えられます。投資家への示唆個人投資家が注視すべきは、RPOとcRPOの成長率が二桁を維持できるか、そしてAI関連投資が営業利益率に与える影響を吸収できるかという点です。これらが確認できれば、オクタのAI時代におけるアイデンティティ管理のリーダーシップが裏付けられ、長期的な成長が期待されます。決算説明会では、新製品の商談状況やパートナー経由の売上比率など、今後の成長を占う重要な情報が開示される可能性が高く、注目されます。

米国債格下げと減税法案で米国債務リスクが意識され、株安・円高のリスクオフ展開へ|米国市場サマリー
先週は、米国債格下げ、政府の債務問題、トランプ大統領の政策発言などを背景に、全体として不安定な展開となりました。ムーディーズが米国債を「Aaa」から「Aa1」に格下げしたことを受けて市場心理が悪化。その後もトランプ政権が大型減税法案を推進したことで債務拡大への懸念が高まり、米国債利回りが急上昇し、株価は大きく下落する局面がありました。一方、半導体株を中心に好調な決算を発表した企業もあり、市場は上昇と下落を繰り返すボラティリティの高い状況が続きました。週後半にはトランプ大統領がEUに対する関税引き上げを示唆したことで再び投資家心理が冷え込み、主要指数は週間ベースで軟調な推移となりました。為替は、米国の財政悪化懸念や米国債格下げ報道を受けて円高が進みました。週初は145円台前半で始まりましたが、ムーディーズによる米国債格下げが嫌気されドルが売られました。20日以降も米国の減税法案に対する懸念や日米財務相会談を巡る円高警戒感が重なり、21日には一時143.2円まで下落しました。週末には米PMIが改善したものの財政不安は根強く、最終的に142.5円で取引を終えました。米国株式市場:米国債務リスクと米EUの貿易摩擦が意識されて下落5月19日(月) 米国株式市場はほぼ横ばいで取引を終えました。格付け会社ムーディーズが米国債の格付けを最上位の「Aaa」から「Aa1」に引き下げたことが市場心理に影響を与えました。S&P500は0.1%上昇し、6連騰を記録。ダウ平均は0.3%上昇、NASDAQは0.1%の小幅高でした。一方、Russell 2000は0.4%下落。個別銘柄では、TXNM EnergyがBlackstoneによる買収報道を受けて7%上昇し、Novavaxは新型コロナウイルスワクチンの承認取得で15%急伸しました。5月20日(火) 市場は反落し、S&P500は7営業日ぶり、ダウ平均は4営業日ぶり、NASDAQは3営業日ぶりの下落となりました。米国債利回りの上昇が重しとなり、エネルギー、通信サービス、一般消費財セクターが下落。トランプ大統領が大規模な減税法案の可決を求めたことが、連邦政府の債務増加懸念を強めました。個別では、Home Depotが予想を上回る売上高を発表したものの、株価は0.6%下落。Teslaはイーロン・マスク氏のCEO継続意向を受けて0.5%上昇しました。5月21日(水) 主要3指数が急落し、ダウ平均は816ドル安、S&P500は1.6%、NASDAQは1.4%下落しました。トランプ大統領の減税法案が政府債務の増加を招くとの懸念から、米国債利回りが急上昇。S&P500の11セクター中10セクターが下落し、不動産、ヘルスケア、金融などが特に弱含みました。個別では、Alphabetが2.7%上昇した一方、Apple(-2.3%)、NVIDIA(-1.9%)、Tesla(-2.7%)が下落。UnitedHealth Groupは報道を受けて6%近く下落し、Targetは売上高見通しの下方修正で5.2%安となりました。5月22日(木) 市場は不安定な取引の中、ほぼ横ばいで終了しました。下院がトランプ大統領の大型減税を含む法案を可決したことが影響し、序盤は米国債利回りが上昇しましたが、その後低下。S&P500とダウ平均はほぼ変わらず、NASDAQは小幅に上昇しました。セクター別では、公益事業、ヘルスケア、エネルギーが下落し、一般消費財、通信サービス、情報技術が上昇。個別では、Snowflakeが製品売上高見通しの引き上げで13%超急伸し、Alphabetも1.3%上昇しました。一方、Analog Devicesは決算後に4.6%下落し、First Solarは減税法案による補助金打ち切り懸念で4.3%下落しました。5月23日(金) 市場は下落し、S&P500は0.2%、ダウ平均は0.1%、NASDAQは0.3%それぞれ下落しました。トランプ大統領がEUからの輸入品に80%の関税を課す可能性を示唆したことが市場に影響を与えました。Appleはこの発言を受けて1.5%下落。セクター別では、情報技術、通信サービス、一般消費財が下落し、公益事業、金融、エネルギーが上昇。個別では、NVIDIAが1.2%下落し、Teslaは0.8%上昇しました。為替市場:米国債務リスクが意識され、安全資産の円が買われて円高に為替は、米国の財政不安や格下げ懸念を背景にドル売り・円買いが進行し、週を通じて下落基調となりました。週初19日は、ムーディーズによる米国債格下げの影響が残り、ドル円は145円台前半から144円台後半へと下落しました 。20日には、加藤財務相がベッセント米財務長官との会談で為替を議題とする可能性を示唆したことが円買い材料となり、ドル円は144.3円付近まで下落しました 。21日から22日にかけては、トランプ大統領の大型減税・歳出法案が共和党内での支持を得られず、財政赤字拡大への懸念が強まりました。これにより、ドル円は一時143.2円まで下落し、2週間ぶりの安値を記録しました 。週末23日には、米企業景況感の改善を示すPMIの発表を受けてドルが一時反発し、ドル円は144円台前半まで戻しましたが、財政不安の影響は根強く、最終的には142.5円で週を終えました 。この週のドル円相場は、米国の財政健全性への懸念が主な下落要因となり、安全資産とされる円への需要が高まりました。また、日米財務相会談での為替是正への警戒感も円買いを後押ししました。結果として、ドル円は約3円の値幅で推移し、週を通じて円高傾向が続きました。今週のマーケット:NVIDIA決算に注目今週(2025/5/26-5/30)は、過去何度も市場全体を動かしてきたNVIDIAの決算があり、PCEデフレーターなどでインフレ動向についても注目が集まります。ブルーモの公式Xでは決算や指標の速報をお届けしているので、興味ある方はフォローしてみてください。https://x.com/Bloomo_invest

【バフェットのポートフォリオ解説】金融株を縮小、昨年の新規投資4銘柄へ投資強化
ウォーレン・バフェット率いるバークシャー・ハサウェイ(BRK.B)の2025年3月末時点でのポートフォリオが、5月15日に米証券取引委員会(SEC)に提出された報告書「フォーム13F」にて明らかになりました。本記事では、バフェット氏のポートフォリオについて解説します。バフェットポートフォリオの中身バフェット氏は集中度の高いポートフォリオを運用していることで知られ、上場ポートフォリオは上位5銘柄で約70%、上位10銘柄で約90%を占めています。上位保有銘柄アップル(AAPL) : 25.8%アメリカン・エキスプレス(AXP) : 15.8%コカコーラ(KO): 11.1%バンク・オブ・アメリカ(BAC) : 10.2%シェブロン(CVX): 7.7%オキシデンタル・ペトロリアム (OXY): 5.1%ムーディーズ(MCO): 4.4%クラフト・ハインツ(KHC): 3.8%チャブ(CB): 3.2%ダビータ(DVA): 2.1%金融株の保有を圧縮アップル、アメリカン・エキスプレス、コカコーラなどの主要保有銘柄に大きな変化はありませんでしたが、昨年後半に続いて、2025年1-3月もバンク・オブ・アメリカ株が7.2%売却されました。バークシャーの2024年9月末時点のポートフォリオでは、バンク・オブ・アメリカ株はポートフォリオの中で2番目に大きなポジションを占めていましたが、コカコーラに次ぐ4番目のポジションとなりました。また、シティグループ(C)、ヌー・ホールディングス(N)の全持ち株を売却。キャピタル・ワン・ファイナンシャルについても保有比率を4%縮小し、金融株からの撤退が目立ちました。このほか、オキシデンタル・ペトロリウムをわずかに追加購入し、ダビータの持ち分が減少していますが、ポートフォリオ全体への影響は軽微となっています。昨年の新規投資4銘柄へ投資強化一方で、追加購入規模は小さいものの、価格決定力のある消費者向け事業への投資が注目を集めています。2024年10-12月期に新規投資を開始した、米国最大のビール輸入会社のコンステレーション・ブランズ(STZ)の株式は560万株から倍増し、1,200万株超に増やしました。同社は、米国でコロナビールとモンデロビールの輸入・独占販売権を持つことで知られ、ロバート・モンダヴィといった高級ワインやスピリッツのブランドもいくつか所有しています。2024年7-9月期に新規投資が明らかになった、プール(POOL)への投資は145%、ドミノ・ピザ(DPZ)への投資は10%増加。2024年3-6月期に新規投資を開始したハイコ(HEI.A)への投資は11%増加しました。また、バークシャーは当四半期において一部の株式投資の開示を非公開とする「秘密保持請求」をSECに行っており、チャブの株式を非公開で保有していた過去の戦略を彷彿とさせます。この機密扱いの株式は、今後数四半期の開示で判明する可能性が高いですが、「商業、工業、その他」のカテゴリーに分類されており、バロンズは工業会社の可能性があると推測しています。手元資金は約50兆円に、バフェット氏は年末退任バークシャーは10四半期連続で株式を売り越し、現金と米短期債保有額を合計した広義の手元資金は3月末時点で3477億ドル(約50兆円)に達しました。国債利回りが高止まりする中、バークシャーは多額の利息収入を獲得しつつ、将来の投資機会に備えて流動性を確保しています。また、5月3日に開催された年次株主総会で、バフェット氏は年末までにCEOを退任する意向を発表しました。バフェット氏の退任後、後任としてグレッグ・エイベル副会長が就任する予定です。バフェットポートフォリオを簡単コピー?ブルーモ証券では、2025年3月末時点でのバークシャーのポートフォリオをワンタップでコピーし、投資を始めることができます。株式のみで構成されるポートフォリオのほか、米短期債を含む手元資金を反映したポートフォリオのコピーもできますし、そこから変更を加えてオリジナルのポートフォリオの作成も可能です。
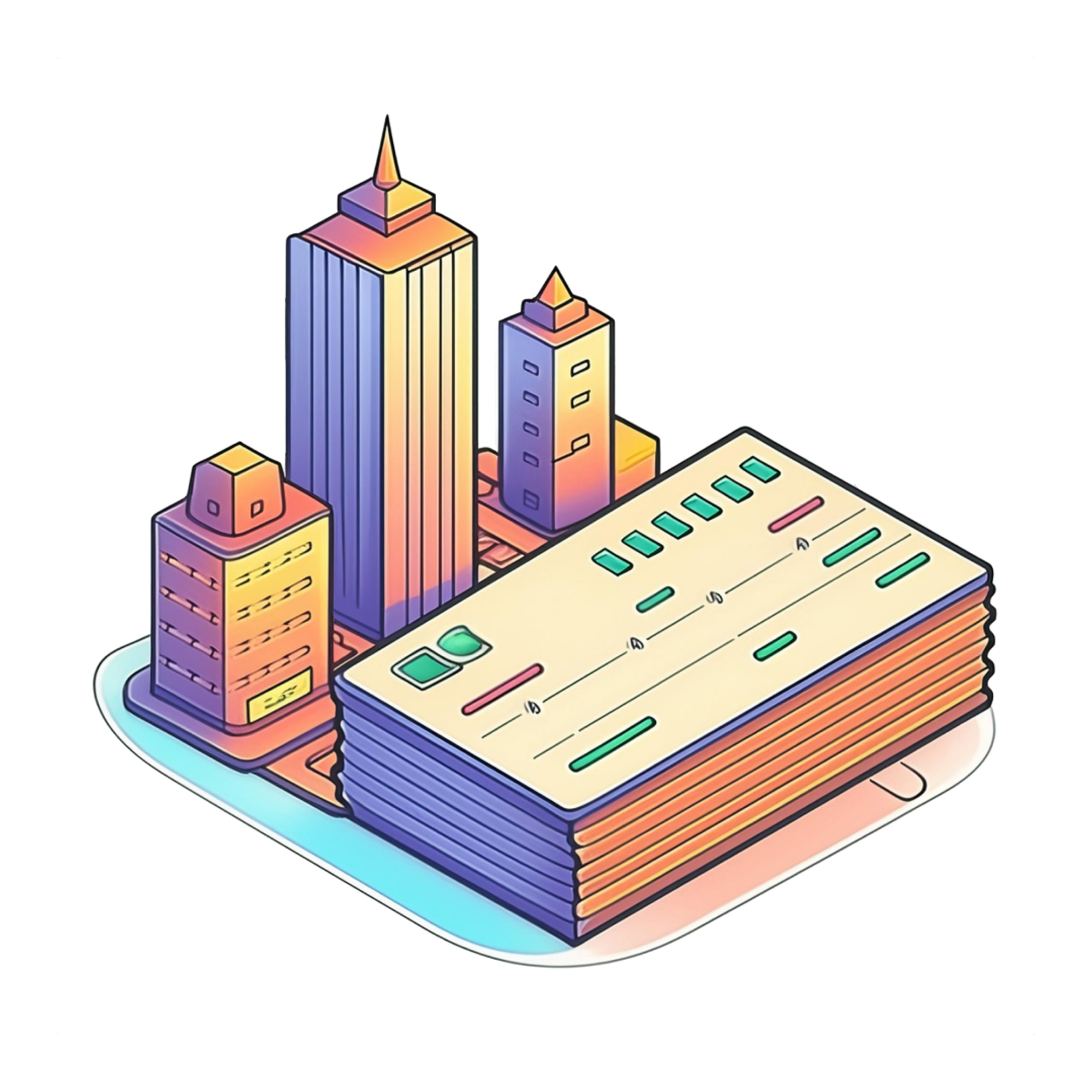
なぜ「マールアラーゴ合意」が注目? 財政危機とドル安誘導への波紋
2025年に入り、米ドル安誘導を目指す「マールアラーゴ合意(プラザ合意2.0)」構想が、金融市場の中心的な議題として浮上しています。本記事では「マールアラーゴ合意」とは何かを解説し、注目される背景について説明します。国際金融秩序の再編を掲げる「マールアラーゴ合意」マールアラーゴ合意(Mar-a-Lago Accord)とは、米ドル高を是正し、米国の債務負担や貿易不均衡を再構築する構想であり、2024年6月に元クレディ・スイスの著名アネリストのゾルタン・ポザール氏が考案したものです。同年11月に当時ハドソン・キャピタルのシニアストラテジストであったスティーブン・ミラン氏が 「世界貿易システム再構築のためのユーザーガイド」 で取り上げ、関税、為替調整、債務再編を通じて貿易不均衡を改革するロードマップを提示しました。その後、トランプ大統領がミラン氏を経済諮問委員会(CEA)委員長に指名したことで、市場の注目を集めるようになりました。「マールアラーゴ合意」という名称は、1985年にG5(米・日・独・仏・英)が協調してドル高是正を目指した「プラザ合意」に由来し、トランプ氏の私邸があるフロリダ州パームビーチの「マールアラーゴ」にちなんで名付けられました。トランプ政権内では、この私邸にて通貨政策の国際的な合意を目指すことが検討されていると報じられています。債務再編とドル安誘導への警戒米国の財政赤字と国債の大量発行は、金融市場の大きな懸念材料となっています。2025年1月に債務上限が再適用されて以降、政府は資金繰りのための「特別措置」を講じていますが、議会予算局(CBO)は8月中にも財政資金が尽きる可能性が高いと指摘しています。これを背景に、米国債の信用リスクが意識され始め、投資家が求めるリターン(リスクプレミアム)は上昇しています。5月19日の取引では、30年債利回りが5%を超え、2年債やそれ未満の短期債でも一時4%を上回るなど、2007年や金融危機の前の水準に近づいています。こうした状況の中、ドル安を誘導し、米国債の借り入れコストを抑えるという政策課題が、マールアラーゴ合意に対する注目を高める一因となっています。一部では、トランプ政権が「他国が保有する米国債と米100年債を交換を奨励する」可能性も取り沙汰されています。スコット・ベッセント氏は、財務長官に指名される前の2024年6月「今後数年間で壮大な経済再編が起こる」と予想し、プラザ合意に類似するドル是正政策が動き出す可能性に言及していました。実現性は乏しいが、現行体制を問い直す契機にしかし、マールアラーゴ合意の実現可能性は現時点では非常に低いとされています。外国の債権者は、自国が保有する米国債の価値を毀損するような金融改革に応じる可能性は低く、また日本、英国、中国といった米国債の主要保有国は政治・地政学的な利害が複雑に絡み合っており、協調は困難を極めます。さらに、債務条件の変更は事実上の「デフォルト(債務不履行)」と見なされ、米国債の信用に対する再評価、そして長期金利の急騰を招くリスクも無視できません。マールアラーゴ合意は、ドルの基軸通貨としての信認、財政持続性、国際協調の枠組みなど、現行体制の持続可能性を問い直す材料となっており、今後の議論の行方が注目されます。
.png)
【ワークデイ決算みどころ】AI投資の成果と成長持続力、株価上昇への試金石に(Workday)
本記事では、ワークデイ(WDAY)の2025年2月発表2025年度第4四半期決算を振り返り、5月に控える2026年度第1四半期決算の見どころを解説します。前回決算では、売上高22.1億ドル(前年同期比+15%)、調整後EPS1.92ドルと市場予想を上回り、発表直後に株価は10%以上上昇しました。しかし、AI投資を優先するために1,750人の人員削減を発表するなど、成長と効率化のバランスを模索しています。今回の決算では、サブスクリプション収益の成長維持、AIエージェントの導入効果、通期ガイダンスの修正有無が注目されます。前回決算の概要2025年2月25日に発表された2025会計年度第4四半期決算では、売上高22.1億ドルのうちサブスクリプション収益が20.4億ドルと前年同期比16%増を記録し、求人市場の回復を背景にHCM(人材管理)需要が堅調でした。調整後EPSは1.92ドル(前年同期は1.57ドル)とコンセンサス1.75ドルを大幅に上回り、連続4四半期の“ビート”を達成しています。発表後の時間外取引で株価は11%上昇し、市場がAIドリブン成長ストーリーを改めて評価した形です。経営陣は2026会計年度第1四半期のサブスクリプション収益を20.5億ドル、通期を88億ドルとガイダンスしましたが、保守的との見方も出ています。2月以降の主要な動向四半期終了後、ワークデイはAIロードマップを加速しています。3月の「Spring Release 2025」では350以上の新機能を投入し、タレントマネジメントや財務ワークフローに生成AIを本格実装しました。5月19日には7種類の目的別AIエージェントを束ねる「Illuminate Agents」を発表し、契約交渉や帳票起票など高付加価値領域の自動化へ踏み込みました。一方、人員の8.5%に当たる1,750人削減を2月上旬に実施。AI・海外展開へ資源を再配分する狙いですが、サービス品質低下を懸念する声もあります。製品面ではGoogle Cloud出身のゲリット・カズマイヤー氏がプロダクト部門トップに就任し、プラットフォーム戦略の刷新をけん引しています。今回決算の注目ポイントサブスクリプション収益の成長維持Zacksコンセンサスは売上22.2億ドル(+11.3%)、EPS1.99ドル(+14.4%)を予想しています。売上の約9割を占めるサブスクリプションがガイダンス通り+11%前後を維持できるかが第一の焦点です。AI製品によるARR押し上げSpring ReleaseとIlluminate Agentsが早期にクロスセルにつながれば、年間経常収益(ARR)の上振れ余地が生まれます。顧客基盤11,000社のうち先行導入企業のROI事例が開示されれば、AIマネタイズ期待が株価のサポート要因となるでしょう。コスト構造とマージンレイオフ費用は一過性ですが、AI投資増との綱引きで営業利益率の方向感が試されます。前四半期の調整後営業マージン26%が維持できれば、利益成長への信頼感が高まります。ガイダンスの更新通期サブスクリプション88億ドル計画が上方修正されるかが株価の分水嶺です。反対に見通し据え置きや保守化が示されれば短期調整も想定されます。株価動向と投資家への示唆株価は現在273ドル前後で年初来+15%。PSRは約7.5倍と過去5年平均にほぼ沿う水準ですが、生成AIプレミアムを織り込み始める局面にあります。好決算でガイダンスが上振れれば300ドル台回復も視野に入る一方、EPSや成長率が鈍化すれば260ドル付近までの押しも想定しておきたいところです。特にサブスク伸長率・AI導入比率・営業マージンの三点が市場再評価の鍵を握ると考えます。まとめワークデイは「クラウド×AI」でHCM・財務領域の標準化を狙う長期成長シナリオを描いています。今四半期は税務シーズンのない端境期ながら、AIエージェントの立ち上がりとガイダンス更新が注目点です。個人投資家は決算後のカンファレンスコールで提示されるAI収益化ロードマップとコスト最適化策を確認し、バリュエーションに対する上値・下値余地を見極めると良いでしょう。
.png)
【イントゥイット決算みどころ】税務シーズン総括とAI投資の成果、上昇基調維持なるか(Intuit)
本記事では、イントゥイット(INTU)の2025会計年度第2四半期決算を振り返り、5月に控える第3四半期決算決算の見どころを解説します。ターボタックス、クイックブックス、メールチンプ、クレジットカルマといった主力製品を擁する同社にとって、税務申告シーズンにあたるこの四半期は、年間でも最も重要な期間の一つです。個人投資家にとっても、今後の株価動向を占う上で注目すべき決算となるでしょう。前回決算(2025年2月発表)のハイライト2025会計年度第2四半期(2024年11月〜2025年1月)において、イントゥイットは売上高40億ドル(前年同期比+17%)を記録し、市場予想を上回りました。特に、グローバルビジネスソリューション部門(QuickBooksなど)が+19%と牽引し、オンラインエコシステムの売上も+21%と好調でした。また、Credit Karma部門も+36%と復調の兆しを見せました。一方で、消費者向け部門(ターボタックスなど)は+3%にとどまり、翌四半期のEPSガイダンス(10.89〜10.95ドル)は市場期待の11.5ドルを下回りました。2月以降の主要ニュースと動向2月以降、イントゥイットはAI技術の活用を強化しています。ターボタックスでは、Google Cloudの生成AI「Gemini」を活用した税務フォームの自動入力機能を拡張し、ユーザー体験の向上を図っています。また、メールチンプでは150以上の新機能を追加し、SMSやShopifyとの連携、AIアシスタントの強化を進めています。さらに、英国では中小企業向けのAI導入を推進する「Small Business Growth Council」を発足し、国際的な成長を加速させています。加えて、AI投資を優先するための人員再配置(約1,800人削減・同数採用)を2024年7月に実施し、コスト圧縮と成長人材の確保を両立させています。今回決算(2025年5月22日発表)の注目ポイント税務シーズンの最終着地アナリスト予想では、売上高75.4億ドル(前年同期比+12%)、Non-GAAP EPS10.89ドル(+10%)と堅調な伸びが見込まれています。消費者向け部門の成長がガイダンス通り7〜8%に回復できるか、AI入力機能の浸透度が鍵となります。QuickBooksオンラインエコシステムの成長中核となるグローバルビジネスソリューション部門のオンライン売上は前年同期比+21%でした。今回の決算でも20%前後の成長維持が達成できるかが注目されます。4月の機能アップデートでAIアシスタントやエンタープライズ統合を強化しており、ARR(年間経常収益)の加速が期待されます。さらに、CEOは「自律型AIエージェント」構想を示唆しており、中長期のユースケース拡大も重要な論点です。Credit Karmaの反発力クレジット市場の回復により、前四半期には+36%の成長を示しました。今回の決算でもこの勢いが続くかが注目されます。引き続き、広告単価と口座開設数の動向を確認する必要があります。通期ガイダンスの修正有無通期売上高18.25億ドル、EPS19.26ドルの従来見通しが据え置かれるか、上方修正されるかで株価の初動が変わります。株価動向と投資家への示唆現在、イントゥイットの株価は約670ドルで、年初来+18%と堅調に推移しています。PSR(株価売上高倍率)は約9倍と過去平均(約7倍)より高水準なため、数字の上振れがない場合はバリュエーション調整リスクに留意する必要があります。決算で税務シーズンの強さとAI投資の回収計画が確認できれば、再度上場来高値(700ドル台)への挑戦も期待されます。逆にEPSガイダンスが据え置き以下であれば、短期的な調整も想定されます。個人投資家としては、クラウド比率の拡大ペース、AI機能によるARPU(ユーザーあたり平均収益)の上昇、来期の投資額とマージン指標を重点的に確認すると良いでしょう。
.png)
【Zoomコミュニケーションズ決算みどころ】AI収益化の進捗とAmazon効果、保守ガイダンス打破の行方(Zoom Communications)
本記事では、Zoomコミュニケーションズ(ZM)の2025年2月発表2025年度第4四半期決算を振り返り、5月に控える2026年度第1四半期(2月〜4月)決算の見どころを解説します。前四半期はAIコンパニオンを核にしたプラットフォーム化が奏功し、売上11.84億ドル・調整後EPS1.41ドルでコンセンサスを上回りました。しかし会社側が示した今期売上ガイダンス(11.62〜11.67億ドル)は市場予想を下回り、株価は発表翌日に8%下落しました。今回はAI関連サービスの伸び、Amazonを筆頭とする大型顧客の契約寄与、保守的と評された通期見通しの再修正可否が、株価83ドル前後のもみ合いを抜け出す鍵となります。前回(FY25 Q4)決算の振り返り2025年2 月発表のFY25 Q4では、売上が前年同期比3.3%増の11.84億ドル、営業CFは4.25億ドルと20%超の伸びを示しました。エンタープライズ売上は7.07億ドルで+5.9%と堅調、10万ドル超顧客は4,088社へ7.3%増加し、AI Companionの月間アクティブユーザー(MAU)は前四半期比68%拡大しました。一方、パンデミック後の減速を映しオンライン売上が微減に転じたことから、同社はFY26 Q1売上を11.62〜11.67億ドル、EPS1.29〜1.31ドルと慎重にガイドしました。決算後から現在までの主要トピック3 月にはAmazonが社内標準の会議アプリにZoomを採用すると報じられ、大手テック企業への大型導入実績が加わりました。さらに、社名から「Video」を外しAIファースト企業として再ブランディングを宣言し、Zoom Workplace・AI Companion 2.0の提供を本格化させています。4 月16 日には世界的なサービス障害が発生したものの数時間で復旧、信頼性リスクへの対応が問われました。株価はガイダンス失望で急落後も80〜88ドルのレンジで推移し、5 月19 日の終値は83.31ドル(52週高値比-10%)です。今回(FY26 Q1)決算の注目点AIコンパニオンとエンタープライズ成長Zacksコンセンサスは売上11.6億ドル、EPS1.30ドルで前年比2%増収・4%減益を想定しています。MAUが急伸したAI Companionがいかにアップセルを生み、エンタープライズ比率を60%超へ高められるかが焦点です。ガイダンスとマージン会社は通期売上を47.85〜47.95億ドル(+2.6%)と見込んでいますが、AI機能の課金拡大や大型契約効果が数値に上乗せされるかが注目です。AI投資による粗利圧迫をオペレーション最適化で吸収し、非GAAP営業利益率を約39%で維持できればポジティブ評価が期待されます。大口顧客動向Amazonの全面導入決定は象徴的勝利であり、契約規模の具体的な売上寄与が会見で示されるか関心が集まります。加えてWorkvivoやContact Centerのクロスセルが続き、10万ドル超顧客数が四半期でどこまで増えるかが成長持続性のバロメーターとなるでしょう。株価インパクトのシナリオ過去4四半期ベースでZoomは平均10%のEPSサプライズを示してきましたが、今回は市場期待値が低めに調整されているため、売上がガイダンス上限を超えれば心理的なリリーフラリーで90ドル台回復も視野に入ります。逆に売上が下限にとどまり通期見通しも据え置きの場合、AI成長の鈍化懸念が再燃し75ドル近辺までの調整もあり得ます。個人投資家への視点Zoomはパンデミック特需の反動局面を経て、AIプラットフォームへの転換で再成長を図っています。今回決算ではAI Companionの実収益化の進度、Amazonをはじめとする大型顧客の拡張効果、そして慎重ガイダンスを跳ね返す受注トレンドを見極めることが重要です。業績ビートと上方修正の両輪が揃えば株価には依然魅力的なリバウンド余地がありますが、競合のMicrosoft Teamsや経済環境の変化も織り込み、ポジションサイズとホライズンの明確化を怠らない姿勢が求められます。
.png)
【スノーフレーク決算みどころ】AI事業の本格収益化と成長持続力が焦点(Snowflake)
本記事では、スノーフレーク(SNOW)の2025年2月発表2025会計年度第4四半期決算を振り返り、5月に控える2025年度第1四半期(2月〜4月)決算の見どころを解説します。今回の決算は、同社が高い成長を維持しつつ、新たな成長エンジンであるAI(人工知能)関連事業でどれだけ成果を出せているかを示す重要なイベントとなります。前回決算(2024年11月〜2025年1月)の主なポイント前回の決算では、Snowflakeは市場予想を上回る強い結果を出しました。売上高は前年比27%増の9億8,680万ドル、その中でも主力のプロダクト売上が9億4,330万ドルと、前年比28%増という好調な伸びを見せました。利益面でも調整後の1株当たり利益(EPS)が0.35ドルとなり、市場予想の0.18ドルを大きく超えています。顧客基盤も堅調で、年間100万ドル以上支出する大口顧客数は580社に達しました。ただ、顧客がどれだけ継続的に利用を拡大しているかを示す「ネット売上継続率」は126%と引き続き高水準ながら、やや伸びが鈍化している点には注意が必要です。将来の売上を占う「残存契約価値(RPO)」は69億ドル(前年比33%増)となり、成長の持続性が確認されました。こうした好決算を受けて、発表直後の株価は約9%の上昇を記録しました。前回決算以降の主な取り組み決算発表後、SnowflakeはAI関連事業を一段と加速させています。特に生成AIプラットフォームである「Cortex」の拡張に注力しており、Meta社の「Llama 2」など外部企業の最先端モデルを自社サービスに統合しました。これにより、顧客企業はより高度なAI分析や検索機能をSnowflakeのプラットフォーム内で容易に使えるようになっています。さらに、自社の大規模言語モデル「Arctic」をオープンソースとして公開しました。企業が自社のデータを活用して独自のAIモデルを構築できる環境を提供し、競合であるDatabricksに対抗しています。また、半導体大手のNVIDIAとも提携を深め、「AIファクトリー」構想を推進しています。これは、Snowflakeのデータ基盤とNVIDIAのAI処理技術を融合させ、企業が効率的にAIを導入・運用できるプラットフォームを作るというものです。新たにCEOに就任したスリダール・ラマスワミ氏(元Google広告部門トップ)も、Snowflakeを「AIデータクラウド企業」へと再定義し、AI関連サービスの強化を中心とした経営戦略を明確に打ち出しています。今回決算(2025年2月〜4月期)の注目ポイント今回の決算では、まずプロダクト売上の成長率が注目されます。会社は21〜22%増の9億5,500万〜9億6,000万ドルの売上を予想していますが、もしこれが市場予想を上回り25%程度の伸びを達成できれば、成長鈍化懸念が払拭され、株価にも好影響を与えるでしょう。さらに、年間を通じた通期の売上見通し(現状前年比24%増の42億8,000万ドル)を上方修正できるかどうかも重要なポイントです。今回の業績が堅調であれば、会社側が自信を示し、年間見通しを引き上げる可能性があります。逆に通期見通しが据え置かれるか、あるいは引き下げられると市場の期待は後退し、株価にとってネガティブ要因となります。利益面では、非GAAPベースの営業利益率(前回は9%)がさらに改善し、2桁台に乗るかが焦点です。AI関連の新規投資コストがかさむ中、利益率が上昇することは同社の効率化努力が成果を挙げていることを示し、投資家からの評価が高まるでしょう。一方、利益率が低下すると、コスト構造への懸念が強まり、株価へのマイナス影響が出る可能性があります。AI関連サービスの具体的な導入件数や、実際の売上貢献について初めて詳しく開示されるかどうかにも注目です。導入実績や収益貢献度が具体的に示されれば、市場はSnowflakeのAI戦略を評価し、中長期的な成長期待が高まります。しかし、導入状況が不透明であれば、「AI事業がまだ収益に寄与していない」という認識が強まり、株価にとってマイナス材料となります。株価への影響と投資家への示唆今回の決算内容次第で、株価には以下のような影響が考えられます。好材料として、売上が予想を超え、通期ガイダンスも引き上げられ、さらにAI関連サービスの具体的な導入件数が示されれば、投資家の期待が再び高まり株価が上昇する可能性が高まります。逆に、売上成長率が会社の予想を下回り、利益率が低下し、AI関連サービスの導入が不透明な状況であれば、成長期待の後退から株価の下落リスクが高まります。総じて、今回の決算はSnowflakeにとってAI事業がどれだけ現実の収益につながっているかを示す重要な試金石です。成長を再加速できるか、それとも一旦成長の踊り場を迎えるか、今回の結果と経営陣のメッセージを慎重に見極め、投資判断に役立てることが個人投資家に求められるでしょう。
.png)
【TJXカンパニーズ決算みどころ】ディスカウント需要追い風の客数増と粗利防衛、還元強化策に注目(The TJX Companies)
本記事では、TJXカンパニーズ(TJX)の2025年2月発表2025会計年度第4四半期決算を振り返り、5月に控える2025年度第1四半期決算の見どころを解説します。前回(2025年2月発表)の第4四半期は既存店売上高+5%、EPS1.23ドルといずれも計画を上回り、同時に増配13%と最大25億ドルの自社株買いを発表しました。 足元では、高インフレ下での「節約志向」を追い風に客数増が続き、アナリスト予想は売上130億ドル、EPS0.91ドルと堅調な伸びを見込んでいます。 本稿では前回決算のポイント、直近ニュース、そして今回決算で注視すべき論点を整理し、株価インパクトを展望します。前回決算の振り返り2025年2月発表の第4四半期(FY25)は、売上164億ドルと前年並みながら、在庫縮小とマージン改善が奏功しPretaxマージンは11.6%へ拡大しました。EPSは1.23ドルと前年を上回り、市場予想1.16ドル前後もクリアしました。 通期では売上563億ドル、EPS4.26ドルと過去最高を更新し、年間営業キャッシュフローは61億ドルに達しました。 株主還元にも積極的で、FY25通期の配当と自社株買い合計は41億ドル、配当は6月支払分から1株0.425ドルへ13%引き上げると表明しています。決算後から現在までの主な動き3月末には取締役会が13%の増配を正式決定し、資本政策の安定感を再確認させました。 一方、米中関税緩和期待や生活必需品インフレを背景に、オフプライス各社への客足は拡大傾向にあり、TJ Maxxで+3.8%、Marshallsで+3.3%のフットトラフィック増が報告されています。 株価は年初来で約10%上昇し、5月19日時点で135ドル前後と過去最高圏を推移しています。 ただし会社側はQ1について、昨年の一時益剥落や賃金上昇を勘案しPretaxマージン10.0〜10.1%、EPS0.87〜0.89ドルと保守的な計画を提示しています。今回決算の注目点まず売上とEPSがアナリスト平均(130億ドル・0.91ドル)を上回るかが最大の焦点です。 上振れの鍵は「客数主導」の既存店売上高で、ガイダンス上限3%を超える伸びが示されればポジティブです。次に利益率ですが、前期貢献の在庫縮小効果が薄れる一方で輸送費は低位安定しており、在庫ロス(シュリンク)と賃金上昇の綱引きが注目されます。また、FY26通期ガイダンス(EPS4.34〜4.43ドル)が維持または上方修正されれば、増配・自社株買いと合わせて株主還元ストーリーに厚みが増すでしょう。株価へのインプリケーション過去10回の決算では初日株価が上昇した確率は約70%、中央値は+3.8%です。 今回も数字が小幅にビートするだけで買い安心感が広がる可能性があります。一方、EPSが会社計画の下限にとどまりガイダンスも据え置きとなれば、賃金コスト警戒が再燃し130ドル台前半への押し戻しも想定しておきたいところです。投資家への示唆TJXは景気減速局面で真価を発揮するディフェンシブ性と、強固なフリーキャッシュフローによる株主還元力を兼ね備えています。直近の株価は高値圏ながら、コンプ売上の客数増に支えられたトップライン成長と継続的な買い戻しが下値を支える形です。今決算では、売上・EPSの「小幅ビート」だけでなく、中期的な粗利率防衛策や在庫水準の健全性といった定性的コメントにも注目し、長期目線での保有是非を見極めることをお勧めします。
.png)
【パロアルトネットワークス決算みどころ】AI投資の成果と利益率維持が株価回復のカギに(Palo Alto Networks)
本記事では、パロアルトネットワークス(PANW)の2025年2月発表の第2四半期決算を振り返り、5月に控える第3四半期決算の見どころを解説します。前回の第2四半期決算では、売上高が前年同期比14%増の23億ドル、調整後EPSが0.81ドルと市場予想を上回りましたが、通期ガイダンスの引き下げにより株価は下落しました。その後、同社はAIセキュリティ分野での大型買収や新製品の投入を進めており、今回の決算では成長戦略の再評価と利益率の動向が注目されます。前回決算の概要2025年2月の第2四半期決算では、売上高が23億ドル、調整後EPSが0.81ドルと、いずれも市場予想を上回る結果となりました。特に、サブスクリプション中心の次世代セキュリティARRが前年同期比37%増の48億ドルと高成長を維持し、粗利率も約74%と堅調でした。しかし、経営陣は価格競争の激化や大型案件サイクルの伸びを理由に、通期ガイダンスを引き下げました。これにより、発表翌日に株価は7%下落しました。その後の主要な動向第2四半期決算後、パロアルトネットワークスは生成AI分野での取り組みを強化しています。4月末には、AIセキュリティ管理のスタートアップであるProtect AIの買収を発表し、AI特有のリスクに対応する体制を構築するとしています。また、新たに公開したプラットフォーム「Prisma AIRS」は、AIモデルやデータの可視化を可能にする統合基盤として注目されています。さらに、RSA Conference 2025では、SOC自動化を進化させた「Cortex XSIAM 3.0」やPrisma SASEの大幅な拡張を発表し、プラットフォーム間のクロスセルを狙う戦略を強調しました。CEOのニケシュ・アローラ氏は、「AIによる攻撃の増加を逆手に取り、当社が“安全なAI”の守護者になる」と述べ、長期的な成長戦略への自信を示しました。今回決算の注目ポイントアナリストの予想では、第3四半期の売上高は22.8〜22.9億ドル(前年同期比15%増)、調整後EPSは0.77〜0.79ドルと見込まれています。注目すべき点は、次世代セキュリティARRの成長維持、Protect AI買収や新製品立ち上げによる営業利益率への影響、そして通期売上成長率の上方修正の有無です。特に、ARRの成長が減速すれば、バリュエーションの前提が揺らぐ可能性があります。また、投資拡大による営業利益率の低下が懸念される中、前四半期の25%強を維持できるかが注目されます。通期売上成長率の上方修正があれば、成長ストーリーの再評価が進むでしょう。株価とバリュエーションの現状2025年5月20日時点で、パロアルトネットワークスの株価は約194ドルで、年初来約7%の上昇にとどまり、S&P 500をわずかに下回っています。PSR(株価売上高倍率)は約11倍と、同業のクラウドセキュリティ銘柄に比べて目立ったプレミアムはなく、決算で成長加速が示されれば210ドル台への戻り余地が開けます。一方で、EPSやガイダンスが市場期待を下回れば、180ドル近辺までの調整も想定されます。投資家への視点個人投資家が注視すべきは、AI関連の買収と新プラットフォームが早期にARRの押し上げに寄与するか、そして投資拡大フェーズでも粗利率・営業利益率が下げ止まるかという点です。これらが確認できれば、長期的には「ネットワーク+セキュリティ+AI」を統合する唯一無二のポジションが評価され、株価は再び史上高値圏を目指すシナリオが見えてきます。逆に、短期的なコスト増やガイダンス据え置きが続くなら、市場はプラットフォーム転換の時間軸を慎重に織り込み直すでしょう。

【ホームデポ決算みどころ】住宅市場の低迷と消費者心理の変化が業績に影響(Home Depot)
本記事では、ホームデポ(HD)の2025年2月発表2025会計年度第4四半期決算を振り返り、2025年5月20日に2025年度第1四半期(2月〜4月期)に発表した決算の見どころを解説します。前回の決算では減益ながら市場予想を上回る売上と配当増を示し、株価は底堅い動きとなりました。以降、生成AI「Magic Apron」の導入や大型物流拠点の買収など、長期競争力を高める施策が相次いでいます。今期は住宅着工の持ち直しや対中関税の緩和が追い風となる一方、高金利環境によるDIY需要の鈍化が逆風となる可能性があります。個人投資家が注視すべきは、既存店売上の底打ち確認、AI・M&A投資が粗利率に及ぼす影響、そして2025年度ガイダンスの修正有無です。前回決算の概要2024年度第4四半期(11〜1月期)の決算では、売上高が397億ドルで前年同期比14.1%増となり、市場予想をわずかに上回りました。一方、調整後EPSは前年の3.30ドルから3.07ドルへ減少しましたが、想定より小幅な落ち込みで投資家の失望を抑えました。経営陣は2025年度通期について「総売上+2.8%、EPS−3%」という控えめな指針を示しつつ、13店舗の新規出店と営業利益率13%確保を掲げています。同時に四半期配当を2.2%増やし、連続増配年数は16年に到達しました。2月以降の主要な動向3月、ホームデポは顧客のDIY相談に生成AIで答える「Magic Apron」スイートを正式公開しました。このツールはチャット形式で工具選定や工数見積もりを支援し、客単価引き上げを狙っています。物流面では、ジョージア州サバンナの140万平方フィート配送センターと隣接地を取得し、ハリケーン時の供給網強化を図りました。さらに、昨年発表した建材卸大手SRSディストリビューションの買収(1.8兆円規模)について、当局審査が進捗し年内完了見込みとの報道が続いています。マクロ環境では住宅着工とリフォーム需要の先行指標が緩やかに改善し、2025年前半のプロ顧客案件も増加傾向にあります。4月に米国が中国製工具などの追加関税を大幅に引き下げたことで、仕入れコスト圧縮と在庫回転の正常化も期待されています。今回決算の注目ポイント第1四半期は春のDIYシーズンが立ち上がる重要な時期です。アナリストは売上393〜396億ドル(前年+1〜2%)、EPS3.55〜3.65ドルを予想しており、前年の住宅低迷からの回復度合いに注目が集まります。既存店売上(コンプセール)昨年度は通期で-3.0%と2年連続マイナスでした。経営陣は2025年度に+1%を掲げていますが、早期にプラス転換できるかが株価のモメンタムを左右します。粗利率とAI・M&AコストMagic ApronやSRS買収関連のIT・統合費用が重なる中、ガイダンス通り粗利率33.4%前後を維持できるかが焦点です。投資先行でマージンが想定を下回れば、短期的な評価調整もあり得ます。通期ガイダンスの更新住宅市場の底入れと関税緩和を織り込み、売上成長率・EPS見通しを上方修正するかどうかが最大の注目点です。逆に据え置きや下方修正なら“高値警戒感”が強まりかねません。株価動向と投資家への示唆5月20日時点で株価は約320ドル、年初来+6%でS&P 500を若干アウトパフォームしています。関税緩和報道で月間5%上昇したものの、依然200日移動平均線近辺での攻防が続きます。PSR(株価売上高倍率)は約2.2倍と過去5年平均(2.0倍)をわずかに上回る程度で、ガイダンスの上振れ余地が評価されれば一段高も視野に入ります。エバコアISIは決算前に投資判断を「タクティカルアウトパフォーム」に引き上げ、通期指針の据え置きを想定しつつ短期の上値余地を指摘しました。投資家は、既存店売上の反転タイミング、Magic Apronの利用率と客単価効果、SRS買収シナジーの初期計数、粗利率/在庫日数の変化を中心に確認したいところです。好決算で通期見通しが上方修正されれば340ドル台の戻り高値試し、逆にコンプセールやマージンが想定を下回れば300ドル近辺までの調整リスクも念頭に置く必要があります。まとめホームデポは住宅市場の回復とAI・M&A投資の二本柱で長期成長を狙っています。今回の決算はその初速を測る試金石であり、ガイダンス修正の方向性が株価を大きく動かす可能性があります。個人投資家は決算後のカンファレンスコールで示される需要環境や投資回収計画を注視し、自身のリスク許容度と照らし合わせたポジション管理を行うことをお勧めします。